Short Short Collections
主にTwitterのワンライ企画やお題で書いたショートショートをまとめています。
男女もの・BLもの・その他いろいろごちゃ混ぜです。
2021年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
俺の頭の調子はもっとおかしい
#BL小説
ちょっと二次創作みたいなノリになってしまいましたw
風邪を引いた主人公のもとに見舞いにやってきた親友は、どこか色っぽいと感じてしまう雰囲気を普段から持っていた。
それは彼を好きと思っているから? いや、そんなはずはない。友達としてしか見ていないはずなんだ。
続きを表示します
----------------
久しぶりに風邪を引いた。
前日は中学生以来の三十八度まで熱があがってしまったが、なんとか微熱より強い程度まで下がってくれた。うまくいけば明日には復活できるかもしれない。
一人きりは寂しくて嫌いというタイプではないのに、風邪特有のマジックか心細さを感じてしまう。本当に若干だが。
『ちゃんとおとなしく寝てろよ? お前、ただでさえ落ち着いてらんないタイプなんだから』
休みのメッセージを送った友人からの返信を思い出す。
大学の入学式で出会ってから一番仲がよくて気の合う、いわゆる「親友」という間柄だ。
昨日は見舞いの打診をされたが、風邪がうつると大変だからとお断りのメッセージを送っていた。それでも彼のことだから、抜き打ちでやってくる可能性が高い。
意外と面倒見のいいやつだから、黙って見過ごせないとかそういうことなのだろう。だとしても彼女じゃあるまいに、放っておいても問題ないのに。
「彼女がいたらお願いしちゃうかもだけどな〜」
看護婦のようにやわらかな笑顔を向けられながら、甲斐甲斐しく世話をしてもらいたい。
『どうだ? 身体、少しはさっぱりしたか?』
『ああ。拭いてもらっちゃってほんと悪い。めんどくさかったろ?』
『なに言ってんだよ。付き合ってるんだからこれくらい当たり前だって』
『そ、そっか。そう、だよな』
『全く、そんな風に照れられたら困るだろ……手、出せないのに』
「ってなんでアイツ思い浮かべてんだ俺はよー!」
かすれてパワーのない叫びでもせざるを得なかった。照れた親友の顔を思い出してひいい、と情けない悲鳴ももれる。
ダメだ、予想以上に頭をやられている。彼「女」がいいのにどうして彼「氏」なんだそこで!
……確かに、あの親友は同性の目から見ても変に色っぽい雰囲気を醸し出すことがあるが、全くもって関係ない。関係ないはずなんだ。
「……んあ? インターホン?」
もう一度寝直すしかないと布団をかぶって、意識が半分落ちかかったときだった。
仕方ない。重い身体を起こしてゆるゆると玄関に向かう。
「よ、今日こそ見舞いに来てやったぞー」
ついさっき妄想していたことを思い出して、固まってしまう。
なぜか、見慣れたはずの整った顔が妙にきらきらしている。今まで一度もそんな現象にあったことはない。まさか妄想のせい?
「おい、どうした? あ、まだ熱高いか……それなら悪い」
「あ、い、いや。今はそこまで高くないよ。大丈夫」
彼はほっとしたように笑う。……やっぱり、色っぽい。いや、むしろ可愛い?
「あ、上がってくか? お前がいいならかまわねーよ」
慌てた拍子に、遊びに来たときのようなノリで口走ってしまう。自ら追い込むような真似をしてどうするんだ!
「おー、もともとそのつもりだったし。んじゃ、ちょっと上がらせてもらうわ」
内心混乱する自分をよそに、彼はリビングにずんずんと進んでいく。後を追うと、手にぶら下げていた大きめのビニール袋からヨーグルトやゼリー、ペットボトルを取り出して冷蔵庫に入れてくれていた。
「ほら、おとなしく寝てろって」
こちらの視線を飲み物が欲しいという訴えと勘違いしたのか、食器棚にあるコップとしまったばかりのペットボトルを両手に、こちらに向かってくる。
まるでこの家のもうひとりの主であるような、実に無駄のない動きだった。
「他に欲しいものあるか?」
「あ、いや、大丈夫。つか、いろいろ買ってきてもらって悪いな。ありがとう」
「冷蔵庫の中スッカスカでびっくりしたぜ。昨日よく無事だったなお前」
「運よくプリンとかレトルトの粥とかあったから、それ食ったりしてた」
スポーツドリンクのほんのりとした甘さがありがたい。くだらない妄想事件はともかくとして、風邪の定番ものを差し入れてくれて助かったのは事実だ。
「あ、そこに貼ってるやつもぬるいんじゃねえの? 替えてやるよ」
実に自然な動作で額のシートを剥がされて、拒否するひまもなかった。
面倒見のよさが遺憾なく発揮されている。
……行き過ぎな気がするのは思い過ごしだろうか。いや、そんな感想自体が危険な気も……。
「そうだ、お前が休んでたぶんの講義のプリント持ってきたぞ。コピー代は差し入れぶんと一緒に、あとできっちり請求するからな~?」
どこか意地悪い笑みなのに、わずかに心臓が跳ねる。
あの切れ長の双眸と左にある泣きぼくろが、色気の元凶かもしれない。
さらに細められた状態で覗き込むように見つめられたら、道を踏み外しそうだ。
「お前さぁ……色気あるって、よく言われねえ?」
口にしてから、無意味に唇を思いきり真一文字に結ぶ。自分で自分をコントロールできていない。熱の恐ろしさを改めて実感する。
「んー、そうでもないけど? てかいきなりなんだよ」
自分も突っ込みたい。どう締めればいいのかわからず、とっさに「なんでもない」とありきたりで解決に向かない返しをしてしまう。
「……なるほど。お前、俺のこと色っぽいって思ってたんだ」
面白い遊びを発見した子供のような表情に、寒気とは違うものが背筋を走る。うまく説明できない。
「そういえば俺が世話してやってたときも嬉しそうだったし、もしかしてそういう意味で好きだったり?」
後ずさろうとして、背中を壁に預けていたことを思い出した。
「ま、俺としては狙った通りかな」
「……え、それって」
どういうこと。
訊き終わる前に、横になるよう促される。自分を映す瞳にますます輝きが灯って、ヘビに睨まれたカエルの気分そのものだった。
「のど、まだ乾いてるだろ?」
自分が口をつけたカップを自らのほうに持っていき、軽く傾ける。トレーの上に役目を終えたそれが置かれた瞬間、ようやく彼の意図に気づいた。
「ま、待っ……ん!」
口内に甘く冷たい感触が流れ込んでくる。火照った熱を冷ますように内壁もゆるくなぞられて、抵抗感が湧き上がらないどころか甘んじて受け入れてしまう。
まさか、夢見ていたシチュエーションがこんなかたちで実現するなんて。
「おいしかっただろ?」
満足げに微笑み、わざとらしく舌を這わせた親友の唇はつややかな光を放っていて、まるで蜜に誘われた蝶のように視線を奪われてしまう。
「それ、もっと欲しいって言ってんの?」
再び重ねられたのは、首を上下に振っていたのだろう。
すべてを飲み込んでもなお、唇は囚われたまま熱をさらに上げていく。不快感どころか、高揚感と気持ちよさを覚えるのは、彼がうまいせいか、風邪のせいか。
「……っあ」
離れていくのが名残惜しい。心の中の声は、ばっちり相手に伝わっていた。
「お前さ……人のこと煽るの、やめろって。さすがにこれ以上、手出せないし」
「いいよ。別に」
なんのためらいもなしに、肯定する。
「お前のせいで、下がってた熱がまた上がっちまった。見舞いに来たんなら、ちゃんと責任とれよ」
わがままなヤツ。
楽しそうに告げたその言葉が、合図だった。
身体を覆っていた毛布をまくられる。シャツの裾から滑り込んでくる、少しひんやりとした手のひらはごつごつとした感触をしているのに、甘美な痺れを生み出す。
「あ……っ、ん」
胸元をかすめた瞬間、思わず口元を塞いでしまった。なんだ、今の鼻にかかったような声は。
「ばか、塞ぐなって。そういう声、もっと聞かせろよ」
いやだと拒否しても彼はお構いなしに壁を壊して、頭上にまとめられてしまう。
「いいから、おとなしくしてろって……」
今度は舌でも触れられて、堪えきれずにみっともない喘ぎがこぼれ続ける。
男でも感じる場所だと知らなかったのは自分だけに違いない。でなければ、ためらいもなく胸に吸いつけるわけがない。
「気持ちいいんだろ? ここ、反応してる」
服の上からなぞられたら、抵抗する力はもうなかった。
「あ……はっあ、ぁ……、や……!」
緩急をつけて揉みしだかれ、ゆれる腰と声を止められず、ついには下着ごと下ろされ、直に触れられた――
目を開けると、見慣れた天井が飛び込んできた。
……天井?
耳の近くで鳴っていると錯覚しそうなほど心臓を脈打たせながら、首を軽く左右にひねる。いたはずの男がいない。というより初めから存在していない雰囲気だ。
「もしかして……」
夢?
声も感触もリアルに覚えているのに、まさかの夢オチ?
茫然自失とは今にふさわしい。ショックも計りしれない。そっと毛布をめくり、身体の中心を確かめてさらに後悔した。
どこからが夢だった? 変な妄想をしたところまでは覚えている。なら夢だけのせいにできないじゃないか。気の合う親友という認識だったはずなのに、ときどき色っぽく見えるなんて感想を抱いたばっかりに……!
のろのろと起き上がり、膝を抱える。しばらく穴ぐら生活をしたい気分でいっぱいだった。誰の目も届かない場所で、落ち着いて頭の中を整理するのに最低一ヶ月の時間がほしい。
「とりあえず、俺があいつを好きだってのはない。絶対ないから」
意味がなくても、言い訳をこぼしたかった。自分が好きなのは女の子、昔も今も女の子と恋仲になりたい。えろいことだってしたい。
『それ、もっと欲しいって言ってんの?』
『ばか、塞ぐなって。そういう声、もっと聞かせろよ』
『気持ちいいんだろ? ここ、反応してる』
瞬間、部屋を満たした音に、突き上がった衝動がかき消される。
家と外をつなぐ扉が、とてつもなく恐ろしく見えた。畳む
お題SS:雨上がり
#男女もの
「深夜の真剣文字書き60分一本勝負」さんのお題に挑戦しました。
イメージソングを、サザンの『雨上がりにもう一度キスをして』にしたつもりが、重い話にw
続きを表示します
---------
雨が降るたび、誰よりも愛していたひとのことを思い出しながら街中を歩く。
『その傘、いつも使ってくれてるよね。そんなに気に入ったの?』
『当たり前でしょ? あなたがくれたものだもの。それに、水玉模様一番好きだしね』
『そっか。俺も贈ったかいがあるってもんだ』
薄い水色で彩られた水玉模様の傘は、三年以上経っても壊れる様子はない。私を、懸命に支えてくれているかのようだ。
生まれ育ったこの街が、私は好きだった。自然に囲まれてのんびり歩く場所も、テーブルを挟んでお喋りを楽しむ場所も、おいしいものを堪能できる場所も、なにもかもがここには揃っている。
あのひとも、同じ気持ちでいてくれた。
春には、桜のあふれる公園で花見をやったね。予想以上に人が多すぎて、次の年は早めに場所を確保しに行ったよね。
夏は、カフェにある限定のかき氷を食べに行ったっけ。サイズが大きいことを知っていて二人でひとつにしたのに、結局食べきれなかったんだよね。でもすっごくおいしかったよね。
秋には紅葉に染まった並木道をひたすら歩いたね。その頃、カメラにハマったって言って、私のこともきれいに撮ってくれたね。
冬は、お互い寒いのが苦手だから室内でばかり遊んでたよね。寒いかもしれないけどどうしてもスケートやってみたいってチャレンジしたら、二人して意外と熱中してたの、覚えてる。
……そう、覚えてるよ。私は、あなたとの思い出すべてを、覚えてる。
身体は、自然と公園内で一番見晴らしのいい場所へとたどり着いていた。
街中を一望できる、夜も人気のあるスポットだ。今日は雨のせいか、人影はない。
雨の勢いはだいぶ弱まっていた。
何度も足を運んだ。あのひととも、ひとりのときも。
一番思い出の詰まっている場所だとわかっているから、引き出しを開けて中身をすべてばらまいて、いつまでも包まれていたいと願ってしまう。単なる逃避に過ぎないとわかっていながら、真正面から向き合うだけの強さがない。
あなたからのキスが、もう一度ほしいよ。
好きだって耳元で囁かれながら、少し高めの体温に優しく包まれたいよ。
どうして、逢いに来てくれないの。「君が呼んだら、いつでも駆けつけてくるよ」って言葉は、嘘だったの?
手すりを掴んだまま、固く目を閉じる。脳裏に浮かぶあなたは、目尻を少し下げた笑顔を私に向けてくれている。私を安心させてくれるとき、愛おしそうに名前を呼ぶとき、甘えてくるとき……同い年なのに、年上にも年下にも見える、笑顔だ。
この場所と同じくらい、大好きだった。
――俺はずっと、君のことを想ってるから。
そんな言葉が聞こえた気がして、思わず目を開けた。思わず苦笑が漏れてしまう。
空耳だなんて、私も相当ね……。
弱い私を見かねて、そばに来てくれたなら嬉しいけれど。
「わ、虹かかってる!」
背中からそんな声が聞こえてきて、のろのろと顔をあげる。隣にやってきたカップルは嬉しそうに、スマホのカメラを起動していた。
雨雲の隙間を狙ったかのように、薄い光の帯が差し込んでいた。
七色というより三色くらいにしか見えないけれど、まぎれもない虹が、視界の先にあった。
『雨上がりにね、虹見えることがあるんだって。いつか見てみたいね』
『漫画とかだったら、いつか俺が見せてやるよ! って言うところかな?』
『ふふ、本当にそれができたら尊敬しちゃうなぁ』
今度こそ、あふれる涙を止められなかった。畳む
お題SS:初めてついた嘘
#BL小説
「一次創作お題ったー!」で生成されたお題に挑戦しました。
相手の気持ちをはかるためについたはずの嘘が、利用された?
続きを表示します
-------
「あの子、お前のこと好きなんだってよ」
危険な賭けだった。
最悪、おれだけが悪者となって終わるだけ。
それでも、友達ポジションに甘んじたままの現状から脱却するにはこれしかないと思った。
多分、相当に追い込まれているのだろう。
「……ふーん」
クールが基本な想い人は、やはりクールに相槌を打った。
「嬉しくない? ほら、あの子って高嶺の花とか言われてるほどじゃん?」
普段、誰それが好きという話は全く聞かずとも、ネットにあふれる女性画像達に「この胸は好み」だの「尻の形がたまらない」だのと話題にしている姿を見ているから、人気のある女子から好かれていると知れば少なからず好意的な反応を取るだろうと踏んでいた。
それは同時に、自らの恋に終止符を打ち込まれるようなものだが……もはや、構わない。
――そうか。一ミリの期待さえも砕かせるための嘘だったのかも知れない。
「……そうだな。嬉しいかな」
こちらをじっと見つめていたかと思うと、目元を緩めてそう返してきた。
「そ、う。やっぱり、そうだよな」
――覚悟していたとはいえ、つらい。
いや、覚悟が足りなかったんだ。どれくらい彼への思いを秘めていたか、理解していたようでできていなかった。
「じゃ、じゃあ、もういっそ告白しちゃえば? いやーうらやましいなぁ。でも絶対お似合いのカップルになるだろうな、うん」
頭をかくフリをして俯く。なにを言っているのかおれ自身もよくわからない。口を開いていないとみっともなく泣いてしまいそうなことだけは自覚していた。
身から出た錆。今の状態にふさわしすぎる言葉だ。
「そんなにうらやましいのか」
聞こえてくる声は、どこか愉快そうだった。
「全く、わざわざ下手な嘘なんかつかなくてもいいのに」
よく、意味がわからなかった。
名前を呼ばれて、反射的に顔を上げてしまう。
漫画だらけの見慣れた本棚が、片目に映る。
あれ、どうして片目だけ?
もう片目には……また見慣れた、彼の顔、いや目が、見え……。
「はは、見事に固まってら」
口の片端を少しだけ持ち上げた、友人得意の笑いを見た瞬間――急激に時間が回り始めた。
言葉にならない声が唇からただこぼれる。恐怖に包まれたようにじりじりと後ずさって、勉強机の椅子にすぐ背中を塞がれてしまった。
どうして彼にいきなりキスをされたんだ?
どうしてずっと夢で見るだけだった光景が、前触れもなくやってきたんだ?
「半ギレでもして、嬉しいなんて言うなとか言ってくれるかと思ったのに、あっさり身を引くんだもんなぁ」
全く事態を飲み込めない自分をよそに、彼はやれやれと溜め息をついている。
「俺を試そうとか、お前が一番苦手なことをわざわざやらなくていいよ。だったら素直にぶつかってこいっての」
な? と小首をかしげて、彼はいたずらっぽく笑ってみせる。
バレていた、とでも言うのか。
あんなに必死にひた隠しにしていたはずの気持ちを、この男はとっくに見破っていたと、いうのか。
「バレてない。そう思ってた?」
頬をするりと撫でる感触が、まぎれもない現実なのだと知らしめてくる。
「知ってたよ。俺はずっと、お前の気持ちに気づいてたんだ」
女子と、恋する人間誰もが見惚れる笑顔が近づいてくる。
独り占めしているのは、他の誰でもない……おれ、ただひとり。
そう飲み込んだ瞬間、自然とまぶたが下りていた。畳む
お題SS:君の甘さは気持ち悪い
#男女もの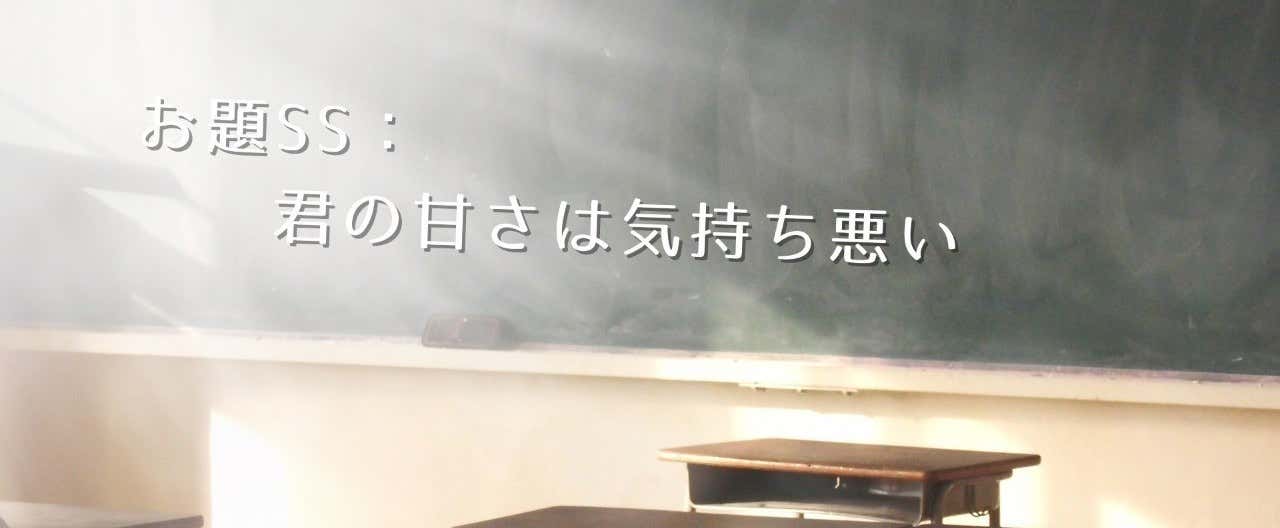
「フリーワンライ企画」さんのお題に挑戦しました。
続きを表示します
--------
私に特別な気持ちでも抱いてる?
からかってるだけ?
誰かと「私を騙せるのは誰か」みたいな賭けでもしてる?
特になにも考えてない?
思いつく限りの可能性を並べてみた。
でも、どれもピンとこない。敢えて選ぶなら二つ目か三つ目だろうか。
迷うのは、彼の真意が全く見えてこないから。
「人の顔、じっと見てどうしたの?」
目の前に想像してた男の顔が現れてびっくりしてしまった。
「そんなのけぞらなくてもいいじゃん? 面白いねぇ」
……そうだ。そういえば担任に「学級委員だからな!」と急にお願いされた書類整理の途中だった。
「……ねえ。今さらだけど、あなたは別にやらなくていいのよ?」
言外に手伝わなくてもいいと告げたつもりだったが、彼はやはり笑うだけ。
調子が狂う。私にどうしろというの。
あなたは一体、私になにを求めてるの。
「あれ、手止まってるよ?」
疲れたと勘違いでもしたのだろうか、胸の高さほどまで積まれた書類の山から、半分ほどを持っていく。
「……なぜ?」
気づくと、問いかけていた。
「あなたは、なぜ私にだけこんなに優しいの?」
そして、後悔した。
こんなタイミングで訊くつもりはなかった。もっと、雑談に近いノリで口にするつもりだった。
こんな、ふたりきりの教室でなんて……雰囲気が、悪すぎる。
「やっと訊いてくれた」
いちだんと柔らかさを増した視線に、心臓が急激に早鐘を打ち出す。
「というか、わざわざ訊いてくるなんて、本当にわかってなかったの?」
これ以上見ていられなくて、慌てて目線を落とす。どこか呆れたような笑い声が耳を打った。
「でも、そうだよね。わかってなかったから、態度が変わらなかったんだもんね」
こういうのは昔から苦手だった。恋自体したことがないから、どう振る舞えば正解なのかわからない。
急に怖くなってきて、反射的に席を立った。そのまま教室を飛び出そうとするが、腕を引っ張られて身体が動かなくなる。
「逃げるなんて卑怯だよ?」
振り向いた先には、わずかな悲しさを含めた笑顔が待っていた。
「せめて、好きか嫌いかなんとも思ってないか、答えだけでもくれないと」
わからない。真意を探ることで精一杯で、自分の気持ちに向き合ったことなんてなかった。
私はどうすればいいの。
調子を狂わされたこの状態から、どう抜け出せばいいの。
焦るだけの私の中に、答えは未だ見えてこなかった。畳む
Powered by てがろぐ Ver 4.2.0.
template by do.
目の前に、夢と妄想
#男女ものnote の企画で書いたものです。
----------
わたし、恋をするとこんなにも腑抜けになっちゃうんだ。
委員会の仕事をようやく片づけてカバンを取りに教室へ戻ると、すっかり人気はなくなっていた。部活のある生徒くらいしか残っていない時間帯だから当たり前だ。
仕事で溜まった疲れを逃がすように、短くため息をついて窓際の自席に向かう。
(……加賀谷くん)
想い人の席を通り過ぎた瞬間、思わず足が止まった。
カリスマ性があり、その気質に負けていない容姿を持つ新島は、このクラスどころか全学年の女子から絶大な人気を誇っている。加賀谷はそんな彼の親友だった。
傍から見ると、加賀谷は完全に新島の影に隠れていると思われるかもしれない。それだけ新島の存在感が強すぎるのだが、自分は決して劣っているようには見えない。実際、加賀谷に惹かれている女子も少なからず存在している。
「あんなにかっこいいのに、誰に対してもスマートって、ずるいよ」
誰もいないのをいいことに、思いきって席に座ってしまった。少しでも加賀谷のぬくもりを感じられた……なんて考えてしまう時点で、頭は相当お花畑状態らしい。
新島は年相応の明るさを持ち、その場をいきなり華やかにしてしまうオーラを持っている。懐も広いから、男女問わず友人も多い。
対して加賀谷はおとなしめで、親友のフォローをしている姿が目立つ。そのせいか誰に対しても物腰が柔らかく、周りをよく見ていて、彼がいるだけでぐっと安心感が高まる。
実に勝手な持論だが、「イケメンは性格が悪い」を見事に覆してくれた二人だった。
それでも加賀谷に惚れたのは……委員会の仕事で手いっぱいになっていたとき、メンバーでないのにたくさん助けてもらったから。
『困ったときはお互いさまだから気にしないで。深見はしっかりしてるから、仕事いっぱい任せられてるんだよな』
『そ、そんなことないよ……昔から要領悪くて、こうやってすぐいっぱいいっぱいになっちゃうんだよ』
『そうだとしても、おれがもし頼む側の立場だったら深見に頼みたくなるよ?』
「すっごい殺し文句……だよね」
しかも爽やかな笑顔つき。一体どれだけの女子が、毒気を抜かれて虜になってしまっただろうか。
「しかもちょいちょい手伝ってくれてるし」
メンバーじゃないのだからと断ってもうまくかわされてしまうし、まるで新しく委員会に加わったんじゃないかと錯覚してしまいそうにもなるのだ。
嬉しくないわけはない。一緒にいられる時間が単純に増えるし、彼との会話も楽しい。
この間は、昔から大好きだった本が同じという事実も判明した。長いシリーズもので、ドラマ化するかもしれないという噂も立っている。それについて否定的だという意見も一致した。
そう、気が合うのだ。
「こんな人、絶対他にいないって……」
机に額を押しつけて深く息を吐く。
最近の頭の中は、加賀谷に告白されるシーンと、もし付き合えたらという楽しい妄想で埋まっている。
デートはカフェでまったり過ごすのもいいし、彼がおすすめだという映画を楽しむのもいい。二人だからこそ楽しめる場所を開拓していくのも新鮮でおもしろいかもしれない。
恋をするのは初めてだった。初めてだからこそ、こんなにも恋に夢中になってしまうとは思いもしなかった。
怖い。それ以上に、彼と恋人同士になりたくて仕方ない。
「あれ、深見?」
幻聴かと思った。けれどおそるおそる出入り口を見やって、頭が真っ白になってしまう。
「びっくりしたー。おれの席に誰か寝てるって思ったら、深見なんだもの」
全身が一気に熱くなる。反対に内心は氷のように冷たい。
気持ち悪いと思われても仕方ない。自分なら、よほど深い仲でない人が自席に座っていたらちょっと引く。さすがの加賀谷もマイナスな感情を向けるに違いない。
「ご、ごめんなさい! えっと、その、特に悪気はなかったっていうか……!」
近づいてくる彼に全力で頭を下げる。言い訳もなにも浮かばなかった。謝るしかできそうになかった。
「そんな、別に怒ったりしてないって。顔あげてよ」
おそるおそる言われた通りにすると、いつもの微笑みがこちらを見下ろしていた。ほっとしたと同時、特別なんとも思われてないのだと知って、がっかりもしてしまう。
――なんてわがままな感情だろう。
「でも、理由は知りたいかな」
微笑みを少しだけ潜ませて――真顔に近いといえばいいのだろうか――、静かに彼は告げてくる。
「きみが意味もなく、こんなことする人じゃないって知ってるから。おれに対して、なにか思ってることがあるんだろ?」
ばくばくと心臓を脈打たせながら、懸命に投げかけられた言葉の意味を考える。
柔らかく、問いかける口調なのに、どこか断言しているように聞こえるのはなぜ?
なにかしらの確信をもって、問いかけているという、こと?
「っだから……特に、理由はない、って」
言えるわけない。自ら傷を負いにいく真似なんてできるわけない。
もっと彼の気持ちが見えたとき、あるいは気持ちが暴走してどうしようもないときでないと、口にはできない。
「おれも君と同じ気持ちかもって言ったら、どうする?」
一歩距離を詰めた加賀谷は、頬に触れながらそう告げた。
夢の中でしかなかった距離に、加賀谷の顔がある。ぬくもりが、これは現実だと訴え続けている。
「かがや、くん……」
「いつも見てたんだよ。君のこと」
ぬくもりが、今度は唇に降りてくる。
夢だけでなく妄想さえも現実になるなど、さすがに予測はできなかった。畳む