Short Short Collections
主にTwitterのワンライ企画やお題で書いたショートショートをまとめています。
男女もの・BLもの・その他いろいろごちゃ混ぜです。
あなたの手のひらが合図
#男女もの
「体調不良版ワンドロ/ワンライ」 さんのお題に挑戦しました。
お題は『息抜き』です。
ある夫婦の日常の一コマ。ほのラブです。
続きを表示します
--------
息抜きするのが下手だね、とよく言われてきた。
実際その通りだと自覚はしている。キリのいいところまで作業したいと気持ちが先走って、気づけば三、四時間経っていた、なんてこともザラだ。
そしてひどく疲労してしまう。反省するのはこの瞬間で、なのに馬鹿の一つ覚えのように同じ行動を繰り返してきた。
急に目の前が闇に包まれて、文字と図で埋まったモニタが消える。
「そろそろ休憩しないと、また体調崩すよ」
視界を覆っていた彼の手を取ると、柔らかな笑顔が次に待っていた。
モニタの右下に目を移して短く息を呑む。昼過ぎだったはずが、もう夕方に差し掛かっている。
「またやっちゃった……いつもごめんなさい。わたしのこと気にさせちゃって」
「気にするなよ。店の売上管理とか広告作りとか、頼りにしっぱなしだし」
表に出るのは彼の役目、裏方は自分の役目。だから気にする必要はないと首を振るのだが、彼としては心苦しいらしい。
「もう少し勉強したら手伝えると思うから! 待っててくれる?」
「ふふ。わかった」
彼に立ち上がるよう促され、そのまま寝室へと手を引かれる。これも日常茶飯事のようなものだった。
「別に寝なくても大丈夫だと思うんだけどな……それに夕飯どうするの?」
「少しくらい遅くなっても大丈夫だって。前に頑張りすぎてめまい起こしたこと、もう忘れたの?」
あのときは寝不足もあったから、と説明しても、彼にとっては忘れがたい事件だったらしい。大事にしてくれるのは本当に嬉しいけれど、少し過剰すぎな気もする。
それでも強く言えないのは――向けられる愛情が心地よくて、幸せだから。
隣で肘をついて、横向きになりながら彼は頭を優しく撫でてくる。
何年経っても変わらない。言葉にせずとも伝わってくる心からの労り。手のひらから癒やしの力が出ているかのように、全身へと染み渡っていく。
――ああ、やっぱりわたし、疲れていたのね。
いつも自己管理の甘い自分を助けてくれてありがとう。
頭を撫でる手を唇まで持っていき、軽く押し当てる。うろたえる彼を可愛く思いながらゆっくりと目蓋を下ろした。畳む
目の前に、夢と妄想
#男女ものnote の企画で書いたものです。
続きを表示します
----------
わたし、恋をするとこんなにも腑抜けになっちゃうんだ。
委員会の仕事をようやく片づけてカバンを取りに教室へ戻ると、すっかり人気はなくなっていた。部活のある生徒くらいしか残っていない時間帯だから当たり前だ。
仕事で溜まった疲れを逃がすように、短くため息をついて窓際の自席に向かう。
(……加賀谷くん)
想い人の席を通り過ぎた瞬間、思わず足が止まった。
カリスマ性があり、その気質に負けていない容姿を持つ新島は、このクラスどころか全学年の女子から絶大な人気を誇っている。加賀谷はそんな彼の親友だった。
傍から見ると、加賀谷は完全に新島の影に隠れていると思われるかもしれない。それだけ新島の存在感が強すぎるのだが、自分は決して劣っているようには見えない。実際、加賀谷に惹かれている女子も少なからず存在している。
「あんなにかっこいいのに、誰に対してもスマートって、ずるいよ」
誰もいないのをいいことに、思いきって席に座ってしまった。少しでも加賀谷のぬくもりを感じられた……なんて考えてしまう時点で、頭は相当お花畑状態らしい。
新島は年相応の明るさを持ち、その場をいきなり華やかにしてしまうオーラを持っている。懐も広いから、男女問わず友人も多い。
対して加賀谷はおとなしめで、親友のフォローをしている姿が目立つ。そのせいか誰に対しても物腰が柔らかく、周りをよく見ていて、彼がいるだけでぐっと安心感が高まる。
実に勝手な持論だが、「イケメンは性格が悪い」を見事に覆してくれた二人だった。
それでも加賀谷に惚れたのは……委員会の仕事で手いっぱいになっていたとき、メンバーでないのにたくさん助けてもらったから。
『困ったときはお互いさまだから気にしないで。深見はしっかりしてるから、仕事いっぱい任せられてるんだよな』
『そ、そんなことないよ……昔から要領悪くて、こうやってすぐいっぱいいっぱいになっちゃうんだよ』
『そうだとしても、おれがもし頼む側の立場だったら深見に頼みたくなるよ?』
「すっごい殺し文句……だよね」
しかも爽やかな笑顔つき。一体どれだけの女子が、毒気を抜かれて虜になってしまっただろうか。
「しかもちょいちょい手伝ってくれてるし」
メンバーじゃないのだからと断ってもうまくかわされてしまうし、まるで新しく委員会に加わったんじゃないかと錯覚してしまいそうにもなるのだ。
嬉しくないわけはない。一緒にいられる時間が単純に増えるし、彼との会話も楽しい。
この間は、昔から大好きだった本が同じという事実も判明した。長いシリーズもので、ドラマ化するかもしれないという噂も立っている。それについて否定的だという意見も一致した。
そう、気が合うのだ。
「こんな人、絶対他にいないって……」
机に額を押しつけて深く息を吐く。
最近の頭の中は、加賀谷に告白されるシーンと、もし付き合えたらという楽しい妄想で埋まっている。
デートはカフェでまったり過ごすのもいいし、彼がおすすめだという映画を楽しむのもいい。二人だからこそ楽しめる場所を開拓していくのも新鮮でおもしろいかもしれない。
恋をするのは初めてだった。初めてだからこそ、こんなにも恋に夢中になってしまうとは思いもしなかった。
怖い。それ以上に、彼と恋人同士になりたくて仕方ない。
「あれ、深見?」
幻聴かと思った。けれどおそるおそる出入り口を見やって、頭が真っ白になってしまう。
「びっくりしたー。おれの席に誰か寝てるって思ったら、深見なんだもの」
全身が一気に熱くなる。反対に内心は氷のように冷たい。
気持ち悪いと思われても仕方ない。自分なら、よほど深い仲でない人が自席に座っていたらちょっと引く。さすがの加賀谷もマイナスな感情を向けるに違いない。
「ご、ごめんなさい! えっと、その、特に悪気はなかったっていうか……!」
近づいてくる彼に全力で頭を下げる。言い訳もなにも浮かばなかった。謝るしかできそうになかった。
「そんな、別に怒ったりしてないって。顔あげてよ」
おそるおそる言われた通りにすると、いつもの微笑みがこちらを見下ろしていた。ほっとしたと同時、特別なんとも思われてないのだと知って、がっかりもしてしまう。
――なんてわがままな感情だろう。
「でも、理由は知りたいかな」
微笑みを少しだけ潜ませて――真顔に近いといえばいいのだろうか――、静かに彼は告げてくる。
「きみが意味もなく、こんなことする人じゃないって知ってるから。おれに対して、なにか思ってることがあるんだろ?」
ばくばくと心臓を脈打たせながら、懸命に投げかけられた言葉の意味を考える。
柔らかく、問いかける口調なのに、どこか断言しているように聞こえるのはなぜ?
なにかしらの確信をもって、問いかけているという、こと?
「っだから……特に、理由はない、って」
言えるわけない。自ら傷を負いにいく真似なんてできるわけない。
もっと彼の気持ちが見えたとき、あるいは気持ちが暴走してどうしようもないときでないと、口にはできない。
「おれも君と同じ気持ちかもって言ったら、どうする?」
一歩距離を詰めた加賀谷は、頬に触れながらそう告げた。
夢の中でしかなかった距離に、加賀谷の顔がある。ぬくもりが、これは現実だと訴え続けている。
「かがや、くん……」
「いつも見てたんだよ。君のこと」
ぬくもりが、今度は唇に降りてくる。
夢だけでなく妄想さえも現実になるなど、さすがに予測はできなかった。畳む
お題SS:雨上がり
#男女もの
「深夜の真剣文字書き60分一本勝負」さんのお題に挑戦しました。
イメージソングを、サザンの『雨上がりにもう一度キスをして』にしたつもりが、重い話にw
続きを表示します
---------
雨が降るたび、誰よりも愛していたひとのことを思い出しながら街中を歩く。
『その傘、いつも使ってくれてるよね。そんなに気に入ったの?』
『当たり前でしょ? あなたがくれたものだもの。それに、水玉模様一番好きだしね』
『そっか。俺も贈ったかいがあるってもんだ』
薄い水色で彩られた水玉模様の傘は、三年以上経っても壊れる様子はない。私を、懸命に支えてくれているかのようだ。
生まれ育ったこの街が、私は好きだった。自然に囲まれてのんびり歩く場所も、テーブルを挟んでお喋りを楽しむ場所も、おいしいものを堪能できる場所も、なにもかもがここには揃っている。
あのひとも、同じ気持ちでいてくれた。
春には、桜のあふれる公園で花見をやったね。予想以上に人が多すぎて、次の年は早めに場所を確保しに行ったよね。
夏は、カフェにある限定のかき氷を食べに行ったっけ。サイズが大きいことを知っていて二人でひとつにしたのに、結局食べきれなかったんだよね。でもすっごくおいしかったよね。
秋には紅葉に染まった並木道をひたすら歩いたね。その頃、カメラにハマったって言って、私のこともきれいに撮ってくれたね。
冬は、お互い寒いのが苦手だから室内でばかり遊んでたよね。寒いかもしれないけどどうしてもスケートやってみたいってチャレンジしたら、二人して意外と熱中してたの、覚えてる。
……そう、覚えてるよ。私は、あなたとの思い出すべてを、覚えてる。
身体は、自然と公園内で一番見晴らしのいい場所へとたどり着いていた。
街中を一望できる、夜も人気のあるスポットだ。今日は雨のせいか、人影はない。
雨の勢いはだいぶ弱まっていた。
何度も足を運んだ。あのひととも、ひとりのときも。
一番思い出の詰まっている場所だとわかっているから、引き出しを開けて中身をすべてばらまいて、いつまでも包まれていたいと願ってしまう。単なる逃避に過ぎないとわかっていながら、真正面から向き合うだけの強さがない。
あなたからのキスが、もう一度ほしいよ。
好きだって耳元で囁かれながら、少し高めの体温に優しく包まれたいよ。
どうして、逢いに来てくれないの。「君が呼んだら、いつでも駆けつけてくるよ」って言葉は、嘘だったの?
手すりを掴んだまま、固く目を閉じる。脳裏に浮かぶあなたは、目尻を少し下げた笑顔を私に向けてくれている。私を安心させてくれるとき、愛おしそうに名前を呼ぶとき、甘えてくるとき……同い年なのに、年上にも年下にも見える、笑顔だ。
この場所と同じくらい、大好きだった。
――俺はずっと、君のことを想ってるから。
そんな言葉が聞こえた気がして、思わず目を開けた。思わず苦笑が漏れてしまう。
空耳だなんて、私も相当ね……。
弱い私を見かねて、そばに来てくれたなら嬉しいけれど。
「わ、虹かかってる!」
背中からそんな声が聞こえてきて、のろのろと顔をあげる。隣にやってきたカップルは嬉しそうに、スマホのカメラを起動していた。
雨雲の隙間を狙ったかのように、薄い光の帯が差し込んでいた。
七色というより三色くらいにしか見えないけれど、まぎれもない虹が、視界の先にあった。
『雨上がりにね、虹見えることがあるんだって。いつか見てみたいね』
『漫画とかだったら、いつか俺が見せてやるよ! って言うところかな?』
『ふふ、本当にそれができたら尊敬しちゃうなぁ』
今度こそ、あふれる涙を止められなかった。畳む
お題SS:君の甘さは気持ち悪い
#男女もの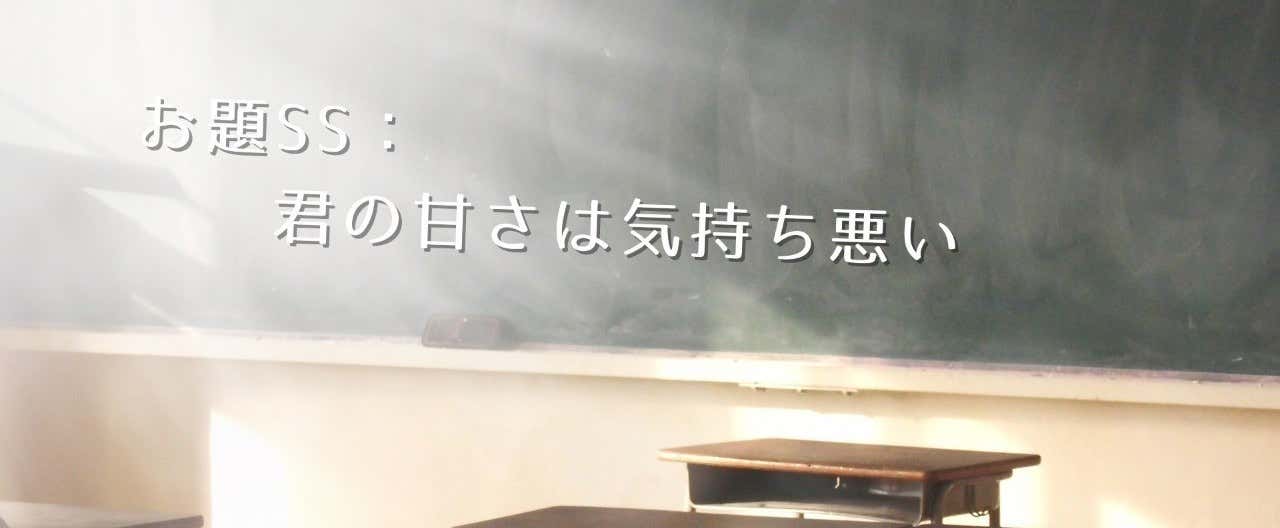
「フリーワンライ企画」さんのお題に挑戦しました。
続きを表示します
--------
私に特別な気持ちでも抱いてる?
からかってるだけ?
誰かと「私を騙せるのは誰か」みたいな賭けでもしてる?
特になにも考えてない?
思いつく限りの可能性を並べてみた。
でも、どれもピンとこない。敢えて選ぶなら二つ目か三つ目だろうか。
迷うのは、彼の真意が全く見えてこないから。
「人の顔、じっと見てどうしたの?」
目の前に想像してた男の顔が現れてびっくりしてしまった。
「そんなのけぞらなくてもいいじゃん? 面白いねぇ」
……そうだ。そういえば担任に「学級委員だからな!」と急にお願いされた書類整理の途中だった。
「……ねえ。今さらだけど、あなたは別にやらなくていいのよ?」
言外に手伝わなくてもいいと告げたつもりだったが、彼はやはり笑うだけ。
調子が狂う。私にどうしろというの。
あなたは一体、私になにを求めてるの。
「あれ、手止まってるよ?」
疲れたと勘違いでもしたのだろうか、胸の高さほどまで積まれた書類の山から、半分ほどを持っていく。
「……なぜ?」
気づくと、問いかけていた。
「あなたは、なぜ私にだけこんなに優しいの?」
そして、後悔した。
こんなタイミングで訊くつもりはなかった。もっと、雑談に近いノリで口にするつもりだった。
こんな、ふたりきりの教室でなんて……雰囲気が、悪すぎる。
「やっと訊いてくれた」
いちだんと柔らかさを増した視線に、心臓が急激に早鐘を打ち出す。
「というか、わざわざ訊いてくるなんて、本当にわかってなかったの?」
これ以上見ていられなくて、慌てて目線を落とす。どこか呆れたような笑い声が耳を打った。
「でも、そうだよね。わかってなかったから、態度が変わらなかったんだもんね」
こういうのは昔から苦手だった。恋自体したことがないから、どう振る舞えば正解なのかわからない。
急に怖くなってきて、反射的に席を立った。そのまま教室を飛び出そうとするが、腕を引っ張られて身体が動かなくなる。
「逃げるなんて卑怯だよ?」
振り向いた先には、わずかな悲しさを含めた笑顔が待っていた。
「せめて、好きか嫌いかなんとも思ってないか、答えだけでもくれないと」
わからない。真意を探ることで精一杯で、自分の気持ちに向き合ったことなんてなかった。
私はどうすればいいの。
調子を狂わされたこの状態から、どう抜け出せばいいの。
焦るだけの私の中に、答えは未だ見えてこなかった。畳む
タグ「男女もの」[31件](4ページ目)
Powered by てがろぐ Ver 4.2.0.
template by do.
すべてが今さら過ぎたけど
#男女もの「深夜の真剣物書き120分一本勝負」 さんのお題に挑戦しました。
使用お題は『①嫌々』です。
高校卒業を控えた幼なじみ同士のお話。ノーマルです。
--------
「そんなこと言わないで、一緒に記念のアルバム作りましょうよ!」
「そんな辞書並みに分厚いアルバム、どんだけ撮るつもりなんだよって言ってんだろ! もう少し薄いのにしろって」
「で、でも、もうすぐ卒業なんですよ? 思い出で埋め尽くしたいじゃないですか! それに、今まで撮ったぶんもここに収めますし」
「収めてもまだだいぶページ残るだろ絶対……」
オレンジに変わりつつある光の差し込む部室で、部長である幼なじみと俺のせめぎ合いが続いていた。かれこれ十分は経過していると思う。
彼女は赤い表紙のアルバムを抱き込むように握りしめて、顔を歪めた。
「……お願いです。お願いですから、アルバム作り、協力してください。もう、こんなわがままは最後にしますから」
「最後って、大げさな」
苦笑しながら言ってみたものの、初めて見る彼女の姿に内心は戸惑っていた。
卒業を目前にしてセンチメンタルにでもなっているんだろうか。中学の卒業式は少し泣いたぐらいで、ここまではっきりとした態度には出していなかった。
「お願い、です」
一歩距離を詰めて、縋りつくように見上げてくる。ここで普段はちっとも有効活用していない、可愛らしい容姿を武器に攻めてくるとは、本当に昔からずるい。
「……わかった、わかったよ。写真撮ればいいんだろ」
盛大に溜め息をこぼして承諾すれば、一瞬で花が咲いたように笑顔になる。泣き笑いと言ったほうが正しいかもしれない。
「ほんと大げさだな。まあ、今までの頼み事に比べたらずいぶんマイルドだけど?」
こいつの「お願い」にはさんざん振り回されてきた。腰までの長い黒髪にヘアバンドという、大和撫子――ただし古め――という四文字熟語が似合う容姿をしているのだが、中身は正反対と言いきってもおかしくない。見た目で惚れて蓋を開けた瞬間去っていった男を今まで何人も見てきている俺だから間違いない。
とにかく面白そうなことがあれば果敢に首を突っ込みたがるのだ。もれなく俺もお供にされる。一番過酷だったのは、富士山でのご来光を写真に収めたいがために登山のお供をお願いされたときだ。プロのガイド付きでも、並みの体力しかなく登山の経験も全くなかった俺には、宿泊つき登山はハードルが高すぎた。彼女も同じ立ち位置のはずが下山するまでずっとはしゃいでいて、いろんな意味で負けた気がした。
「……そうですね。本当に、たくさん振り回しちゃいましたよね」
普段なら「まだまだ付き合ってもらいますよ!」とでも返してきそうなのに、なぜかマジレスされてしまう。
「お、おい?」
「じゃあ、早速明日から少しずつ撮影開始しましょうね! わたし、ざっくりと計画を練ってきます。校内でも校外でも、撮りたいものいろいろあるんです」
はぐらかされた? 追求したくても、彼女はアルバムを棚に戻すと逃げるように部室をあとにしてしまった。
「なんだ? あいつ……」
あのぶんだと、改めて問いかけても答えてくれそうにはない。今時珍しく、携帯電話の類はなにも持っていないから、今すぐ追求できないのももどかしい。
違和感を拭えないまま、とりあえず帰ることにした。
ふと、今さらな事実に気づく。中学校からの付き合いなのに、今まで一度も下校を共にしたことがなかった。
アルバム作りは、予想通り面倒な作業となった。
彼女が持ってきた計画をこなすには、放課後だけでは全く時間が足りず、休日も贅沢に使ったものとなった。
そして……あの日に抱いた違和感が、日に日に大きくもなっていた。
「これで最後ですね!」
構えていたデジタルカメラを下ろすと、彼女は両手を上げて小さい子供のように喜んだ。
「いやー、時間かかったな……マジでギリギリじゃん」
卒業式は三日後だ。写真の選定は彼女がするらしいが、本当に間に合うのだろうか。
「本当にお疲れ様でした。たくさんいい写真が撮れて、本当によかったです」
心からの笑顔を向けてくる彼女に、焦りの色は全く見られない。こうと決めたときの行動の早さは折り紙つきではあると知ってはいるものの、手伝った身としては心配してしまう。
「なあ、俺、本当に手伝わなくていいのか?」
「いいんですよ。わたしが言い出したことですし、わたしがやりたいんです」
言い切られてしまっては、これ以上なにも言えなくなる。
「あ、アルバム、ちゃんと二冊作りますからもらってくださいね? 間に合わなかったら郵送しますし」
「え、いいよそこまで……」
「いいから! せっかくです、受け取ってください。あとで住所、教えてくださいね」
まただ。彼女は縋りつくように俺を見つめてくる。静かな気迫に押されて、頷くしかできなかった。
「ここ、懐かしいですよね」
改めて背後を振り返り、呟く。もやもやした気持ちを持ったまま、また頷いた。
「中学のとき、この商店街にある食べ物全部食べて回りたい! って言ったときの顔、未だに覚えてます」
「そりゃそうだろ……初めての遊びがアレって、インパクトありすぎるわ」
食べられないものあるかもしれないとか、お金はどうするんだとか、そういう当たり前の疑問を豪快にすっ飛ばして店に入りまくった彼女の恐ろしさを、その日だけで一生分味わった。にもかかわらず、未だにこうして付き合いが続いているのも不思議だとつくづく思う。
「なあ、今さらだけどさ……あのとき、お金ちゃんと全部払ってたろ? それって、お前が金持ちだから、とか?」
彼女は自身のことをほとんど語らない。あまり触れてほしくないからかもしれないが、勢いで訊いてみてしまった。
「そう、ですね。そんな大層なものじゃないんですけど、一応」
彼女は苦笑しながら告げて、気まずそうに髪を耳にかけた。
「あの、黙ってたのは変な目で見られたくなかったからです。こう、普通の人として接してほしかったというか」
「別に今さらなんとも思わないって。普段のめちゃくちゃな行動力の謎、解きたかっただけだから」
本当に安堵したように笑う。金持ちなりに、きっといろいろと苦労してきたんだろう。これ以上の追求はやめておいた。
彼女は改めて、地元の店が並ぶ商店街を振り返った。遥か彼方を眺めるように、目を細める。
「……わたし、どうしてもこの場所をラストに持っていきたかったんです」
だから、食べ歩きもしたのか。
「そうだ、せっかくですからツーショット撮ってもらいましょう? あの、すみませーん!」
否定する間もなく、彼女の言う通りの流れになってしまう。多分微妙になっているだろう笑顔で、人生初の女子との二人きり写真がカメラに収められた。
「ふふ、ありがとうございました。いい思い出になりました」
カメラを大事そうに見つめる彼女の瞳は、寂しそうだ。
「あの、さ」
違和感を吐き出す瞬間は、今しかない。
「お前が作ろうとしてるアルバム……なんか、今までの思い出作り、って感じがするんだけど」
この商店街だけじゃない。
高校と以前通っていた中学校の通学路の風景、俺の家の周辺の風景、二人で遊びに行った……もとい、無茶を要求された場所――俺達が共有している思い出の写真が、特に多い。
卒業文集のようなノリのアルバムを作ると思っていたのに、これではまるで、思い出のアルバムだ。
「それ、は……それは、気のせいですよ」
明らかに動揺しておきながら、彼女は下手な嘘をつく。
「大学生になったら、こうして会える時間も減ってしまうでしょう? だから、その前にこうしてまとめておきたくて」
「俺、お前の進路知らないけど」
俺は、単純に家から近い私立の大学に行くと答えた。
彼女は、まだ進路を決めていないと言っていた。それきり、知らない。
「わたし……わたしも、大学行きますよ。でも、ちょっと遠いというか」
なぜだ。どうして下手な嘘を続ける。
どうして、俺の目を見て言わないんだ。いつもまっすぐ俺を見つめてくる、お前なのに。
「あ、もう時間ですね。わたし、帰ります。アルバムの作業もありますし」
細い腕を、掴めなかった。
掴もうと思えば掴める距離なのに、できなかった。
わかりやすい拒絶をされて、情けないことに、足を動かせなかった。
俺はスマホに表示されている地図のもとへ、全力で駆けていた。
頭の中はいろんな感情がごちゃまぜになって、まずい料理を作ってしまったような状態だ。でも、その中で突出しているのは「怒り」かもしれない。
――こんな形で、あなたに本当のことを告げる卑怯さを許してください。
わたしは、高校を卒業するまでしか自由を許されない身でした。
だから、中学のときに出会ったあなたを気に入って、たくさんの無茶を繰り返していました。
したいと思ったことを、できる限りやりたかったのです。あなたと一緒に、楽しみたかった。
付き合わせてしまって、あなたの優しさに甘えてしまって、本当にごめんなさい。
あなたが好きでした。いいえ、今でも好きです。
でも、どうぞわたしのことは気にしないでください。
どうぞ、いつまでもお元気で。
卒業式の次の日に送られてきたアルバムに同封されていた一枚の手紙で、すべてが線につながった。
彼女があんなアルバムを作りたがっていたのも。
卒業式の日、第二ボタンがほしいとせがんで、一度でいいから抱きしめてほしいと懇願してきたのも。
全部……今さらすぎる、種明かしだ。
なんとなく、大学も変わらない関係でいられると思っていた。大人に近づくから少しずつ無茶も減っていって、俺も勇気を出して、無理なお願いは断ろうなんて小さい目標も立てたりしていた。
呆れるほど呑気で、自分に腹が立って仕方ない。
「ちょっと、そこのあんた!」
金持ちなのは本当だった。でも、彼女の謙遜が謙遜にならないほど立派すぎる屋敷で一瞬足がすくんだものの、門の前に立っている初老の男性に声をかけることで気合いを入れた。
「なにか御用でございますか?」
身なりからしてこの屋敷の執事だとわかる。俺は勢いのまま、彼女の名前を告げて会いたいと申し出た。
「なるほど。あなた様が、お嬢様が大変お世話になったお方でございますね」
「……知ってるのか」
「はい。お嬢様より、あなた様が訪れた際は対応するようにと、ご命令いただいております」
きれいなお辞儀をされて、出鼻をくじかれてしまう。
「お嬢様は、現在日本にはおりません。イギリスにおります」
……なにを、言われているかわからなかった。
「……大学は、イギリスってことか?」
「大学卒業後も、イギリスでしばらくお過ごしになられます」
「いつまで、だよ」
「それは、私ではわかりかねます」
それから、いくら粘っても彼女がイギリスにいることしか教えてもらえなかった。
イギリスってなんだ。なんでいきなり外国なんかに行ってるんだ。
お前は、ずっと俺のそばで無茶なお願いをする奴じゃなかったのか。
「そう、か。俺も、あいつのこと……」
また、今さら気付いてしまった。よかったのか、よくなかったのか、中途半端に興奮した頭では判断できなかった。
でも、ひとつだけはっきりとわかっていることがある。
「このまま、終わりになんてできるか」
大体、告白して逃げるなんて卑怯にもほどがある。いつも変に自信があるくせして、こんなときは臆病だなんてお前らしくもない。
「待ってろよ。絶対、あっちで再会してやるからな」
口にして、俺もいつの間にか無茶体質が伝染していたんだなと、苦笑するしかできなかった。畳む