星空と虹の橋の小説を掲載しています。
更新履歴
- こんな日は素直に休みましょう
2025/11/23 08:55:29 探偵事務所所長×部下シリーズ - 思いがけない小さな宝石たち
2025/11/18 14:42:15 探偵事務所所長×部下シリーズ - 【300字SS】拭えないまま
2025/10/04 22:41:49 ショートショート・その他 - 【300字SS】必然で唐突な運命
2025/07/05 22:00:07 ショートショート・その他 - 【300字SS】だから、独りを選ぶ
2025/06/07 22:41:10 ショートショート・その他
カテゴリ「ショートショート・BL」に属する投稿[38件]
急に伸びた手は、誰も躱せない
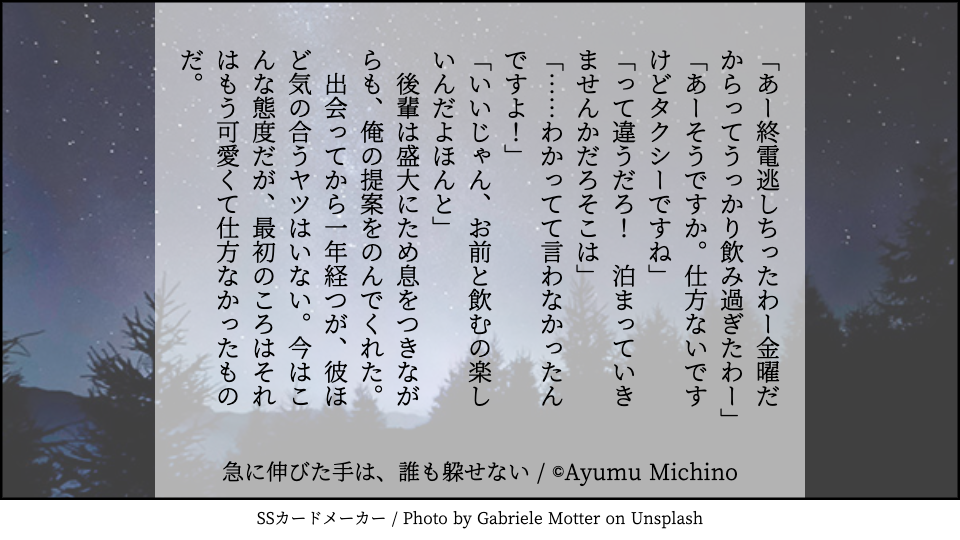
創作BL版深夜の60分一本勝負 のお題に挑戦しました。お題は「終電」「泊まってく?」です。
-------
「あー終電逃しちったわー金曜だからってうっかり飲み過ぎたわー」
「あーそうですか。仕方ないですけどタクシーですね」
「って違うだろ! 泊まっていきませんかだろそこは」
「……わかってて言わなかったんですよ!」
「いいじゃん、お前と飲むの楽しいんだよほんと」
後輩は盛大にため息をつきながらも、俺の提案をのんでくれた。
出会ってから一年経つが、彼ほど気の合うヤツはいない。今はこんな態度だが、最初のころはそれはもう可愛くて仕方なかったものだ。
「どうぞ、散らかってますけど」
「今さらだろー。っていうか言うほど汚くないぞ、俺んちのほうがだらしないわ」
お邪魔しまーす、と一応の断りを入れる。というのも、彼の部屋が二次会会場になるのも珍しくはなかったりする。
本当にダメだと念押しされたら素直に引くぐらいの常識だってちゃんとあるし、彼も遠慮せずに言ってくる。それくらいの仲なのだ。
でも、なんだろう。今日は少し、様子が違うような……。
後輩がテレビをつけると、深夜帯にふさわしい内容のバラエティがやっていた。少しうるさいなぁと思ったら彼も同じ気持ちだったのだろう、すぐに消した。
「ビールしかないですけど、いいですよね?」
頷くと、500ミリリットル缶を一本だけ持って、向かいに腰掛けた。
「あれ、お前は飲まないの?」
「僕は充分飲みましたんで」
やっぱりなんか違う。はっきり断らなかったからと、無理強いさせてしまったか?
いつもなら深い話を楽しんだりするのだが、今日は早めに帰ったほうがよさそうだ。
「……あのさ。俺の顔になんかついてる?」
「別についてないですよ」
「そ、そう? なんかこう、見つめられてるなぁって」
こんなに読めない後輩の姿は初めてだった。なぜか怒られているような気にさえなってくる。いや、俺は俺で押しかけてしまったという負い目もあるが、それを抜きにしても変な気持ち悪さを感じる。
「いえ? ただ、ちゃんと考えてくれてるのかなって。僕があなたに告白したこと」
酔いが一気に醒めるなんて、本当にあるんだ。
缶、持ち上げる寸前でよかった。絶対に落としていた。
「ああ、やっぱり冗談だって思ってたんですね。センパイ」
嫌みを存分に含んだ笑みを向けられる。こいつ、こんな顔もするんだ。
「だって全然態度変わんないんですもん。こっちは勇気出して告白したんですよ?」
……忘れていた。頭の隅に追いやって、彼の態度が変わらなかったからそれに全力で甘えて、いつしか、なかったことにしていた。
「っで、も」
「こっちの身にもなれ、ってやつですか? わかってます、あのときだって申し訳ないと思ってました。でも、無理だったんです。我慢できなかったんです」
眉間に皺を寄せて、声を絞り出す。
わかる、俺だって恋をまったく知らない人間じゃない。でも、でもなんで俺なんだ。確かに彼は好きだ、でもそういう目で見たことはない。あくまで可愛い後輩なんだ。
「だ、だって男だし年上だし! お前だって信じられないって思うだろ絶対!」
「好きになったのがあなただった、それだけです」
泣くんじゃないかと心配になるほど、瞳が歪んでいる。正直、気にかける余裕はない。だってどうしようもない、どうにもできない。
「……だから、家にあげたくなかったんだ」
そうつぶやいた後輩は俯いたまま、いきなりテーブルを乗り越えてきた。
「お、おいビールが」
「そんなの、どうでもいいです」
いつもなら絶対ないのに、鼻を刺激するアルコールのにおいにくらくらする。
「いいですよ、泊まっていっても」
強制的に視線を固定されて、どうにもできない。
「先輩を好きだって言ってる男の家に泊まるってことは、そのつもりだって受け取りますから」
俺は全然そのつもりじゃない!
喉の奥ではそう叫びたがっているのに、声が出ない。
告白してきたとき以上の迫力を間近で浴びて、完全に押されていた。
「先輩はこれくらい荒療治しないと、わかってもらえないみたいですしね」
無理やり重ねてきた唇は、震えていた。
拒めなかったのはきっと、そのせいだ。
#ワンライ
お互いがお互いに
創作BL版深夜の60分一本勝負 のお題に挑戦しました。お題は「魅力」です。
-------
あいつ、絶対気づいてないんだろうなぁ。だから能天気な顔してあっちにもこっちにもふらふらしやがるんだ。
「あれ、眉間にシワ寄せてどったの? おれがいない間になにかあった?」
能天気が隣に腰掛け、眉尻を下げて能天気に問いかけてくる。
「別に。誰に絡まれたとかそういうんじゃねえよ」
「そう? ならよかったけど」
どうも人受けの良くない人相をしているようで、特に中高生時代は陰であれこれ言われたり、酔っ払ったお行儀のよくない輩に絡まれたりした。彼と出会ってから不思議と頻度はだいぶ減ったが、ゼロまではなかなかいかない。俺は彼の能天気さのおかげだと思っている。……口に出したことはないけど。
でも、こいつがあまりに自覚ないから、ちょっとからかってやろうかな。
「お前の無自覚さに呆れてたんだよ」
「え、なになに? 無自覚ってなに?」
そこそこ丸い目をさらに丸くする。こういうとこも魅力……じゃなくて。
「べつに。人気者は大変ですねえってだけ」
二、三度瞬きを繰り返して、ようやく合点がいったらしい。丸すぎる目がわざとらしく細められた。
「寂しかった?」
「そんなんじゃねーよ」
デート中とはいえ、友達に遭遇したらそりゃあ挨拶もすれば軽い会話もするだろう。加えて「まあ人気者なんだろうなあ」というなんとなくの予想も当たりとわかるくらい、みんなまぶしい笑顔だった。
「こいつは俺のだ」と嫉妬するより、みっともない臆病さが頭をもたげている。仮に俺を知り合いだと紹介したら、絶対ふさわしくないと笑われるに違いない。
それくらい、彼は無自覚に、周りを明るく照らしまくっているんだ。
……あの友達のなかに、彼に惹かれている奴がいても、おかしくないんだ。
「確かに寂しそうっていうより、無駄にいらないこと考えてる感じだね」
反論しようとした口は、両方の頬を若干強めに包まれて失敗に終わった。
「はっきり言うよ。それは単なる考えすぎだから全部忘れていいよ」
ため息をついて両手を軽く払う。
「話も聞かないでよく言うぜ」
「聞かなくたって大体わかるよ。おれたち何年の付き合いだと思ってんの」
「せいぜい三年くらいだろ」
「それでも君のことはだいぶ理解してるよ。だからこそ考えすぎだって言ってるの。君はネガティブなところがあるから」
……見抜かれている。嬉しいような、悔しいような。
彼は再び、頬に手を添えてきた。今度は労るような、優しい手つき。
「何回だって言うけど、おれは君が一番好きだよ」
俺を見つめるふたつの瞳は純粋な想いが伝わってくるほどにきれいで、つい手を伸ばして触れてみたくなる。けれど実行はしない。手に入れられるけれど、そのまま眺めていたいから。
「君に一番ふさわしいのはおれだし、おれに一番ふさわしいのは君だけ。これからも変わらない」
「すごい自信だな」
声を詰まらせて、なんとか返せたのがこれだった。ああもう、さっきからカッコ悪いところばかり見せている。
目の前の笑顔がいっそう深まった。こいつ、絶対いろいろ見抜いてやがる。
「君だってそう思ってくれてるって、わかってるからね」
人目につかないところとはいえ、誰が通るともわからない場所でなにをやってるんだ俺たちは。
そう呆れても、彼の与えてくれるぬくもりにもはや抗えなかった。
――くそ、やっぱりこいつの人たらしぶりは危険だ。
こうして、ずっと離れたくないという気持ちにさせられてしまうのだから。
#ワンライ
【300字SS】これは不敬な感情だから
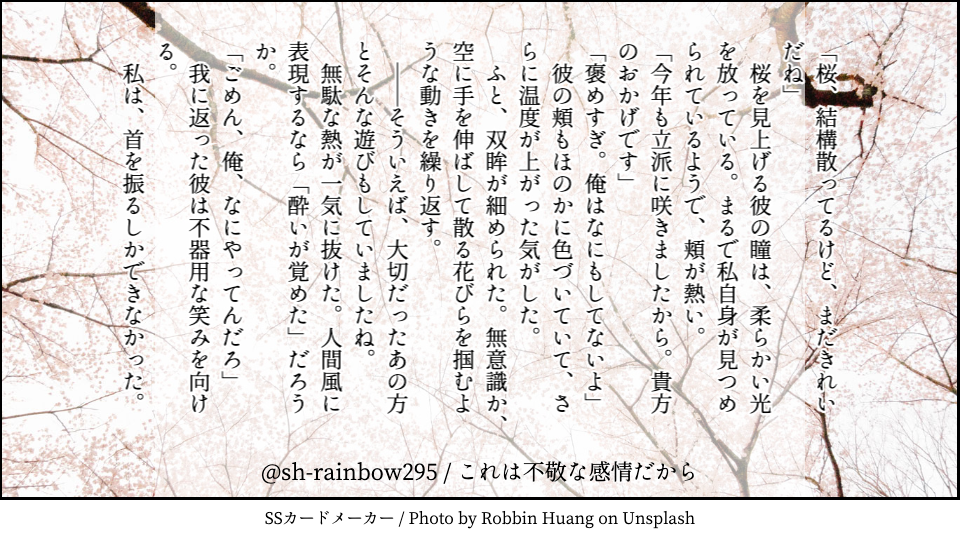
毎月300字小説企画 のお題に挑戦しました。お題は「酔う」です。
桜の木の精と恋人を亡くした社会人のお話。
『現実を忘れられるなら、今は』の話が元ネタです。
-------
「桜、結構散ってるけど、まだきれいだね」
桜を見上げる彼の瞳は、柔らかい光を放っている。まるで私自身が見つめられているようで、頬が熱い。
「今年も立派に咲きましたから。貴方のおかげです」
「褒めすぎ。俺はなにもしてないよ」
彼の頬もほのかに色づいていて、さらに温度が上がった気がした。
ふと、双眸が細められた。無意識か、空に手を伸ばして散る花びらを掴むような動きを繰り返す。
——そういえば、大切だったあの方とそんな遊びもしていましたね。
無駄な熱が一気に抜けた。人間風に表現するなら「酔いが覚めた」だろうか。
「ごめん、俺、なにやってんだろ」
我に返った彼は不器用な笑みを向ける。
私は、首を振るしかできなかった。
#[300字SS]
NotOneSummerLOVE
——欲に負けた瞬間、ひと夏の過ちになると思った。でも、手のひらの上だったんだ。
高校生、同級生同士です。
-------
少し色褪せた木目の天井を見つめていた。
見つめておく必要があった。
隣から意識を逸らしておく必要があった。
最初はただの同級生だった。
席替えをした時、前の席に彼がやってきたのをきっかけに、友達同士に変化した。
いつしか親友同士へとなり、……
驚くほど馬が合った。考え方は正反対、好きなものは被らない、けれど他の誰よりも、隣で呼吸をするのが楽だった。
『お前、今こういうこと考えてたろ』
それが彼の口癖となるのに時間はかからなかった。その予言はほとんど当たっていたからだ。
『お前はわかりやすいんだよ。まあ、俺が理解しすぎてるだけかもしれないけど』
ただのからかいとも取れる言葉が、嬉しかった。切れ長の目を細めて、口角を少し上げたさまが、格好いいとさえ思えた。
……逸らす必要があるくらい彼を好きになっていたのだ。
冷房は十分に効いている。
背中にじっとりと感じる熱は、明らかに隣のせいだった。
どうしてこうなったのか思い返してみる。夏休みの宿題を見てもらいたくて――本当は一緒にいたくて――彼の家に押しかけた。一時間もすると集中力は切れて、意外に長い睫毛とか、自分で整えているのかちょうどいい太さの眉をちらちら盗み見るようになったら、呆れたように気分転換のテレビゲームを提案された。それに敢えて熱中していたら思った以上に疲弊してしまい、互いに大の字に寝転んで、気づけば彼だけが寝ていた。そういえば寝付きのよすぎるタイプだと言っていた。
エアコンの風では打ち消せない呼吸音が左耳をくすぐる。――寝息だけを意識的に拾おうとしているのは明白だった。
身体の最奥で激しく打ち鳴らしているような鼓動が続いている。息を吐き出す瞬間も、無駄に熱さを含んだものだった。
視線はいつしか、テレビの左隣にある本棚へと移っていた。知っている漫画もあれば小難しそうな参考書と思われる文庫、分厚い図鑑など、多種多様な本が四段すべてにきっちりと収められている。
ここから視線を下ろしたら、無防備な彼へとたどり着いてしまう。今の状態で寝顔を捕らえてしまったら、どうなるかわからない。
「……、ん」
色を含んだように聞こえたのは特別な目で見ているせいだ。
だからこそ、ここでとめておかなければならない。
「つか、さ……」
名前を、呼ばれた。
今まで一度も、名前で呼ぶなんて、なかったのに。
まさか、夢を見ているのか?
夢の中に、「いる」のか?
「ゆき、と」
魔法にでもかかったみたいだ。鼓動のせいで苦しささえ感じているのに、今にでも飛び立ててしまえそうな気分になっている。
「ゆきと、ゆきと……」
何でも見通してしまう聡明な輝きに蓋をして、普段より柔らかな表情で寝息をこぼし続ける彼は、理性でつくられた壁を簡単に破壊していく。
エアコンは、もう役に立たない。
顔の両端に手をついた。初めて見下ろす、親友と油断している彼の無防備さにむしろ喉の奥を震わせた。
少しずつ肘を折っていき、腕半分を完全に床につける。
呼吸が、唇に触れる。皮膚同士はまだ離れているのに熱が伝わってくるような錯覚が襲う。彼の顔だけが、視界を埋め尽くして離れない。
夢の中でしか成し得なかった距離に目眩がしそうだった。
好きだ。友達として以上に、好きでたまらないんだ。お前しか考えられなくて、どうしようもないんだ。軽蔑しないでくれ。嫌わないでくれ。
初めてのキスは彼の飲んでいた麦茶の味が混じっていた。見た目には薄い唇なのに、心地よさを感じるほどに柔らかい。
口の中に吐息がかすかに入ってくる、それだけで何も考えられなくなる。いつまでも重ねていたいと、欲が頭を出しそうになる。
「っ、んぅ⁉」
あるはずのない衝撃が、後頭部に走った。反射的に身体を引こうとしても動けない。呼吸ごと奪おうとするような、確信的なキスまでされている。
「やっぱり、襲ってきた」
ほんの少しだけ距離を取って、目蓋の奥にあったダークブラウンがまっすぐに射抜く。
再び、唇を塞がれた。
背中をそわりとした感触が這って思わずくぐもった声を漏らすと、湿った塊が差し込まれる。
「ふぁ、は……っ、ん……!」
「ん……っは、ぁ……」
これは彼の舌なのか。苦しい。どう呼吸すればいいのかわからない。気持ちいい。
たくさんの情報が頭の中を圧迫して処理しきれない。ただ口内で余すところなくなぞっていく塊に、ぴくりぴくりと反応するばかりだ。
ちゅ、と唇を軽く吸われた音で、うつつな状態から戻ってくる。彼の細い指が下唇の端から端までをゆっくりなぞって、吐息に甘い音が重なる。
なんで。問いかけようと懸命に開いた口からは、引きつった悲鳴が漏れる。
「せっかくだから、こっちも触ってやるよ」
うそ、だ。
でも彼の手は確かに、ジーンズを押し上げているモノを捕らえている。形を確認するように、あるいは愛撫するように、ゆるく上下に動いている。
鼻で軽く笑う声が聞こえた。ベルトが外され、チャックまで下ろす動作を黙って受け入れてしまう。
両膝が崩れ落ちるのを助長するように、右耳に熱い吐息を注ぎ込みながら直に触れてくる。腰が大げさに跳ねるのも仕方ない。他人に、しかも彼に触れられる日が来るなんて、想像しろという方が無理だ。
自慰をするように、指全体で根元から先までを丁寧に何度もなぞる。たまに先端からにじみ出ている液体を拭うような動きを取り、さらになめらかな愛撫を重ねていく。
「わかるか? ここから、どんどんあふれてるの……」
「っ言う、なぁ……!」
「無理だね……お前が、エロいのが悪いんだ」
最初からエアコンがついていないような暑さにまみれている。汗がにじむ。触れ合ったところすべてが、じっとりとあつい。
「……ねえ。俺のも一緒に、触ってほしい」
触って?
もう一度ねだる声が、波紋のように頭に響く。
向かい合わせの体勢になると、明らかな欲に染まった表情と対面してぼうっと見つめてしまう。
視線で続きを促され、タックボタンを外し、下着越しに一度撫でる。十分な硬度が手のひらに返ってきて、思わず喉を鳴らしてしまう。
「っあ、は……ぁ」
甘く、待ち望んだとわかる溜め息が自らのものと混ざり合って、身体の奥がひどく反応している。
触れられている中心に、集まっていく。
「お前の……っまた、大きくなった、ぞ」
欲情にまみれながらも鋭い光を秘めた双眸と、唇が、ゆるやかな弧を描く。
とめられない。五感すべてが、彼を求めてやまない。
彼の一番の熱を、直接感じたい。下着を下ろして、そろりと手を添える。小さな震えを返してきた彼にいとおしさが増して、あふれる液を塗りつけるように全体を愛撫していく。少しずつ大きくなる濡れた音にさえ、煽られる。
クーラーの風は聞こえない。冷たさも感じない。でも、それでいい。もっとこの熱に浸っていたい。ぼやけた視線を、浮かれた吐息を、交わし合っていたい。
けれど、腰が軽く痙攣するほどに限界が近いのもまた、同様で。
「一緒に、いきたいんだろ?」
ふいに耳元へと落とされた囁きに、素直に首を上下させた。
互いに、撫でる動きを加速させる。鼓動がさらに速さを増す。無意識に伏せていた瞳を持ち上げて彼を捕らえると、唇を重ねた。
身体全体の熱が倍に膨れ上がって……すとんと落ちる。
手の中の感触を確かめるように、ゆっくりと握りしめた。
「全部わかってたよ。お前が寂しくなって、俺のところに押しかけてくることも」
さっきよりも温度の下げられた風が、身体全体を優しく撫ぜていく。
「お前が、ずっと俺のことを好きだったってことも」
繋がったままの手に、力が加わる。
「いつまでもうじうじしてるから、仕掛けてやったんだ。予想通り食いついてくれて、俺としては大満足だね」
隣を見やると、推理が的中した探偵を彷彿とさせる笑みが待ち構えていた。
彼に一番似合う、一番見惚れてしまう表情だった。
#R18
油断禁物
思いついたシーンをつらつら書いてみました。
イメージ的にはサラリーマン同僚同士。のらりくらり型男子とツンツン気味男子。受け攻めはあまり考えずに書きました。
-------
まったく、まいったなぁ。
大体「なんでもないんですよー」「こっちは大丈夫です、それよりあなたですよ! なんか疲れてません?」的なことを言っておけばかわせるのになぁ。
「下手な誤魔化しなんてしないほうがいいよ」
「そっちのほうがしんどそうな顔してるくせに、よくそんなこと言えるね。呆れるよ」
ストレートすぎるくらいストレートに、実年齢より若く可愛い容姿の彼は言ってくる。
このすっぱり感はうちの弟を思い起こさせるが、むしろ鋭利さが増している。
綺麗なバラにはトゲがある的な? 綺麗より可愛いだけど。
変に詮索されるのは苦手なんだよね。自分は自分、他人は他人。たとえば俺が親身に話を聞いたところで、本当の意味で他人を理解できるわけじゃない。どうしたって主観が混じってしまうから、失礼だと思うんだ。
まあ、話すだけでも楽になるっていうのもあるけど、自分にはあんまり当てはまらないかな……。今までも自分で処理できてたし。
今回はちょっと、珍しく長引いてるってだけ。
「あんたは多分強い人間なんだろうけど、いつまでもそれを保ってられるわけじゃないでしょ」
「変な意地張ってないで、いい加減さっさと折れたら? 限界迎える前にさ」
それより、なんで君はこんなに構ってくるわけ? こっちの状態見抜けるわけ?
確かに普段からやり取りは多いほうだけど、大体ツンツンした態度だから、嫌われてるとばかり思ってた。俺はせいぜい「まあ面白いやつだな」ぐらいの意識だった。
彼のことがよくわからなくなってきたよ。
「そんなに必死になっちゃって、よっぽど心配なの? もしかして俺のこと好き?」
ドラマとかでよくある冗談を言えば、怒って解放してくれると思ったんだよね。
ほんと、もういい加減にしてほしかったし。
「……そうだとしたら、どうなの?」
まっすぐに俺を見つめて、ツンツンした物言いも影をひそめて。
予想外の反応に、もっとわからなくなった。まさかこっちが動揺するなんて思わなくて、うまい言葉が出てこない。
彼がさりげなく距離を詰めてきた。目線がほぼ同じ位置だ、なんて場違いな感想を抱いてしまう。
「ぼくがあんたを好きだって言ったら、あんたは素直になってくれるわけ?」
初めて間近で見た彼の瞳は、腹が立つほど綺麗だった。
真面目な言い方をしてるってことは、まさか、本当に? いやでも、全然そんな素振りなかった。わからない。
「それは、どうだろうね」
精一杯の返答をすると、まったく可愛くない不敵な笑みを彼は浮かべた。
夢から少しずつ、現へ
スマホアプリ「書く習慣」のお題:桜散る で書きました。
以前書いた『現実を忘れられるなら、今は』の続きみたいなものです。
-------
覚悟を決めていつもの桜の木を訪れる。
遠目からでも薄桃色の花たちはすっかり跡形もなくなり、代わりに葉が若々しい緑色をまとっているのがわかる。
だが、恐れていた光景はなかった。
「こんにちは。私の言った通り、消えなかったでしょう?」
「あれ、君……いつもの、君?」
「はい。ただ、歳を少し遡っておりますが」
つまり若返ったということらしい。
最愛の恋人を、春を迎えたと同時に失った。
胸に深く暗い穴をつくったまま、俺はいつも恋人と訪れていた一本の桜の木に、縋るように毎日足を運んだ。
人目を避けるようにひっそりと、けれど確かな存在感で生えているこの木を、俺たちは毎年見守っていた。
その想いがきっかけだと、「彼」は言った。
桜の木の精だと名乗り、突然目の前に現れた「彼」。
『このようにお会いするつもりはありませんでした。ですが、心配で。あなたまで、そのお命を失ってしまいそうで、黙って見ていられなくなりました』
夢としか思えなかったが、このときはそれでもかまわないと、彼の存在をとりあえず受け入れた。
そうでもしないと――恋人がいないという現実に、耐えられなかったから。
今は、違う。
彼の包み込むような優しさと雰囲気に、空いたままの穴が少しずつ小さくなっていくのを、確かに感じていた。
だから、怖かった。
桜が散ってしまったら、彼の姿は消えてしまうのではないかと。
二度と、会えなくなってしまうのではないかと。
「先日も申しました通り、私たちは新緑の時季を迎えるとこのように若い姿となります」
「じゃあ、あの薄ピンクで長い髪の状態は二週間くらいしか続かないんだ?」
彼はひとつ頷く。耳のあたりまで短くなった、絹を思わせるような白髪がさらりと頬を滑る。
「そうか、って納得するしかできないけど」
俺と同じ人間ではないから、疑う余地も当然ない。面白いなと感じるほどには余裕はできた。
「姿は見えなくとも、毎年あなた方にお会いしていましたから消えることはありませんよ」
少し笑って彼は告げる。そうだとしてもやっぱり、この目で確認するまでは心配で仕方なかったのだ。
「……でも、完全に枯れたら、会えなくなるよね?」
木に触れながら、気になっていた疑問を口にする。
この桜の木は彼そのもの。
今はまだ、大丈夫だと信じられる。太陽の光を存分に浴びている葉はどれも生き生きとして、生命力に満ちているのが素人目でもわかる。
それでも、いつまで無事かはわからない。
――突然この世を去った、恋人のように。
「ご心配なく。あなたがこうして足を運んでくださる限り、私は生き続けておりますとも」
隣に立った彼は、優しく頭を撫でてくれた。まるで子どもにするような手つきなのに、反抗する気になれない。
「私に会えなくなると、そんなに寂しいですか?」
「そ、それは……まあ」
「そうですか。……ありがとうございます。私もあなたに会えなくなるのは、たまらなく苦しく、悲痛で、耐えられないでしょう」
ほとんど変わらない位置にある茶と緑のオッドアイが、長い睫毛の裏に隠れた。
どくりと、覚えのある高鳴りが身体を震わせる。
いや、これは彼があまりにも美しすぎるゆえだ。人ならざる者の優美さにまだ慣れていないせいだ。
「俺も、大丈夫だよ。簡単に死んだりしたら、あの世であいつに怒られそうだし。今はそう思うよ」
視線を持ち上げた彼は、心から嬉しそうに微笑んだ。
喉の奥が、変に苦しい。
ふと、足元に影ができた。疑問に思うと同時に、全身を優しい感触で包まれる。
「本当に大丈夫ですか? お辛そうですが」
どうやら彼に抱きしめられているらしい。誰かに見られたらという焦燥感は確かにあるのに、ほのかに伝わってくる熱が不思議と上書きしてしまう。
「ご、ごめん気を遣わせたね。本当に大丈夫だから」
落ち着いたら落ち着いたで、心音が思い出したように早鐘を刻み始める。彼に知られたくなくて、なるべくゆっくりと身体を離した。
「なら、よろしいのですが……。遠慮なさらず、私に寄りかかってくださいね。あなたの苦しみは、私の苦しみですから」
向けられた微笑みがどこか眩しいのは、若返った容姿のせいだろうか。
頬を撫でる風がやけに涼しく感じるのは、全身がほんのり熱いからだろうか。
「……あんまり献身的すぎるのも、困りものだな」
思った以上に小さい声だったようで、彼の耳には届いていなかった。
よかった。きっと、彼をただ困惑させてしまうだけだから。
#お題もの
恋路の始まりと信じていいの?
創作BL版深夜の60分一本勝負 のお題に挑戦しました。
使用お題は「夜景」です。
-------
夜景がやたら綺麗に見えるのはたぶん、隣のこいつに恋しちゃっているからだと思う。浮かれパワーというやつだ。
仕事上ではよくつるむことが多いものの、プライベートは全く干渉せずだったはずが、どんな気まぐれか、彼から夕食の誘いを受けた。てっきりどこかの居酒屋だと思っていたのだが……
(ビアガーデンとはいえ、こんな夜景が堪能できるところとはね)
席がフェンスに近い場所だからなおさらよく見える。周りにカップルも多いし、たぶんそういう層向けなのだろう。
「どうしたどうした、飲み悪くね?」
しかし目の前のこいつは全然気にしていないらしい。まあ、いつでも「らしさ」を崩さない性格ゆえだ。
「ガラにもなく夜景きれいなーって思ってただけ」
「あ、だろ? ここ一人でも来るんだけど、景色いいから余計開放感あってたまらんのよ」
「ひ、一人で? カップル多いのに強いな」
「今日は金曜だから仕方ないさ。それ以外ならそんなでもないぞ」
「ていうかなんで俺を誘ったんだよ? 今まで俺らそういうのなかったじゃん」
さりげなくうまく質問できただろうか。片思い中の身としては正直、夜景よりもそっちが気になってビールもつまみの味も曖昧のままだった。
「ん? ああ、前から気になってた、ってのはあったかな。でもずっとバタバタしててなかなかチャンス掴めなかったっていうか」
ジョッキを置いて、彼は細めの瞳をますます細めて笑う。相変わらず爽やかな雰囲気を放ってやがる。
「オレら結構いいコンビだと思うのよ。オレって抜けてるとこあるけど、お前がいつもいい感じにフォローしてくれるから感謝してるんだぜ。そのお礼も兼ねてるかな」
その「抜けてる」ところに最初はわりとイライラしていた。何度言っても直らないし、そのうちこっちも助けてもらうことが増えたし慣れてもきたから、ある意味懐柔された気がしないでもないが。
「お、お前はプライベートは俺には見せるつもりないって思ってたよ。あくまで仕事上の付き合いっての? ほら、他のやつともあんまり飲みに行ったりしないじゃん?」
「ほー、やっぱよく見てんな」
そりゃあ好きなやつだから、観察力も上がるってもんだ。
「基本プライベートは一人で行動するのが好きなんだけど、お前は仕事のときも気が楽だし、お前ならいいかなって思ったんだよね」
薄暗い場所でよかった。頬が無駄に熱いから、絶対はっきりと赤くなってる。というかナチュラルに口説いてくるなんて、心の準備が全然できていない。前もってそういう雰囲気なり出しておいてくれ。
「……俺は、」
さりげなくを装ってビールを一口飲む。
「俺も、お前といると楽しいよ」
落ち着かない、心臓がうるさい、こんなこと言えるわけないのに、うっかりこぼれそうになった。酒と片思い相手の不意打ちの力は予想以上に強い。
「そう? よかった。なんて、実は結構自信はあったんだね。オレお前に好かれてるよなって」
特別な意味ではないとわかっているのに、俺は単純だ。
「どこまでもポジティブで羨ましいね」
「もー、素直に喜んでくれよ」
してるよ。表に出したら絶対ドン引きするくらい、心の中ではめちゃめちゃ顔緩んでるよ。
「ん、なんか言った?」
溜め息混じりに彼がなにかを言ったように聞こえたが、ちょうど背後で「かんぱーい!」と楽しそうな声と被ってしまった。
「気のせいだろ。よし、とにかく飲んで食おう!」
「俺あんまり酒強くないんだけど……」
とりあえず今は、この幸運に身を任せていよう。この男の笑顔をたっぷり堪能してやるんだ。
#ワンライ
たまらない瞬間
創作BL版深夜の60分一本勝負 のお題に挑戦しました。
使用お題は「汗」です。
「そういう」行為をしていますが、直接的な描写はありません。
-------
全身のあらゆる箇所から湧き出る熱と奥から絶え間なく生まれる快楽におぼれながら、ふと、頬に当たる感触にうっすらと理性が戻る。
わずかに視線を上げれば、堪えるように眉根を寄せた彼の顔から、汗がたくさん浮かんでいる。そのうちのいくつかが、自分に垂れたのだ。
「っ、なに……?」
顎から今まさに落下しそうになっていたひとしずくを人差し指で拭うと、訝しげな視線を投げられた。
「……いいや。相変わらずえろいなぁって」
拭った人差し指をちろりと舌で舐める。
「相変わらずって、初めて聞いたよ? 俺」
「いつも思ってたよ? 言わなかっただけ」
わずかに視線を外して言葉を詰まらせている。照れているときの仕草だ。
普段どちらかというとクールな印象の彼からは想像できないくらい、最中のときはとても色っぽくて、むき出しになる素直な欲にあっけなく飲み込まれる。
眉間に深い皺を刻んだ表情は雄っぽさが全面に出ていてたまらないが、特に、熱をぶつけられているときに顔を打ってくる彼の汗に一番興奮する。
それだけ、自分自身に夢中になってくれているという証のようで。
それだけ、自分も彼を「溺れされて」いる証のようで。
好きになったのは自分からだったから、なおさら。
「ちょ、ちょっとくすぐったいから」
「たまには振り回される側に回ってみたら? なんて」
舌を這わせた顎を押さえて彼がうろたえている。今日は少しだけ意地悪したい気分らしい。
「もう、いい加減にしな、って」
言葉が終わると同時に深く突かれて、思考が一気に塗り替えられる。
「もう一人で楽しむのはなし。こっちに集中して」
ささやきが終わると同時に唇にも降りてきた熱を、嬉々として受け入れた。
#ワンライ
雨降って幸運舞い込む
創作BL版深夜の60分一本勝負 のお題に挑戦しました。
使用お題は「桜流しの雨」「新生活」です。
BL要素はほとんどないです、すみません。。
-------
頭に濡れた感触を覚えて空を見上げると、いつの間にか青空は鉛色へと変わっていた。
時間がたっぷりあるのをいいことに飲みまくっていたら、また不幸に見舞われた。
「自覚なかっただけでそういう星の下に生まれたんだな、俺」
急に勤めていた会社をクビになったのもそのせいだし、その足で酔いたくて酒を飲みに行ったのに酔えなかったのも酒が強いという不幸体質のせい。
不幸のせいにしてしまえば、くっきり刻まれた傷の痛みも少しは紛れる気がした。
どんどん雨脚が強くなってきた。思い出したが、朝の天気予報で「昼過ぎから強い雨が降り始めて、風も吹き始めるでしょう」なんて言っていた。遅刻しそうだったから折りたたみ傘なんてまったく頭になかった。とことんまでついていない。
わざわざ傘を買うなんて馬鹿らしいし、どうせなら濡れて帰ってやる。
とはいえ、まっすぐ帰る気にもなれなくて、駅までの道を遠回りで進むことにする。どうせこの街にはもう来ないから、最後にどういうものがあるかぐらいは確認してみてもいいだろう。
「……こんな街中に、公園なんてあったんだ」
駅から少し離れた距離にあるからか、普通に散歩も楽しめそうな、そこそこの規模の公園だ。
この街の雰囲気は繁華街寄りだと思っているが、ゆえに憩いの場なるものがあるイメージがなかった。
「そうか、桜、満開だったっけ」
ざっと確認できただけで十本近くはあるだろうか、散策路を挟むように立っている。吸い込まれるように近づくと、地面に薄桃色の絨毯ができつつあることに気づいた。ついこの間満開を迎えたとネットニュースでも言っていた気がするが、もうこんなに散ってしまっている。
「これから雨風強まるみたいだし……お前たちも、不幸だな」
なぜか涙がこみ上げそうになる。人外でも仲間が見つかったことに孤独感を拭えたからなのか、よく、わからない。
「あの、大丈夫ですか?」
急に話しかけられて、思わず背筋が伸びた。
振り返った先には、作業着とわかる格好をした若い男性が怪訝そうにこちらを見つめている。
「雨強くなってきてますし、雨宿りするならすぐそこに屋根付きのベンチありますよ」
「……君、ここで働いてる人?」
「え、はい」
公園で働いている人というと、個人的に年齢層が高いイメージだった。アルバイトかもしれなくても、珍しい。
「ああ、気を悪くしたらごめん。公園で働く若者ってイメージがなかったからさ」
「あなたも若者なんじゃないですか?」
「若く見える? 一応三十近いんだけどね」
明らかに彼の目が見開かれた。昔から年相応に見られないことは慣れている。
「あの、なにかあったんですか?」
「え?」
「すみません、なんかすごく悲しそうに見えたんで」
そんなに顔に出ていたのか。急に恥ずかしくなってきたが、うまく誤魔化すすべも見つからない。
「っと、ほんとに雨強くなってきましたね。変なこと言ってすみません、早く雨宿りを」
「会社、急にクビになっちゃったんだよね」
笑ったつもりだったが、情けなく息が漏れただけだった。
「覚えがないことで犯人扱いされてね。反論したんだけど無駄で、事が大きいからもう会社に来るなって言われちゃって」
もう怒りも混乱もしない。ただ無気力だった。この先のことも考えられないし、たぶん、しばらく休みたいと全身が主張しているのかもしれない。
黙って聞いていた彼が、無言で腕を引っ張った。連れて行かれるまま従うと、屋根付きのベンチに辿り着く。
「いきなりすみません。このままじゃお互い風邪引くんで」
「いいよ、ありがとう。ごめんね、いきなり愚痴っちゃって」
「いえ、今でもそういうとんでもない会社ってあるんですね。びっくりしました」
彼は会ったばかりの他人に、本気で同情しているようだった。
「でも、無責任な言い方かもですけど、そういう会社ならどんな形でも辞められてよかったんじゃないですか」
正直、本気で驚いた。胸の中心を一陣の風が通り抜けたような、不思議な爽快感が残っている。
「そんなクソみたいな会社のことをずっと引きずってたらもったいないですよ。さっさと忘れて、いいところ見つけましょう」
一生懸命、彼が励ましてくれているのがわかる。その姿がとても可愛らしくて、嬉しくて……気づけば、口端が持ち上がっていた。
「え、な、なんですか?」
「あ、ご、ごめん。その……すごく、ありがとうって思って」
少し低い位置にある彼の頭を、子どもにするように撫でていた。バツが悪そうに視線を逸らした彼の頬がはっきりと赤く染まっている。
「そうだよね。いつまでも恨みつらみを向けてたって仕方ないよね。鬱にでもなりそうだ」
「ですよ。でも、ちょっとは休んだ方がいいと思います」
「確かに。ってことで、またこの公園に遊びに来てもいい?」
再び向けられた瞳が、丸い。
「そりゃ、もちろん構いませんけど」
「正確には、君に会いに来てもいい?」
「お、おれ?」
「君と話してると落ち着くんだよね。励みになるんだ」
今度は、頬が桜のようにほのかに染まる。
「仕事の邪魔にならないなら、まあ」
お礼を言ってまた頭を撫でると、今度は軽く怒られてしまった。なお、迫力は全然なかった。
最後の最後で、思わぬ幸運が舞い込んだ。
我ながら現金だと呆れながらも、彼との出会いは運命のように感じていた。
#ワンライ
現実を忘れられるなら、今は
創作BL版深夜の60分一本勝負 のお題に挑戦しました。
使用お題は「夜桜」です。
続きを書きました→『夢から少しずつ、現へ』
-------
夜風が頬を優しくくすぐり、淡いピンクの花びらを少しずつ散らす。
また、「ここ」に来てしまった。
かすかに聞こえてくる、浮かれた声が耳障りで仕方ない。こっちの気も知らずに、なんて無駄な八つ当たりを繰り広げてしまう。
意味なんてない。何度「ここ」に来ても、失ったものはもどらない。時は巻き戻らない。
残された側がただ、現実を受け止めきれていないだけで。
「どうも、こんばんは」
桜の花びらが、ひときわ多く舞い散る。
その散った先、木の幹に着物姿の男が立っていた。
「こん、ばんは」
いつの間に? 少なくとも来たときは誰もいなかった。
「今宵も来てくださいましたね。ただ、とても花見を楽しむようなお顔ではありませんが」
薄桃色の長い髪を揺らして近づいてきたその男は、慈しむような表情をしていた。改めて見ると、とても人間とは思えない容貌をしている。
「あの、今夜も、って」
「私は知っています。あなたも、かつて隣にいた方のことも」
喉を絞められたような感覚が襲う。足元がふらついて、尻餅をついてしまった。
「……あなた、誰なんですか。なんで、そんなこと」
「信じてもらえないのを承知で告げますが、私はこの桜の木の精です。ですので、あなた方がこの時季を迎えるたび足を運んでくれていたのを知っていました」
このあたりで一番大きいというわけでもなかった。それでもあの人と見つけたとき、お互いに特別目を奪われた。他に客がいないのを不思議に思ったものだ。
何年も通ううちに、すっかり二人だけの特別な場所となっていた。
その桜の、精だって?
「ちょ、っと待って。ほんと、意味が」
「あなた方は毎年、私を愛おしく見守って、時には優しく触れてくださいましたね。そのおかげで私も立派に咲き誇れていたのです」
記憶がよみがえっていく。必死に蓋をした想いが、にじみ出していく。
「特にあなたは、ただまっすぐに毎年私に会いたいと願ってくれていました。本当に、嬉しかった」
肩に触れる感触は、あの人よりも、柔らかい。
「このようにお会いするつもりはありませんでした。ですが、心配で。あなたまで、そのお命を失ってしまいそうで、黙って見ていられなくなりました」
目の裏が熱を帯びていく。あの日、とっくに涙など涸れ果てたと思っていたのに、まだ出し足りないのか。
「……俺なんかがいなくなったって、君には関係ないだろ」
「いいえ、関係ありますとも」
意外に近くから聞こえた声にゆっくり顔を上げる。
年齢不詳、皺一つない顔、中性的過ぎて二次元の世界でないと浮いてしまう容姿。
ああ、確かに彼は人間ではない。
「あなたがいなくなったら、きっと私はすぐさまこの身を枯らしてしまう。会えなくなるなんて、耐えられません」
肩から細かい震えが伝わってくる。茶色と緑のオッドアイが、今にも涙をこぼしそうに不安定に揺れている。
「……俺がいなくなっても、悲しんでくれる人なんていないって思ってた」
両親はとうに他界した。特別仲のいい友人はいない。
あの人が、すべてだった。
彼が緩く首を振る。
「少なくとも私にとっては、あなたは命の恩人みたいなものです。これからもいてくださらないと、困ります」
『そばにいてくれよ! お前がそばにいてくれないと……俺は、もう、生きていけない』
『お前が俺をこんなにしたんだぞ! 責任、とれよな……!』
やけくそ気味に、あの人に投げつけた告白とは呼べない言葉の数々を思い出す。
受け入れてくれたときの、豪快で気持ちのいい笑顔を思い出す。
まさか立場が入れ替わるとは、人生は本当にわからない。
「今度は私が、あなたを護る番です。護らせてください」
両手を包み込むように握りながら、まるでプロポーズのように彼は告げる。
「……護るって、君、ここから離れられないんじゃないか」
変なところで現実的になる癖がここでも出てしまった。
「それは今から考えます。どうにかしますのでご心配なく」
「わ、わかったよ。でも今は大丈夫だから」
本当に思考を煮詰めそうになっていたので慌てて止める。
「また、会いに来るよ。約束する」
彼のせっかくの厚意を無駄にするのは気が引けるし、どうせなら非現実に身を置くのも悪くないと思い始めていた。
現実を普通に生きるのは、まだ、つらい。
「……はい。願わくば、あなたの一時の、拠り所となれますよう」
向けられた笑みは、どこか寂しそうに見えた。
#ワンライ
片翼で鳥は飛べない
くるっぷの深夜の真剣創作60分一本勝負 さんのお題に挑戦しました。
使用お題:「阿吽の呼吸」「雛」です。
お題に触れているのは最初だけで、後半はお題とあまり関係なくなってしまいました😅
-------
「西島、そこを曲がった先だ!」
頷いた彼は走るスピードを一層上げる。見失わないよう懸命に足を動かした。
予想通り道を塞ぐように立ち塞がっている数人の敵に、早くも西島は踏み込んでいた。相変わらず鮮やかな体術を駆使して、果敢に攻めてくる者たちを次々なぎ倒している。
ふと気配を感じてさりげなく視線を配ると、彼の死角になる位置から銃を構えている仲間がいた。素早く懐にあるナイフを投げつけて距離を詰め、押さえつける。
「死ぬのはお前のようだな」
後頭部に突きつけられたのが何か、説明されるまでもない。
——落ち着け。焦る必要は全然ない。
「馬鹿だな。気づいてないとでも思ったか?」
身震いしたくなる気配が近づいているが、相当鈍いのか察知している様子はない。
のんきに訊き返してくる声は、途中で汚い悲鳴に変わった。
「大丈夫? 篠崎」
「ふん、間に合ったか」
「ひどい、せっかく助けてあげたのに」
「ばーか。お前なら余裕で間に合うって信じてたからだよ」
先ほどまでの奮闘が嘘のような、どこかのんびりとした口調と雰囲気につられそうになりつつも報告を入れて、待機している仲間が来るのを待った。
「まったく、仕事のときは無駄に活躍するのにプライベートではこれだもんな」
「しょうがないじゃん。おれ、ほんと生活能力なさすぎるんだもん」
仕事のときはどちらかというと西島主体で動くことが多いが、その舞台から降りた瞬間、完全に役立たずと化す。もはや雛のように後をついて回るだけと言っても過言ではない。
片づけできない、料理できない、時間通りに起きられない、とにかくないない尽くし。
初めて会ったときは、こんな人間が世の中にいるのかと衝撃を受けたものだ。
「篠崎のおかげで毎日生きていられるから、ほんと感謝してるんだよ」
「どうせなら仕事でそれくらい評価されたいね。どうしたって目立つのはお前だから」
「大丈夫だってー。おれだって篠崎のいないとこですごく言われるよ。お前は篠崎がいないと輝かないとかお前を完璧にフォローできるのは篠崎しかない感謝しろとか」
「せめて僕の前で言ってくれ……」
文句を言いつつも、内心にやにやしていた。こういうのは自分のいないところで褒めてもらうほうが嬉しさ倍増だったりする。……まさか、それを見越して? なんたって仲間は彼に負けず劣らず個性派が揃っているから。
作った夕飯をテーブルに並べていると、西島がにこにことこちらを無駄に見つめていた。はっきり眉根を寄せる。
「また余計なこと考えてるなお前」
「そう? おれは嬉しいなーってしみじみ実感してるだけだよ」
「嬉しい?」
「だって職場だと完璧人間みたいに思われてる篠崎がおれの前だと遠慮なく愚痴るから」
変な声が漏れた。くそ、やっぱり言った通りじゃないか。
「人間ずっと気を張ってると精神やられるし? お前は生活面で僕に迷惑かけてんだからそれくらいいいだろ」
「おれなんにも言ってないじゃん。ふふ」
最後の意味深な笑いはなんだ、気持ち悪い。突っ込むのは絶対面倒だからしないけれど。
「な、なんだよ?」
「そういうとこがかわいいなーって思ってるんだよ。いつも」
掴まれた腕が全然ふりほどけない。見た目はぼんやりしているが、少なくとも力は自分より上なのだ。
「いらんことしたらメシ食わせないからな」
絶対この時間にはふさわしくないアレコレをされる。先手を打たねば。
「的確に弱点突いてきたね。さっすがパートナー」
「ありがたくない褒め言葉をどうも」
何度そっちのペースにのまれるという屈辱を味わってきたと思ってる。
「おっと、力ずくも禁止だ。作るのもやめるぞ」
一番の好物である自分の手作り料理も存分に活用させてもらう。
「むう、恋人に向かってひどくない?」
「タイミングを考えろというだけの話だが?」
ようやく解放された。と安堵したのが間違いだった。
「おれが今食べたいのは篠崎だけ、なんだけどな」
最高に頭の悪い台詞だが、耳元で囁くのは反則じゃないか。こいつもピンポイントに弱点を突いてくる。
「なんてね。君のご飯が食べられなくなるのはいやだから、全部終わったあとでいただくよ」
ふざけるないい加減にしろ!
という反撃は、わざとリップ音を響かせたキスをされ、素早く逃げられたせいでタイミングを逸してしまった。
真面目な声を作ってまで本当にバカとしか言えない。でもそんなバカと飽きずに一緒にいるのだから、人のことは言えない。
「しのざきー、早く食べようよ」
「誰のせいだよ」
呆れながらも、口元が緩んでいるのは隠せなかった。
――明日朝早いから、いただかれるのは全力で拒否するが。
#ワンライ
隣の幼なじみがマジです
創作BL版深夜の60分一本勝負 のお題に挑戦しました。
使用お題は「吐息」「ゼロ距離」です。
-------
「いいよ。考えてやるよ」
もちろん冗談のつもりだった。
今まで自分自身そんな気配を感じたことは一ミリもなかったし、これからも起きるわけがないと信じていた。
彼は幼なじみで一番の友達だった。
普段は自分のあとをついて回る甘えん坊かと思えば、言うときははっきり言うし、彼が前に出るべきと己で判断したときの動きは全く迷いがない。
まさに「守り守られる」という言葉が似合う関係だった。
それが、なんだ。急に「ミツが好きだ」と真面目な顔で告白なんかしてきて。
「そういう意味で好きって、俺は違うぞ」
「わかってる。ただ、言ってみただけだから」
明らかに狙って言ったと、もちろんわかっていた。彼、ユウキは大事なことを「ついうっかりこぼす」性格ではない。
「まあ、これで友達やめるつもりはないけど」
「相変わらずわがままだな。俺が気持ち悪いから絶対いやだ! ってごねたらどうするんだよ?」
てっきり泣きついてくるかと思ったが、ユウキは熟考している。嫌な予感がするのは気のせいだろうか。
「二度とそんなこと言えないように無理やり説得しちゃうかも」
予感は当たっていた。本当に降参するまで諦めなさそうだから冗談に聞こえない。
「でも、どうするの? おれ、今のところ諦めるつもりは全然ないんだけど」
その訊き方は正直ずるいし困る。たとえば絶対友達以外ムリ! ときっぱり言っても意味がないということになる。
「どうにもならないだろ。お前と恋の始まりなんて見える気配すらないね」
しかし、よくも悪くも諦めの悪いのがユウキだった。
「恋の始まり……ときめき?」
顎を触りながら大真面目につぶやく。
「ほら、相手にときめきを感じたとき『これって恋?』みたいに自問するやつあるじゃん。それだ」
「待て待て、一人で勝手に話進めんなって」
さらに嫌な予感が強まった気がしてならない。
ユウキは一歩距離を詰めると満面の笑顔で見上げてきた。
「ねえ、ミツをときめかせられたらさ、おれと恋人同士になること真面目に考えてくれる?」
アホか、と切り捨てようとしてとどまる。
たぶん彼は諦めないであれやこれやと手を尽くして条件をのませようとするだろう。もっと面倒になるのは勘弁してほしい。
「いいよ。考えてやるよ」
絶対にユウキを親友以上の色眼鏡で見ることはない。
自分の感情を信じていたから、敢えて乗ってやった。諦めて今のポジションのままでいることを選ぶ未来しか見えていなかった。
「ほんと? ありがとう!」
語尾に音符マークでもついていそうな言い方ではあったが、まあ、しょせんは男だしな……。思わず苦笑がこぼれる。
「約束したのはそっちだからね。覚悟してよ?」
一瞬で、ユウキの双眸が視界を埋めつくす。緩やかな月を描いている。
「そんなに無防備で大丈夫? おれ、調子に乗っちゃうかもよ?」
唇に、吐息がかかる。すべての神経が奪われてしまったように身体が動かない、突き飛ばしたり茶化したりできない。
「まあ、ここで無理やりしても意味ないし、宣戦布告ってことで」
こんな刺激的な宣戦布告があるか。
――初めて、ユウキの恐ろしさが身にしみた瞬間だった。
#ワンライ
ひっつき虫が可愛く見えるまで
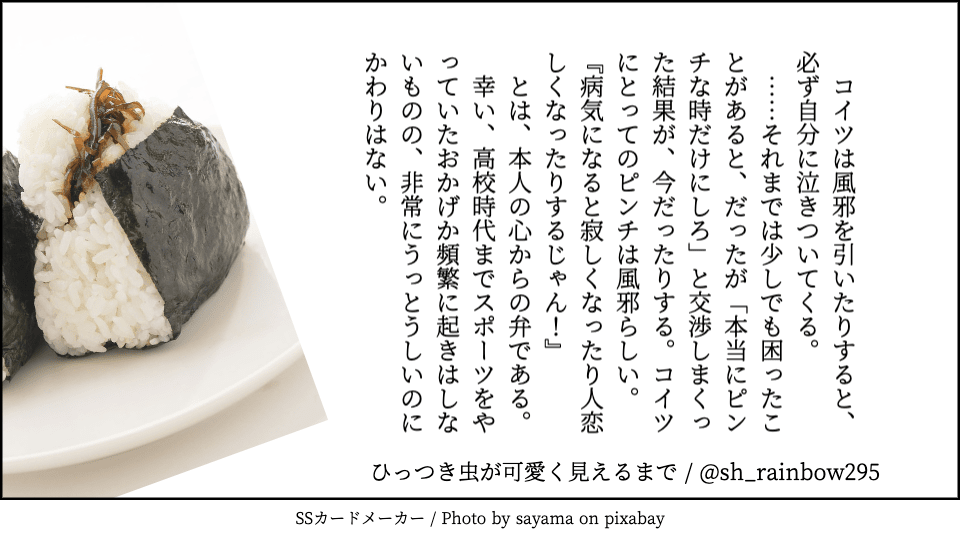
ふらっと思いついたまま書いてみたものです。
主人公:無自覚な友達以上恋人未満
お相手:片思い
な雰囲気です。
-------
コイツは風邪を引いたりすると、必ず自分に泣きついてくる。
……それまでは少しでも困ったことがあると、だったが「本当にピンチな時だけにしろ」と交渉しまくった結果が、今だったりする。コイツにとってのピンチは風邪らしい。
『病気になると寂しくなったり人恋しくなったりするじゃん!』
とは、本人の心からの弁である。
幸い、高校時代までスポーツをやっていたおかげか頻繁に起きはしないものの、非常にうっとうしいのにかわりはない。
「安藤~どこ行くんだよ~オレを一人にしないで~」
「だー! 買い出しだってんだろが!」
「そんなの宅配とか通販でいいじゃんか~」
「今すぐ持ってきてもらえるわけないし配達の方に申し訳なさすぎるわ! てか徒歩5分もかからないコンビニなんだから我慢しろっての!」
これである。毎回、これである。
とにかくべったりひっついてくるのだ。いくら友人とはいえ同性に隙間なくくっついて気持ち悪くないのだろうか?
「ったく、お前は毎回毎回しょーもないな……」
やはり寝入った隙に行くしかない。一応病人だから気を遣う心はあるものの、精神力が異常にがりがり削られて、気を抜いたら共倒れしてしまうんじゃないかと思うこともある。
「へへ、安藤が優しいとこも毎回変わらないよ」
「へいへい、嬉しいお言葉をどうも」
ベッドに大人しく横になった石川はふにゃりと口元を緩めた。身長が180以上ある、精悍な男の笑顔にはつくづく見えない。
「つーか、いい加減彼女とか作れよ。よっぽど甲斐甲斐しく世話してもらえんぜ?」
余計なお世話だろうが、言わずにはいられなかった。自分だって、いつまでも「お世話係」をやらされたらたまったもんじゃない。
「……え?」
さっきまでの笑顔はどこへやら、見事に固まってしまった石川にこちらも面食らう。
「な、なんだよ。俺ヘンなこと言ったかよ。そりゃ余計なお世話だと思ったけどよ」
その気になれば、恋人という関係を手に入れられる容姿も性格も備わっている。他の友人もきっと同じ評価をするだろう。
「……オレを捨てるんだ」
全く予想外の言葉に勢いよく殴られた。恋人に縋り付くダメ男そのものじゃないか。
「オレが頼れるのは安藤しかいないのに……」
「いやいや、他にもいるだろ。お前が俺にばっか言ってくるだけで」
「オレは安藤がいいの!」
本当に、物理的に縋り付いてきた。振りほどきたくとも病人相手に本気は出せないのに、ものすごい力が腕にかかっていて痛い。
「おま、ちょっと力ゆる」
「安藤じゃなきゃイヤなんだ。いつだって、安藤にそばにいて欲しいんだよ」
似たようなことは高校生の頃から言われてきた。まるでお熱い告白のようにも聞こえると冗談まみれで返しては石川がただ笑って、気づけばやり取りの頻度は減った。
どういうつもりで言葉にしているのか、深くは考えていなかった。ただ、石川がどこか寂しそうな雰囲気を漂わせていたような気はする。
「そ、そばにって、なんか、意味合い違うように聞こえるんだけど」
今日はいつもと違う。風邪を引いているせい? だとしてもこんなに戸惑うだろうか。らしくない返答をしてしまうだろうか。
「ちがくないよ。オレにとっては一緒だから」
見上げてくる石川の瞳は完全に高熱で揺れていた。触れたら崩れてしまうんじゃないかとつい思ってしまうほど、頬も熟れすぎている。
「オレには安藤だけだもん。知らないでしょ、オレがどんだけ安藤を」
「ま、待て待て。お前風邪引いた勢いで変なこと言うんじゃねえって」
この流れはお互いにとって不幸しか生まない気がする。もし危惧している通りの流れになったら正直受け止め切れない。
「変なことじゃないよ。オレ、前から言ってるじゃん」
触れられた腕から伝わる熱さで、自分まで眩暈でも起こしそうだ。こんな展開になるなんて誰が想像しただろう。
「安藤……本当に、だめ? オレ、一ミリも望みなし?」
これでもかというくらいに眉尻を下げて、図体とは正反対の空気を一気に纏いだした。
正直、ずるい。こんなの、駄目だと一刀両断しづらいじゃないか。いや、ここで中途半端な態度を晒してしまうのがいけないんだと思う、思うが。
「……なんだかんだで、大事な奴だとは思ってるよ。じゃなかったら、クソ面倒なお世話なんてしねえし」
石川が求める意味とは違うだろうが、嘘ではない。一番つるんでいる友人だし、一緒にいると気が楽というか、自然体でいられる存在だったりする。
「……安藤がそんなこと言ってくれるの、はじめてだね」
本当に驚いたようで、小さい双眸がかなり見開かれている。
「ありがとう、納得したよ。今はね」
「今は、ってなんだよ」
「うーん……そうだなぁ」
頬をそろりとひと撫でした石川は、唇の端をわずかに持ち上げた。
「覚悟しといてね、ってことかな」
小悪魔のような笑みとは、今のような表情を言うのだろうか。
初めて、心臓が無駄に高鳴ってしまった。
「へいへい。心からお待ちしておりますからいい加減寝ろ」
悟られないよう、石川の頭を枕に押しつけて布団をかぶせる。
きっと自分も見えない熱に浮かされているに違いない。そう思い込まないと、動揺を抑えられそうにはなかった。
愛したくて愛したくて
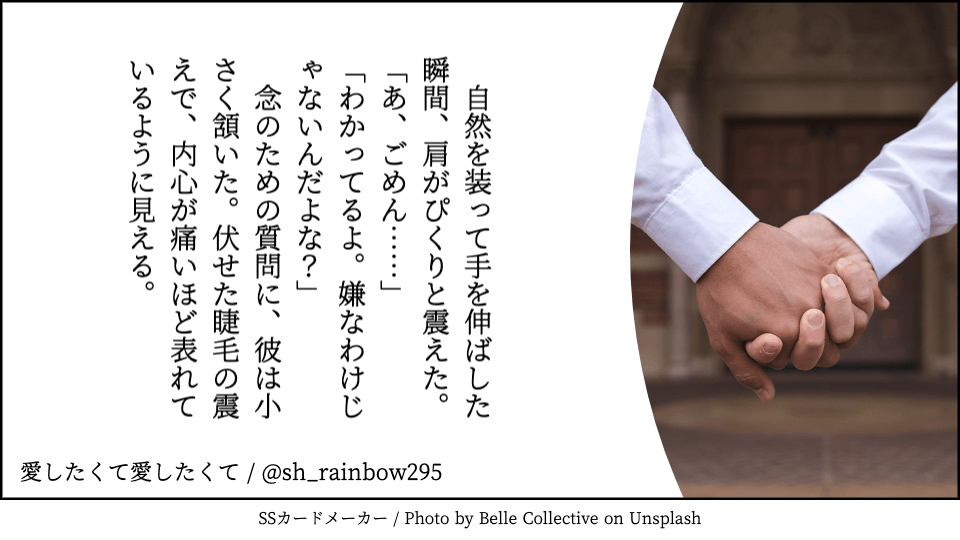
お題bot* のお題に挑戦しました。
お題は「愛されることには、まだ不慣れで、」を使いました。
-------
自然を装って手を伸ばした瞬間、肩がぴくりと震えた。
「あ、ごめん……」
「わかってるよ。嫌なわけじゃないんだよな?」
念のための質問に、彼は小さく頷いた。伏せた睫毛の震えで、内心が痛いほど表れているように見える。
勇気を振り絞った告白に、受け入れてもらえた瞬間の自分以上に彼は驚いていたと思う。
『告白ってしてもらったことなくて……いつもこっちからしてたから』
脈があるとわかっていても、自分から告白してOKをもらわないと気持ちを信じられないこと。
だから多分、告白されていたとしたら、その瞬間に気持ちは冷めてしまっていたかもしれないこと。
普通じゃないとわかっていても逃れられずにいたことを、告白したその日にカミングアウトされた。
『え、じゃあなんで俺は……』
『わかんない。わかんないけど、大丈夫だったんだ。むしろ、なんかぶわーってなったっていうか、もっと好きになったっていうか……』
普段の付き合いで驚くほど正直者だと知っているから、ひどく戸惑っている姿を疑う気にもなれなかった。
『じゃあ、正式に付き合って、みる?』
普通なら諸手を挙げて喜ぶ場面でお互いおそるおそるなのも変な状況だが、改めて気持ちを確かめてみると、控えめに笑いながら頷いてくれた。
「逆に見てみたいかもな、お前の『愛し過ぎちゃう』姿」
微妙に伝わってくる緊張感をほぐすように肩を軽く撫でながら言うと、びっくりしたようにこちらを見つめてきた。
「トレーニング中なのはわかってるけど、愛されるのも好きだからさ。たまには受けたい」
『恋人に愛される喜び、っていうのを確かめてみたいんだ。あと、勉強もしてみたいし……だからしばらくは、受け身でいさせてくれる?』
冗談を言っているようにはもちろん見えなかったし、それだけ自分との関係を本気で考えてくれているのだと嬉しくなった。
今も不満らしい不満は特にないものの、欲が頭をもたげ始めたのもまた、事実で。
「……説明したこと、あったよね?」
いつでも「100%」を出し切って接していた結果、ある人は重すぎると苦し紛れに呟かれ、ある人は束縛されているみたいで嫌だと泣かれ……反省して言動を改めてみたつもりでも、ゴールは「離別」一本だったという。
興味本位もあるが、そこまでの愛情を浴びてみたいという純粋な願いもあった。
たとえどんな姿であっても、彼への想いは絶対に揺るがない。
「わがまま言ってるのは自覚してる。強制もしない。……でも、味わってみたいなぁ」
敢えて砕けた言い方をしてみた。
「完全再現じゃなくていいから! こんな感じだったかも、ぐらいで全然」
「余計に難しいよ……でも、僕のわがままに付き合ってもらってるもんね」
気合いでも入れるためか一度頷くと、肩に伸ばしていた手をそっと外し、緩く握り込んできた。
思わず息をのむ。
覗き込むように見つめてきた瞳の輝きが、いつもと違う。不快にならないぎりぎりのところで捕らわれているような、どっちつかずの気分になる。
「いつも、本当にありがとう。君には負担ばっかりかけてるよね」
まとわりつくような甘い声だった。普段は緊張の方が目立つのに。
「僕が君を好きな気持ち、ちゃんと伝わってるかな。いつ愛想尽かされるかわかんないって、毎日不安なんだよ?」
握ったままの手の甲を、自らの頬に擦りつける。昔漫画でよく見た、段ボールに入れられた子犬のような上目遣い付きだ。
すでになかなかの破壊力を発揮している。これで全力なのか、まだまだなのか。
「そんなことあるわけないだろ? 本気で好きだから告白だってしたんだし」
それでも、あくまで日常生活の延長のつもりでいきたい。自ら望んだのは確かだが、ただ享受するばかりでは対等じゃない。
「……ほんと、君の言葉って不思議。すごく信じられるんだ。すごく、安心する」
自然に距離を詰められ、抱き込まれた。わずかに速い心音に口元が思わず緩む。
「だからかな、僕にできることなら何でもしたい。君の願いを全部叶えてあげたい」
背中にあった両手が顎を掬い上げる。まっすぐに与えられる視線から摂取できる糖分の限界値は、とうに超えている。めまいでも起こしてしまいそうだ。
「ねえ、僕にしてほしいこと、ない?」
「わざわざ言わなくたって、充分してもらってるよ」
「僕は足りない」
とん、と肩を押されて、気づけば彼を見上げる体勢になっていた。いつも使っているソファは意外に固いんだなと、どうでもいい感想を内心呟いてしまう。無理やり意識を逸らしていないと今すぐ抱き潰してしまいそうで、安易にその選択肢をとるのは嫌だった。
「僕がどれだけ、君に夢中なのか……知らないでしょ?」
「わかってるけどな」
触れるだけのキスを終えた瞬間、彼の瞳が頼りなげに揺れた。どうやら心の奥に巣くった不安は、相当しつこく根付いているらしい。
「俺も夢中じゃなかったら『お願い』聞こうなんて思わないし、『わかってる』なんて言えないだろ?」
「でも……」
キスを返して、頭を包むように胸元へ引き寄せた。くせの弱い髪は相変わらず、指に簡単に絡まる。
「告白した時以上に好きになってる。できるんなら四六時中こうやって一緒にくっついてたいし、いっぱい愛したいって思ってるんだからな」
シャツを掴む手にぎゅっと力が込められた。触れ合っている箇所すべてが妙に熱く感じるのはきっと、気のせいじゃない。
彼に感化されて、自分も相当恥ずかしい台詞を口にしている自覚はある。あくまで彼のためだ、悶えるのは一人きりになった時でいい。
「……ずるい」
くぐもった声は震えていた。
「僕より、君の方がトレーニングになってるんじゃない」
「はは、そうかな」
「本気で、君なしじゃ生きていけなくなっちゃうかも」
「そりゃ光栄なことで」
もっと愛されるよろこびを味わって、二度と離れられないところまでいけばいい。
少なくとも、自分はとっくにそうなっているのだから。
#お題もの
【300字SS】世界でたったひとりだけ
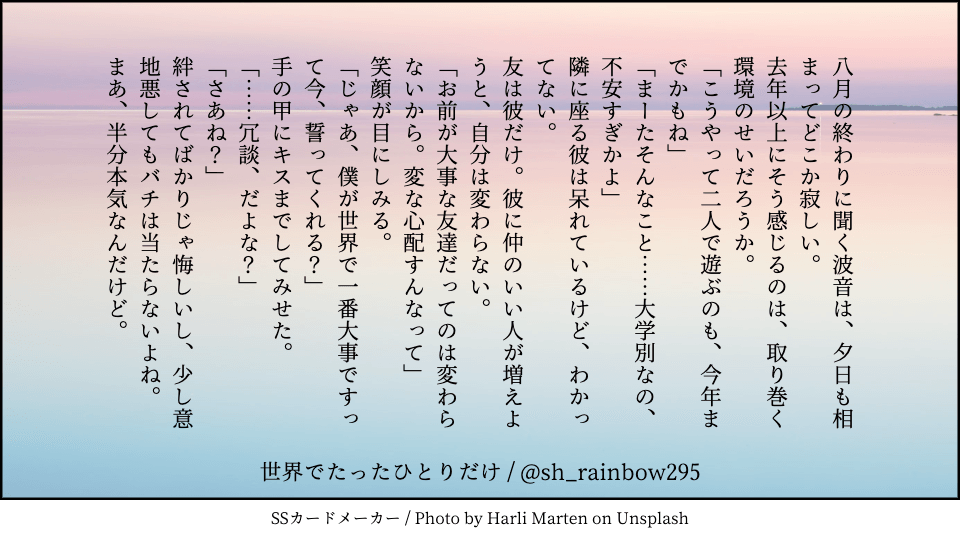
300字SS のお題に挑戦しました。お題は「波」です。
めっちゃ遅刻しました💦
-------
八月の終わりに聞く波音は、夕日も相まってどこか寂しい。
去年以上にそう感じるのは、取り巻く環境のせいだろうか。
「こうやって二人で遊ぶのも、今年までかもね」
「まーたそんなこと……大学別なの、不安すぎかよ」
隣に座る彼は呆れているけど、わかってない。
友は彼だけ。彼に仲のいい人が増えようと、自分は変わらない。
「お前が大事な友達だってのは変わらないから。変な心配すんなって」
笑顔が目にしみる。
「じゃあ、僕が世界で一番大事ですって今、誓ってくれる?」
手の甲にキスまでしてみせた。
「……冗談、だよな?」
「さあね?」
絆されてばかりじゃ悔しいし、少し意地悪してもバチは当たらないよね。
まあ、半分本気なんだけど。
#[300字SS]
最後の嘘と願って
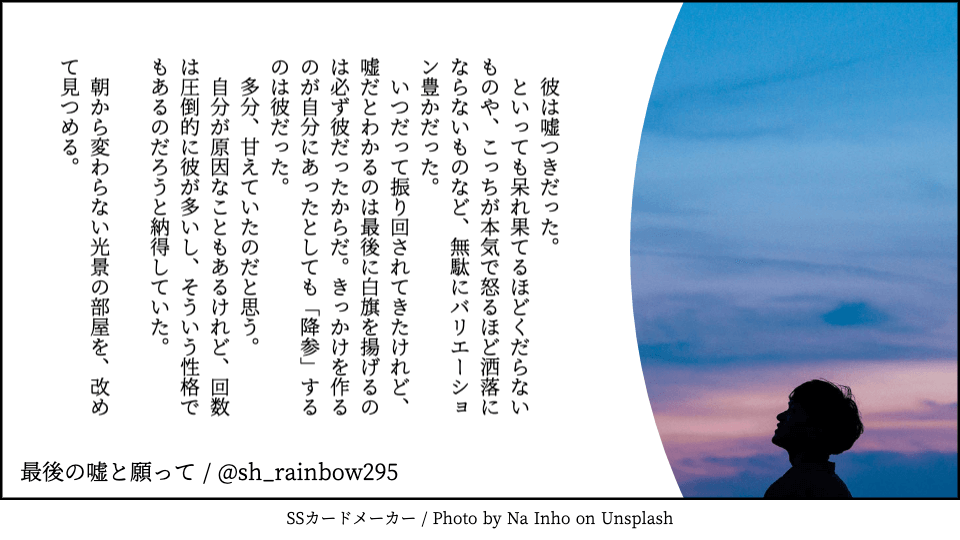
深夜の真剣物書き120分一本勝負 のお題に挑戦しました。
お題は「③西日が差す窓」を使いました。お題要素は軽く触った程度です😅
どうしてもユーミンの曲『最後の嘘』が頭から離れなくなってしまいました……該当の歌詞は「朝日が差し込む〜」なんですけどね。。
-------
彼は嘘つきだった。
といっても呆れ果てるほどくだらないものや、こっちが本気で怒るほど洒落にならないものなど、無駄にバリエーション豊かだった。
いつだって振り回されてきたけれど、嘘だとわかるのは最後に白旗を揚げるのは必ず彼だったからだ。きっかけを作るのが自分にあったとしても「降参」するのは彼だった。
多分、甘えていたのだと思う。
自分が原因なこともあるけれど、回数は圧倒的に彼が多いし、そういう性格でもあるのだろうと納得していた。
朝から変わらない光景の部屋を、改めて見つめる。
昨日の夜はいつもと同じようでいて、主に自分自身の勝手が少し違っていた。
だから「きっかけ」を作ったのは間違いなく、自分。
「どうしたの、なんからしくないじゃん?」
軽口を叩き合う延長上のような口調だったのは、多分気遣ってくれていたのだと思う。それに真面目な空気にしたところで、素直に吐き出すわけもなかった。
「……うるさいな。ほっといてよ」
離れている間どういうことがあったのか察せなんて傲慢でしかないのに、そう願ってしまった。
仕事で嫌なことがあっただけ。いつもなら鼻で笑って流せるレベルが、今日はなぜか胸につかえてしまっているだけ。疲れが溜まっているせいかもしれない。
ここまでわかっていながら、彼には伝えなかった。悪い癖だ。
「あ、もしかして冷蔵庫にあったショートケーキ食べたのバレた? ごめん、どうしても食べたくって」
ショートケーキは確かに買ってあった。まだ確認していないが、たとえ嘘だとしても「甘いもの好きな自分のために、明日にでももっと美味しいケーキを買ってくる」という意味だったのだと思う。
そこまで推察できたのは、数時間後の未来でだった。
「嘘でも本当でも、ケーキくらい別にいいよ。……いいから、そういうくだらないの」
放っておいてほしかった。一晩すれば元通りになって、こんなやり取りにも苛ついたりしなくなる。
彼は何も知らないのに、あまりにも感情的になりすぎていた。
「……ごめん。何かあったんだね」
「そう思うなら、ほっといて」
それからどんなやり取りをしていたのか、細かいところは思い出せない。
ひたすらに、せっかく伸ばしてくれていた手を振り払い続けていた。ひどい態度だと頭のどこかで鳴っていた警報も無視して、気づけば部屋を包む空気はかつてないほどの重苦しさに溢れていた。
「……あのさ。俺と付き合ったこと、やっぱり後悔してるんじゃない?」
一言一句、声の調子も、表情も忘れられない。
笑っていた。雰囲気に似つかわしくないはっきりとした声だった。やせ我慢のようなものだったと今ならわかる。
反論できなかったのは、彼の問いかけが頭の中でぐるぐると回り出し、まるで必死に材料をかき集めているようだったから。
「……ごめん、嘘。だけど悪い、言い過ぎた」
ちょっと頭冷やしてくるよ。
それが、三日前に聞いた彼の最後の台詞だった。
「こんなに落ち込んでるのに、後悔なんてしてるわけないでしょ……」
今さらな返答だった。わずかでも口ごもった時点で、あの時の彼にとっては肯定されたも同然だ。
異性と付き合うのをやめて、初めてできた同性の恋人だった。好きという気持ちにあれから揺るぎはないものの、半年ほど経って同性なりの難しさや悩みが出てきていたのも事実だった。
隠していたつもりでもあんな言葉が飛び出すのだ、きっと見透かされていた。だから「頭を冷やす」と嘘をついて、出て行ってしまったのでは……。
「ほんと馬鹿だな、僕」
後になって後悔する癖は直る兆しが全くない。今日はまともに食事すら取れなかった。お出かけ日和の天気なのに身体は全く動かず、部屋の中は薄暗い。
そういえば、ベランダのカーテンを閉めたままだった。
『ここ、日当たりがすごいいいんだってさ。日当たり大事!』
その一声で借りることを決めた部屋だったのを思い出しながら、ベージュ色のカーテンを開ける。
「まぶし……」
真正面から浴びているような感覚に陥る。やたら目に沁みる気がして、ぎりぎりまで目蓋を下ろす。
窓を突き抜ける光の大元は朝も夕方も一緒なのに、どうして後者はやたらもの悲しい気分にさせられるのだろう。……違う。きっとひとりきりだからだ。二人でいる時の空気はもっと、穏やかだった。
――このまま終わりだなんて思いたくない。頭を冷やすが嘘だなんて、思いたくない。
目元を窓に押しつけた。光の強さとは裏腹にひんやりとした温度が、少しずつ熱を奪っていく。
「……まだ、決まったわけじゃない、よな」
近所を探しに行ってもいなかったのは、たまたますれ違っただけだと信じたい。
そもそも、仕事から帰ってきても部屋の様子に変化はなかった。何より、彼の荷物は全くの手つかず状態にある。スマホすら、未だテーブルに置かれたままなのだ。
今日は気力が底まで落ちてしまったけれど、いつまでも立ち止まっているわけにはいかない。
今度は自分が「降参」する番。
そして、こんな嘘はもう最後にしてとお願いしなければ。
#ワンライ
ダーリンはすでにおみとおし

創作BLワンライ&ワンドロ! のお題に挑戦しました。
お題は「ハニー」です。そのまんま? 使いましたw
-------
「今回も助かったよ~さっすが俺のハニーだね!」
「お前、何でもかんでもハニーって言っとけば済むと思うな……って待て!」
突っ込みが終わる前に彼は走り去ってしまった。周りの生徒が小さな笑い声をあげていて、慣れてしまったとはいえ自然と眉間に力が入る。
……人の気も知らないで、気軽に肩を組んできて、ハニーだなんて。
無視すればいいのにできない理由があるからこそ、表面上は「仲のいいお友達」の彼――国枝(くにえだ)をただ、恨めしく思った。
そんな自身の感情にはおかまいなしに、国枝の過多なスキンシップと「ハニー」呼びは容赦なく続く。
「あ、いたいたハニー! あのさ、これから暇? 部活なかったよね?」
満面の笑みがいつも以上にまぶしく映るのは己の理性が限界を迎えつつあるせいなのだろうか。いや、違う。認めたら多分いろいろと終わる。
「……部活はないけど、用はある」
不自然にならないよう視線を机にある鞄に逸らして、呟く。
「うそつき。ほんと、そらちゃんってわかりやすいよね」
「お調子者」の色が抜けた声音に、思わず国枝を見上げ直してしまう。
普段は丸みの目立つ瞳が、今は鋭さを増してこちらを射抜いている。
だが、それもわずかな時間の出来事だった。
「ハニーにとってもすっごく大事な用事なんだよー! だから、ね? 付き合ってよ、お願い!」
まるでお参りする時のようにお願いされてしまった。はっきり言って大げさすぎる。目立つためにわざとそういう振る舞いをしているんじゃないかと邪推してしまうくらいだ。
「わかったわかった、だからやめろ今すぐにだ。じゃないと付き合ってやらんからな!」
言い終わる前に、鞄を掴んで教室を出ていく。
国枝がやたら構うようになってきたのは去年の春――同じクラスになってからだが、我ながらうまく受け流してきたと思っていた。なのに最近はやたら苛立って仕方ない。国枝の無邪気すぎるパフォーマンスがここまで恐ろしいとは。
ああ、早く一人になりたい。
「おい、用事があるんじゃなかったのか」
「ん、そうだよ? だからおれん家に来たんじゃん」
何を言ってるんだ、とはっきり書いてある顔で、国枝はお茶の入ったコップを持ってやってきた。
「へへ、そらちゃんが部屋に来るのすっごい久しぶりだね。ここんとこ全然来てくれないからさ~」
「……帰る」
反射的に立ち上がった。理由は探りたくもないが、このままこの空間にいたらまずい気がする。
「ま、待って待って! まだ用件言ってないじゃん!」
「どうせくだらない理由だろ」
「違うよ!」
「全く、ちょっとでもお前を信じた俺がバカだったよ。いいから」
「……だって。あれくらいしないと来てくれなかったでしょ、空(そら)は」
声音と空気の変化に気を取られて、動きを止めてしまった。
「う、わっ」
肩を押された。思った以上の衝撃に足がもつれ、その場にみっともなく尻餅をついてしまう。
「な、んだよ……いったい、なんだってんだよ……」
立ち上がれない。視線の先の国枝は立ったままこちらを見下ろしているだけで、妨害されているわけでもないのに、なぜか力が入らない。
「いい加減、受け入れてほしいんだよね。おれも限界だから」
受け入れてほしい? 限界?
脈絡なく告げられた言葉に当然疑問を持つが……「限界」の二文字に妙に同調してしまいたくなるのは、自分も似た状態にあるから?
訊けるわけなどない。それは、自らの手の内も晒すことになる。
「どういう意味だって訊かないの? 空ならこういう意味わかんないとこは絶対突っ込んでくるじゃん」
こいつ、もしかして「わかってる」のか?
ありえない。完璧に押し隠してきたはずだ。たまに「ダーリン」と返してみても冗談で流れて終わっていた。周りの認識が「仲のいいお友達」止まりなのが何よりの証拠だった。
「相変わらず空は鈍いね。まあ、おれもあからさま過ぎたけど」
国枝の苦笑がまるで馬鹿にしたように見えて、思わずテーブルに手を伸ばしていた。
「ふざ、けるな……」
コップの中身を顔面にぶちまけられたくせに、国枝は拭いもせず平然としていた。ますます腹立たしい。惨めにさえ思えてくる。
「お前はいいよな? 毎日毎日ノーテンキに絡んでくるだけでいいんだもんな? 俺がどんな気持ちでいたか知らないで、本当にいい気なもんだ……!」
もう堪えきれない。少し先の未来の不安より、気持ちが楽になっていく欲望を止められない。
「空は、おれが悪いって言いたいんだ?」
前髪を軽く払って問いかける姿はまるで世間話のノリだった。ここまで内心が読めない国枝は初めてで戸惑いもあるが、もうどうでもいい。
「そ、そうだ。お前にどれだけ俺が振り回されてきたか、気づいてもいなかっただろ?」
「ふうん……」
国枝の双眸がすっと細められ、胸の奥が嫌な音を立てる。
本当はこっちが悪くてわがままなだけだとわかっている。余計なものを生んでしまったばかりに、一人で勝手に空回っているだけに過ぎない。
最初は自他共に認める「仲のいい友達」だった。いつから綻び始めたかなんてわからない。気づけば容赦なく膨れ上がる想いを押し込む方に躍起になり、国枝との普段の接し方さえわからなくなり、「友達」のままの彼がありがたくもありうっとうしくもある、複雑な感情を向けるまでになった。
国枝と、離れたくなかった。
必死だった理由はただ、それだけ。
「……っくに、えだ」
目線を合わせてきた男はなぜか、笑っていた。理由のわからない笑みを刻んでいる。
「じゃあさ。実はおれも空と同じ理由で振り回されてましたって言ったら、どうする?」
心臓が耳元で動いているような、変な錯覚を覚える。
国枝が、自分と同じ理由で、振り回されていた?
あんなことを言ったのは、いつの間にか生まれていた、友情以上の気持ちのせいだ。知られるわけにはいかないと頑なだったせいだ。
それと同じだと、目の前の男は告げている。
息が詰まる。両手で顔全体を塞ぐ。全身があっという間に熱くなってきた。
うそだ。だっていきなり、そんなことを告白されても飲み込めるわけが――
「ハニー」
ある時から幾度となく呼ばれた、もう一つの呼称が鼓膜をゆるく震わせる。
「ねえ、ハニー。おれはいつだって、冗談で言ったつもりはなかったよ」
顔を隠す壁はあっけなく破壊され、そのまま国枝の腕の中に閉じ込められる。
「ああ言ってれば、空はおれのものだって知らしめることができるでしょ?」
「ば……」
「馬鹿なことじゃない。だって、空は誰にも渡すつもりないもの」
こんな、とんでもない爆弾を隠し持っていたなんて。
完全に、してやられた。
想像以上に、こいつはぶっ飛んだ奴だった。
「あれ、なんで笑ってるの」
「笑うしかないだろ。あれだけ悩んでたのに、なんだよこの展開はって」
「ハッピーエンドでよかったでしょ?」
確かによかった。が、腹立つ。一発殴ってやりたい。
だが、その企みは国枝の派手なくしゃみで立ち消えた。
「ご、ごめん。さっきぶっかけたせいだな」
「これくらい大丈夫。……と言いたいとこだけど」
国枝の口元がいやに弧を描く。
すぐさま違和感を覚えたのに、次の瞬間にはベッドの感触が背中を覆っていた。
「せっかくだから、ハニーにあっためてほしいな」
見上げた先の、太陽のように眩しい笑顔がたまらなく、憎らしい。もちろん、言葉通りの意味でないと悟っているからだ。
「当然、断るなんて真似しないよね?」
「お、親が帰ってくるんじゃ……」
「残念でした。今朝から旅行中でーす」
「な、だ、だから俺を呼んだのか!」
「当たりー。それにいいの? 風邪引いたらそらちゃんのせいになるんだよ?」
最終兵器を突きつけられたら……もう、何も返せない。
「……わか、ったよ」
「そこは『わかったダーリン』って言ってほしいなー。……いや、待てよ。最中の時のがもっと萌えるか」
「調子に乗るな!」
せっかくだ、国枝の気が逸れている間にこっそり呼んでやる。
それくらいの反抗なら許されるだろう?
#ワンライ
結局、負けは確定
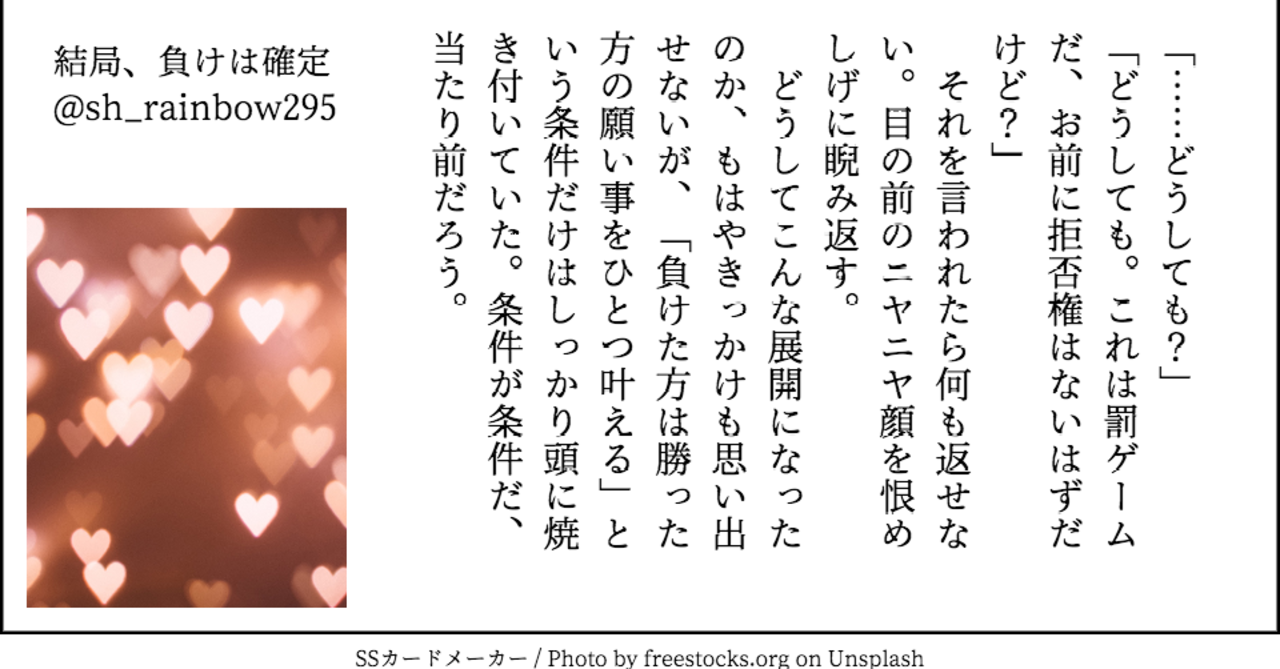
一次創作BL版深夜の真剣60分一本勝負 に挑戦しました。
・「どうしてもって言うならば」
のお題を使用しました。大学生ぐらいの2人がキャッキャしてるような感じですw
----------
「……どうしても?」
「どうしても。これは罰ゲームだ、お前に拒否権はないはずだけど?」
それを言われたら何も返せない。目の前のニヤニヤ顔を恨めしげに睨み返す。
どうしてこんな展開になったのか、もはやきっかけも思い出せないが、「負けた方は勝った方の願い事をひとつ叶える」という条件だけはしっかり頭に焼き付いていた。条件が条件だ、当たり前だろう。
そして自分は見事に敗者となってしまった。冷静に考えれば彼にゲームの腕で勝てるわけがないのに、さっきはどうかしていた。熱くなりすぎてしまった。
「で、でもさ? いくら恋人だからって普通に引くだろ? 女装してデートとかありえないって。しかも絶対スカートとか嫌すぎるわ!」
まさかの条件に、最初は空耳かと疑った。二回目で冗談だと思い込みたかったのに、許してもらえなかった。
「だから大丈夫だって。お前結構可愛い顔してるじゃん? ばれないばれない」
何て脳天気な恋人なのか。いや、これは違う。意地悪スイッチが全力でオンになっているんだ。
「そんなん理由になるか! あのな、周りって見てないようで見てたりするんだぞ? それに顔が可愛いって言ったって身長170以上あるしゴツめだし」
「俺と身長差そんなにないし、ぶかぶかした服着れば目立たないっしょ。姉貴、確か緩めの服いっぱい持ってたから大丈夫」
爽やかな笑顔を向けられても絶望しかない。お姉さんにどう説明する気なんだ。彼のことだからきっとうまく口が回るのだろう。ああ、お姉さんの身長が170近くあることが今は恨めしい……。
「あのさ。俺にとっては嬉しくもあるんだぞ?」
急に真面目な声で距離を詰められて、口ごもってしまう。
「何も気にしないで普通にデートできるんだぞ? 俺、密かに夢だったんだよ。その夢、叶えてくれないのか?」
眉尻まで下がっている。どこか気弱にも見える仕草がらしくなくて、柄にもなく戸惑いかけた。
「……そうなんだ。ごめん気づかないで……ってそんな手に引っかかるか!」
「あら。ダメ?」
「口の端っこがびみょーに震えてたぞ」
「顔に出てたか……しまったなぁ」
「大体、今までだって何回も堂々とデートしてるだろ。おれが嫌だっていってもお構いなしにベタベタしてくるじゃないか」
「俺はいつでもそういう気持ちで楽しみたいからね」
今の言い方はずるい。無駄に反応してしまったのは死んでも隠し通してやるけれど。
「じゃあ、誰よりも可愛い恋人を堂々と連れて悦に浸りたいっていうのじゃダメ?」
さっきの理由より信頼できる物言いだった。だったが。
「お前、そういう奴だったのか……若干引くわー」
「そうか? 俺はたまらなく嬉しいけどね」
頬に触れられたかと思った瞬間、唇を柔らかい感触が走る。
「だって、人目を引く奴の一番近くを占領してるんだぞ。どんな表情も独り占めできるし、こういうことだってできる。ものすごい優越感だと思わないか?」
また、何も返せなくなってしまった。
彼もそうだ。街中を歩けば、すれ違った異性が絶対反応する。時には声さえかけてくる。
そんな彼の「一番」に君臨しているのは、紛れもない自分。自分だけが、いろんな姿の彼を知っている。時には本当の心に遠慮なく触れることだってできる。
ああ、納得してしまったじゃないか。反論の材料がなくなってしまった。
「理解してくれたんだ?」
狙い通りとも取れる笑みが腹立たしい。何でお前は見た目がいいんだと、理不尽な言い訳を叩きつけたくなってしまう。
「わかったよ、わかりました。お前がどうしても、って言って聞かないからな」
これぐらいの負け惜しみは許してもらいたい。彼には全く効いていないみたいだが。
「ただし、一時間な。家を出てから一時間」
「短い。二時間、いや、四時間は欲しい。これは厳命だ」
彼の目が本気すぎて、受け入れざるを得なかった。
「……待てよ。悦に浸るって、別に女装してる必要なくね?」
「今さら気づいたのか?」
「……またお前にいいように乗せられたああああ!」
「どうも、ゴチソウサマデシタ。可愛い可愛い恋人さん?」
#ワンライ
わがまま猫な彼と僕

創作BLワンライ・ワンドロ ! のお題に挑戦しました。
お題は「花より団子」です。タイトルは適当だし、花より団子……? な出来です←
---------
二年前だったと思う。SNSでもかなり話題になったドラマだった。
僕はもちろん、バイト先の先輩後輩も友達も大体見ていたし、感想や考察を話し合うのが当たり前になっていた。
だが、今隣にいる僕の恋人は当時全く興味を示さなかった。
と思ったら、今さら「気になるから今度一緒に観たい。レンタルしてきて」とおねだりまでしてきた。本当に読めないヤツだと思う。
なのに……この状況はなんだ?
「あのさ……観てる? ドラマ」
第五話まで来たところで、僕はたまらず声をかけた。これからどんどん面白くなるというのに、この男の行動が信じられない。
「んー? 観てるよ、もちろん」
「って言いながら画面見てないじゃん!」
「へー、わかるの?」
「さっきからちょっかいかけられてるからね」
僕は、テレビは床に座って好きな体勢で観る派だ。彼はソファ派だから何となく縦に連なるような形になったのだけれど、そのせいで頭を撫でられたり耳たぶを触られたりと地味なスキンシップを受け続けている。
彼がイタズラ好きというのは今に始まったことではないけど、言い出しっぺがこの態度だとさすがに文句も言いたくなる。
「そっちが観たい観たいってダダこねるから借りてきたんだよ? なのになんなの?」
「なんなのって、そりゃ決まってるだろ? お前が可愛すぎるから」
思わず背後を振り向いた拍子に唇をさっと盗まれる。まるで手練れの怪盗だ。
でも正直、ときめきじみたものは全然ない。
「誤魔化しのつもり? 普段そんなこと言わないくせに」
「心外だな。口に出してないだけでいつもそう思ってるぞ?」
怪しい……。天の邪鬼と知りすぎてる僕からすればつい裏を読んでしまう。極端な話、スキンシップだけが頼りの綱だ。
というか早くドラマに戻りたいんだけどな……。展開を知ってても、本当に面白いと関係なく見れてしまうものらしい。
「俺は照れ屋だからそういうのは簡単に口にしないの。だからそう疑うなって」
隣に移動してきた恋人は頬を人差し指で突いてきた。完全に馬鹿にしている。
「というか、今んとこそんなに刺さってないんだよなードラマ。表情コロコロ変わるお前見てる方がよっぽど楽しいわ」
何なんだ全く。本当は、ドラマ見終わったらいろんな話だってしたかったのに。楽しみにしていたレンタル中の僕が急激に色褪せてきて、悔しさと苛立ちのあまりリモコンの停止ボタンを押しかけて……止まる。
「……僕、見てたの? ちょっかい出してるだけじゃなくて?」
「あれ、気づかなかった?」
頭をなでなでしてくるにやにや顔を呆然と見つめる。
「オチまで知ってんのに笑ったり泣きそうになったりしてさぁ。全然飽きないのなんのって。俺的にはそれが収穫だったなー」
逃げたい。あるいは布団にくるまりたい。無防備な状態を観察されてたなんて恥ずかしい以外ない!
思わず両手で顔を覆うも、遠慮なしに外された。そのまま押し倒されて、床に固定されてしまう。
「本当に天然だよな、お前」
「天然って、意味わかんない……」
それ以上の反論は、互いの口の中に消えた。
ドラマは、いつの間にか第六話に進んでいた。クライマックスに向けてますます盛り上がる大事な回だ。
けれど、もう頭に入る余裕はなかった。
#ワンライ
どこまでフィクションな恋物語か
一次創作BL版深夜の真剣60分一本勝負 のお題に挑戦しました。
・文化祭
のお題を使用しました。無理やり感ハンパないです💦
----------
「今日は抱きしめるだけ。次来た時、まだ僕のことが好きだったらキスしてあげる」
もちろん、好きなままだった。抱きしめられた時のあの高揚感と幸福感は、初めてに等しい強さだった。
「好きでいてくれてありがとう。じゃあ、約束通り……キスしてあげる」
人生で初めてのキスを、同性から受ける。
いや、性別は関係なかった。相手がこの人だったから、唇に最初触れられた時も、二度目三度目と繰り返されても、嫌な気持ちにならないどころか、もっと欲しくなった。
この人への想いは嘘じゃない。本物だとようやく確信できた。
「おれ、あなたのこと本当に好きです。何があっても絶対ぶれません。だからもう、確認はいりません。……付き合ってください」
自分を気遣って、段階を踏んでくれていたのはわかっていた。
今こそまっすぐに応えたい。偽りない本心を届けたい。
「……また、会いに来るよ」
返事はもらえなかった。それどころか、約束もなかった。
確定された未来が目の前に降りてくるはずだったのに、一瞬で手が届かなくなってしまったようだった。
嫌な予感がした。「会いに来る」と言われはしたが、それも果たされない気がしてならなかった。
——今度は、自分から会いに行かなきゃダメなんだ。怖いけれど、怖じ気づいていたらダメなんだ。
「まさか、君から来てくれるなんて思わなかったな」
唯一の手がかりだったバイト先に何日も張り込んで、ようやく会えた想い人。本当に来るとは思っていなかったようで、純粋な驚きだけが存在していた。
その場で言葉を連ねようとした自分の手を取ると、建物の裏に向かう。改めて対峙するも、なかなか彼は目線を合わせてくれない。
「……おれ、本気です。抱きしめてもらった時も、キスしてもらった時も、すごく嬉しかった。気持ち悪いとか全然なかった。……あなたは、違うんですか?」
最後の問いかけはしたくなかった。その通りだったら立ち直れない。どうして期待させたんだと、恨みさえしてしまいそうだ。
「本当に好きになってくれるなんて、思ってなかったんだ」
ようやく発された言葉は、意味のわからない内容だった。
「改めて告白された時に、僕も同じくらい好きなのかなって思ってしまったんだ。……僕からあんなことを提案したのに、最低だよね」
最初に告白した後、段階を踏もうと言ったのは彼からだった。
『僕も好きだけど、本当に同じ気持ちなのかわからないから。確かめる意味でも、少しずつ恋人らしいことをしていこう?』
結果は確かめるまでもなかった。だからこそ二人のこれからに心躍らせていたのに、現実は非情になりかけている。
「それで、どうなんですか。おれのこと、本当に……好きなんですか? キスとかしたいって思うくらい、好きでいてくれてるんですか?」
声が震える。そうだと肯定してくれ。お願いだから、おれを否定しないで。
掴まれたままだった腕をぐいと引っ張られた。否応なしに目の前の胸元に飛び込む形になる。体勢を整える間もなく、頬を包まれた。
呼吸のまともにできないキスをされている。口内を動き回る柔らかいものは……彼の、舌? それに、たまに聞こえる変な声はもしかして、自分のもの?
無理やりされているのに、呼吸もまともにできなくて苦しいのに、背筋がぞくぞくしてたまらない。気持ちいい。
「……こういうこと、したくてたまらないって思ってたよ。だから、本当は今日会いに行こうって思ってた」
こちらを見つめる瞳が熱い。気を抜いたらあっという間に染められてしまいそうなほど、鋭い光で照らしている。
「もう絶対離してあげられないよ。それでもいいの?」
返事の代わりに、初めて自分からキスをした。
「……っていう台本はどうよ? さすがに文化祭の舞台向きじゃないかなぁ」
「当たり前だろ! しかもこのネタ元ってお前とバイト先の先輩とのやつじゃねえか!」
「もちろんある程度加筆修正してるよ? 例えばべろちゅーなんて実際されてないしね。キスはされたけど」
「……それ以前に平然とネタにできるお前がこええよ……」
「でも恋愛ものとしてはなかなかいいんじゃないかなーと思うんだけどなー。書き直すのも面倒だし、いっそのことおれを女子にしちゃうか!」
「先輩見に来たらどう思うのかね。知らんけど」
#ワンライ
きっと死刑宣告
一次創作BL版深夜の真剣120分一本勝負 のお題に挑戦しました。
『やめてって言ったでしょ』『コンプレックス』です。
120分+若干オーバーで完成です。
-------
なんだよこれ。どういうことだよ。
口にしていたつもりが、出なかった。喉から先が詰まって、苦しささえ覚えた。
「どういう、ことなの……?」
目の前で彼女が青ざめている。その言葉の意味は多分違う。
「あれ、意味わからなかった?」
彼女も自分も同じ表情をしているはずだ。
彼だけが、間違い探しのように明朗な笑みを浮かべている。
「君が浮気してるんじゃないかって疑ってる相手は、俺だったってこと」
「っうそ……うそ……! だってあなた、女がいるって……!」
そう。嘘だ。こいつのことは大学を卒業してからも大切な親友のままだけど、そんな付き合いは一度もしていない。さらに言えば他の女だっていない。ずっと彼女だけを想ってきた。初めてできた恋人だなんだ。
今夜も、彼女との幸せな時間を過ごせるはずだった。週末の予定をどうするか決めて、気持ちはそこに向かっていたはずだった。
どうしていきなりこんな展開になった? 高い場所から突き落とされた?
「それが嘘。ついでに君に見せた写真も実は合成なんだよねぇ」
スマホを取り出した親友は、実に愉快そうだった。真っ赤になる彼女が滑稽に映ってしまうくらいの余裕を見せている。
「……いい加減にしろよ」
苦しさが、胸元から湧き上がる熱で溶けた。
反論もろくにできないままでいられない。彼女の誤解を解けるのは自分しかいない。
「さっきからでたらめばっか言うなよ! ふざけんな!」
胸ぐらを掴み上げても、彼の表情は変わらない。堪えようのない恐怖も生まれて、もはや彼がどんな存在なのかわからない。
「でたらめなんかじゃないよ? 俺は本当におまえを好きだし」
「好きだったらこんな馬鹿げたことしねえだろ!」
掴み上げたままの拳が細かく震える。今まであんなに仲がよかったのに。誰よりも理解者でいてくれてたのに!
「するに決まってるだろ? 俺とお前は好き合ってるんだから」
「やめろって言ってんだよその嘘を!」
「嘘じゃないって言ってるのになぁ」
再び、喉の奥が詰まった。唇が塞がれている。いやというほど覚えのある感触だ。それを今、目の前の男から——
胸ぐらを解放して、思いきり彼を突き飛ばす。認識したくないのに、確かにあった感触が容赦なく現実と突きつけてくる。
同時に、後ろの方で耳慣れた足音が遠ざかっていくのが聞こえた。慌てて振り返っても、どこかで曲がってしまったのか姿はない。なくなってしまった。
「やっと彼女もわかってくれたみたいだねぇ。いやあ、長かったよ。……本当に」
身体中に、雑多に物を詰め込まれたようだった。吐き出す手段も、浮かばない。
視界が歪む。堪えたいのに地面さえも映らなくなって、頬を、口元を押さえる指を、涙が何度もなぞっていく。本当にこれは現実なのか?
顎をすくい上げられた。ある程度戻ってきた視界のすぐ先で、親友のはずの男がぞっとするほど綺麗に笑っていた。
「大学卒業したらこれだから、本当にまいったよ。やっぱり近くで見張ってないと駄目だね。お前はとっても人気者だから」
自分の知らないところで、そもそも問題のわからない答え合わせをされている気分だった。考えないといけないのに、できない。
「あんな女、お前にふさわしいわけないだろ? 一番は俺。お前のこと絶対幸せにしてやれるって、あんなに一緒にいたのにわからなかった?」
宝物に触れるように、両方の頬を撫でられる。感情が流れ込んでくることを防げない。
「俺はお前の全部が好きだよ。誰にでも分け隔てなく優しいところも、相手をつい優先させちゃうところも、でもいざという時は前に出て守ってくれるところも、もちろん身体も全部……好き」
親指で、唇の表面をするりと撫ぜると、男の口元がさらに緩んだ。
「そういえばこのぷっくり気味の唇がコンプレックスだって言ってたっけ。俺からしたら全然そんなことないっていうか……いつも貪りたくてたまらなかったんだよ?」
そのまま迫ってくる瞳を、そのまま受け止めてしまった。ゆるく食まれて、舌であますところなく撫でられて、ついには口内に侵入されても、抵抗できなかった。
気力が、奪われていた。
「これで、お前はもう俺のものだね」
彼は、今まで見た中で最高にまぶしい笑顔を顔面に飾っていた。
死ぬまで、脳裏にこびりついて離れないような、笑顔だった。
#ワンライ
ここから紡がれる

一次創作お題ったー のお題に挑戦しました。『スタートライン』です。120分で完成。
前作に続いてのリハビリ仕様です。
---------
付き合ってから初めてのケンカをしてしまった。
内容は、今考えると本当にくだらない。例えるなら犬の方が可愛い、いいや猫の方がいいと決着のつきそうにない言い合いをしていたようなものだ。
スマホを手にしてから体感で五分ぐらい経っているのに。指は全く動きそうにない。代わりに思考回路が無駄な足掻きを続けている。
原因は間違いなく自分側にあるとわかっている。彼もさぞ驚いたことだろう。普段おとなしく言うことを聞くような人間が感情をただぶつけてきたら当たり前だ。
無意識に我慢していたのだと、今さら気づく。初めてできた恋人だし、本当に好きだから絶対に嫌われたくなかった。不満があっても飲み込んできた。きっと「いい子」を演じすぎていたのだ。
『もうちょっとわがまま言ってもいいんだぞー? 俺はもう少し言われたいなぁ』
以前そう言われたことを思い出す。冗談だと流してしまったけれど、本音だった?
両手でスマホを握りしめ、深く息を吐き出す。
悲観的になる必要なんてない。ケンカしただけで「別れよう」と切り出すような人でないのはわかっている。原因は自分にあると自覚しているのだから、早く謝るべきなんだ。
「……よし」
無駄に力の入った指で、通話ボタンを押す。コール音の無機質さがどこか怖い。いきなり空中に放り出されたようで気持ち悪い。
『もしもし』
意外に普通の声で驚いた。不機嫌さを隠しているだけとも取れる。
「……あ、あの。良くん。あの、さ」
反応はない。顔が見えないだけでこんなにも不安を煽られる。
「今日のことなんだけど。……本当に、ごめんなさい」
言いたい言葉をどうにか吐き出せた。
『うん』
そっけない返答だった。想像以上に傷つけてしまっていたとしか思えず、全身が震えそうになる。
「つい、カッとしちゃって。おれ、すごく楽しみにしてたのに行けなくなって、ついわがまま言っちゃった」
『うん』
「り、良くんの都合も考えないでごめん。仕事なら仕方ないのに、今までだってそういうことあったのに、おかしいよね」
『我慢してたからでしょ?』
恋人の声に咎めるような音はなかった。それでも深く、胸に突き刺さった。とっくに見抜かれていたと知ってしまった。
『新太(あらた)は言いたいことあっても言わないで、俺に合わせてくれてたから』
いつもの自分ならとっさに反論していた。良くんに合わせてるとかそんなんじゃない。おれの意思だ。本当にそう思っているんだよ。――それが今は、出ない。
「ご、めんなさい、ごめんなさい……おれ、ほんとに、良くんが好き、で」
涙が浮かぶなんて卑怯以外の何物でもない。目元や口元に一生懸命力を込めるが、嗚咽が強くなるばかりで無意味だった。恋人ができてから、元々弱い涙腺に拍車がかかってしまった。
『俺だって新太が好きだよ。本当に好きだ』
声が少し柔らかくなったように聞こえたのは自分の願望のせいだろうか。
『正直さ、嬉しかった。やっと新太がわがまま言ってくれたって』
――幻聴かと疑ってしまった。ケンカの原因を作った相手にかける言葉じゃない。
『何て言うんだろ……信用されてないのかな、って。俺の気持ち。俺にいつも従順なのは本心なのかなって』
電話越しに、必死に首を振る。嫌われたくない一心が、彼を傷つけていた。疑心を向けさせてしまった。
『だからほっとした。……変かもしれないけど、やっと恋人同士になれたなって思ったんだ』
想いを伝え合ってから二ヶ月は過ぎた。その間に改めて彼の人となりを知って、やっぱり好きになってよかったと思えて、けれどその嬉しさをうまく伝えられていなかった。
「……おれ、ほんとバカだ」
『な、なんだよ急に?』
「自分に置き換えて考えればよかった。良くんにわがまま言われたくらいで、嫌いになるわけないのに」
小さく吹き出したような音が聞こえた。
『そうだよ。ていうか、今までわがまま聞いててくれたろ?』
「そんなの、わがままに入らないよ」
『へえ。じゃあ、例えばどういうの?』
改めて問われると難しい。たっぷり唸り声をこぼしていると、「長すぎ」と突っ込まれてしまった。
『わがまま言い慣れてないなぁ』
「し、しょうがないでしょ。元々苦手なんだから」
『じゃあ、ひとつ例を出してやるか』
そして告げられた「わがまま」に、すぐ電話を切って身支度を整え、家を飛び出す。
たった電車二駅ぶんの距離が、倍以上に長くてもどかしかった。
#お題もの
現実につながる夢

一次創作お題ったー のお題に挑戦しました。『こんな夢を見た。』です。120分+若干オーバーで完成。
久しぶりのお題SSです。思いっきりリハビリ仕様です。。
---------
普段から交流のある人が夢に出てきて、しかも内容を大体覚えていると何だか気になってしまう。それから好意に変わる。改めて容姿やら性格やらを観察するようになって、意外な面を発見したりこういう仕草がツボだと知るからだろう。
多分珍しいことではないと思う。……相手が異性だったら。
(多様性がどうの、っていう時代なのはわかってるよ?)
心の中で自身に向かって言い訳をするのも今日だけで二桁はいっている。ちゃんと数えていないけれど体感的にはそれくらいいっている。
目の前にある唐揚げをひとかじりしながら視線の端で捕らえようとしているのに気づいて、無理やりテーブルの上の小皿に戻す。これも何度繰り返しただろう。
大学のサークルつながりで仲良くなった同年代たちと笑い合っている声が右耳をがんがんに打ってくる。近所迷惑になりそうな声量ではないし距離だって四人分くらい離れているのにそう聞こえるのは、己の精神状態のせいか。
ふと視線を感じた気がしたが、反応はできなかった。もしあいつだったらどうすればいいのかわからない。すでに二回ぶつかっているから余計に混乱する。
ああ、酒が飲めれば逃げられそうなのに。あと一年がもどかしい。
「どうしたの大ちゃん、元気ないじゃん?」
賑やかし担当が多いメンツの中でも比較的おとなしい女子――安田が気遣うように話しかけてきた。そういえば「大ちゃん」という愛称もあいつ発祥ですっかり定着してしまった。
「そうかなー?」
そんなに顔に出ていただろうか。まあ、わかりやすいねと言われるのが多いのは認める。
「だって、いつもなら章くんとバカやって楽しんでるじゃない。今日はなんか違うなーって」
さすがに露骨だったらしい。
こっちだって夢のことがなければとっくにそうしている。それとなく二人きりを避けたり遊びを泣く泣く断ったりもしない。今日は人数が多いからそれほど気にしなくていいと思ったから参加したのに、このざまだ。
すべては約一ヶ月前に見た夢のせいなんだ。忘れたいのに忘れられないせいなんだ。
「んー、具合悪いのかもしんないわ。俺、先に帰ろうかな」
待ちに待った夏休みが始まってから最初の集まりだったのに、本当に残念でもったいない。けれど、粘ってもこれ以上気分は変わってくれない。店に入ってからずっとこの調子だから断言できる。
「……本当に具合悪いだけ?」
急に声をひそめてきた彼女を怪訝そうに見返すと、なぜか隣に移動してきた。嫌な予感がするのはなぜなのか。
「な、なんだよ。口説くつもりか?」
「違うから。……本当は章ちゃんとケンカでもしたんじゃないの?」
どうしてそんな質問をされないといけない? 戸惑っているとさらに言葉を重ねられる。
「どうしたんだろうって言ってる人もいるんだよ」
「な、なんでそんなこと」
「当たり前でしょ。あんなに仲いいのに急によそよそしくなったら怪しむって」
予想以上に筒抜け状態だった。このぶんだと彼も同様に感じているかもしれない。もしかしてさっきの視線もそういうことなのでは……。
「き、気にしすぎだって。ほんと何でもないんだから。ケンカってガキじゃあるまいし」
「年齢関係ないから。それより、ケンカじゃないって言葉信じてもいいんだね?」
「だから違うって。つか、やたらつっかかってくんじゃん」
誰かの差し金かと疑いたくなるしつこさだった。だが安田からは返答をもらえないどころかそそくさと立ち去っていってしまった。残されたのはどうしようもないモヤモヤとした気持ち悪さだけ。
(本当に具合悪くなってきた……)
あいつも安田同様に怪しんでいると想像したら逃げたくなった。仮に問い詰められたら言い逃れできる自信がない。というか言いたくない。
「悪い、先に帰るわ」
空気を敢えて無視して金をテーブルに置き、足早にその場を後にする。途中退場を咎めるような連中ではないが戸惑うような声はちらほらと聞こえた。
夜風の生ぬるさに顔をしかめる。こんな時はいっそ凍えそうな温度でお願いしたい。
どうしたら忘れられる? というより、どうしてここまで気にしないといけない? あの夢は一ヶ月も前の、幻みたいなものなのに。
大学で初めて見つけた、気の合う友人だった。最初は素直で単純なだけかと思っていたが、実は真面目な部分も持ち合わせていたり、実は尻込みするところのある自分を引っ張ってくれる力強さもあったり、中学生かと突っ込みたくなるような無邪気な笑顔がどこか可愛いと思ったり……。
(だからどうして可愛いとか考えてんだ俺は!)
水風呂にでも飛び込みたい。喝を入れてもらいたい。
「大ちゃん」
いつの間にか止まっていた足を動かそうとした時だった。
一番聞きたくない声が、背後から響いた。
振り向きたくない。露骨でも、違和感だらけと思われても、どんな顔をすればいいのかわからない。
「大ちゃん。オレも一緒に帰るよ」
許可を求めてこなかった。つまり、逃がさないという意思表示。
反射的に駆け出していた。電車になんて乗れるわけがない。でも行き先はわからない。
「まて、ってば!」
逃走は予想通り失敗に終わった。無我夢中だったからいつの間にか住宅地に迷い込んでいたらしく、目印は木製のベンチが二つ並べられた、屋根付きの休憩スペースぐらいしかなかった。
「……花岡。もう、逃げないから。だから腕、離してくれ」
花岡はそろりと掴んでいた手の力を抜いた。支えを失ったように、ベンチに腰掛ける。隣からどこか荒々しい音が響いた。
屋根があってよかった。電灯はあれど、互いの顔ははっきり見えない。
「……オレ、大介になんかした?」
沈黙は長く続かなかった。絞り出すような声には苛立ちよりも困惑の方が大きいように聞こえた。
「してないよ」
嘘じゃない。現実のお前は何も悪くない。すべては自分一人で不格好に踊っているだけに過ぎない。
「なら、逃げたのはなんで? 避けてるのもなんでだよ?」
当たり前の疑問だった。逆の立場なら同じ行動を取る。そこまでわかっていながら、理由を告げるのが……馬鹿らしいけれど正直、怖い。
親友に近い関係といえど、笑ってすませてくれないんじゃないか。本気で引かれたら今まで通りでいられなくなる。
思わず頭を左右に振った。全く無駄な言い訳だ。
一ヶ月も経っていながら「単なる夢」だと切り捨てられなかった時点で通用しない。うすうす、気づいていた。
「大介……?」
「……夢を、見たんだよ。お前が出てくる夢」
肩にある感触が少し震えた。次の瞬間にはきっと離れていく、そう想像するだけで喉の奥が詰まりそうになる。
けれど、もう年貢の納め時だ。
「どんな夢だと思う? 俺とお前、恋人同士だったんだぜ」
意味が飲み込めない。そんな問い返しだった。
「抱きしめて、キスだってしてた。それ以上の、ことだって、してた」
ベッドの上に組み敷いた夢の中の花岡は、恍惚とした笑みを浮かべてあらゆる行為を受け入れていた。そんな彼がたまらなく愛おしくて、また火がつく。まさに「溺れる」状態。
――オレ、お前がたまらなく好きだよ。好きすぎて、苦しい。
熱に浮かれた花岡に応えた瞬間、薄い光が視界を埋めた。
ただ呆然とするしかなかった。驚きこそすれ、さほど嫌悪感を抱いていない自分にも呆然とするしかなかった。
さらに一ヶ月かけて、夢と現実の想いがイコールになるなんて思わなかった。
「な? 普通に引くだろ? 俺もなんかまともにお前の顔見れなくて変に避けちまってたんだよ」
これで仕方なしでも納得してくれれば御の字、呆れたように笑ってくれたら上出来だ。
「こんな理由で、しかも気持ち悪くて、ほんと悪い。俺もさ、何でそんな夢見たのかわかんないんだよ」
沈黙が怖い。何を考えているのだろう。本心を悟られていたらどうしよう。一番大事にしたい関係なのに壊れたらどうしよう。
「大介」
短く名を呼ばれて、肩をぐいと押された。否応なしに、顔ごと花岡に向き直る形になる。年齢より上に見られることがある端正な顔がうっすらと浮かび上がっていた。
瞬きを一度する間に、口元に熱が生まれた。
正解の反応がわからない。ただ馬鹿みたいに再び目の前に現れた無表情の花岡を見つめるしかできない。
「全く、どんな告白だよ。斜め上すぎるわ」
叱責に聞こえない叱責に、感情のこもらない謝罪がこぼれる。それどころじゃない。今起こった出来事をどう処理すべきかわからない。
「そんな夢見たって言われて、一ヶ月もオレの顔まともに見れないとか言われたらさ、期待するしかないじゃん」
期待、という二文字が大きく響いた。期待するしかない、漫画やドラマなどでよく聞くワード。
「好き、なのか?」
まるで他人事のような心地だった。小さな苦笑が返ってくる。
「じゃなかったらキスなんてしないし、お前が見たような夢も見たりしないよ」
軽く引き寄せられて、耳元にその夢の内容を吹き込まれる。次第にじっとしているのが苦しくなってきて、思わず身を捩ってしまった。素直に解放してくれた花岡は、今度は楽しそうな笑い声をこぼす。
頭の回転速度が全然足りない。ここ一ヶ月の出来事をいきなり全否定されたような気さえしてくる。
「……お前、実は嘘つくのうまいだろ」
こんな物言いはどうなんだと思いながらも、大なり小なり反撃したくてたまらなかった。
「俺はみっともない態度取っちまったのに、お前いつも通りすぎただろ」
「そりゃそうだよ。だって大好きなお前に絶対嫌われたくなかったんだから」
密かな努力を褒めてほしい。そう言い切った花岡に再び抱きしめられた。
――夢の中と違って、自分はどうやら翻弄される側らしい。
#お題もの
二人をつなぐミモザ
「一次創作BL版深夜の真剣120分一本勝負」 さんのお題に挑戦しました。
使用お題は『イラスト課題(下記ポストURLをクリック)』です。
高校生のときに好きになった彼・高梨を忘れられず、同窓会で絶対に告白すると決めて臨んだ主人公・高崎のお話。
https://x.com/sousakubl_ippon/status/878...
-----------
『写真、撮ってもいい?』
『いいよ。……でも、撮るならこの場所でいいかな?』
今でも考える。
どうして高梨は、わざわざミモザを背景に選んだのだろう。
「久しぶり。元気だったか?」
「うん。そっちも相変わらず元気そうだね。安心した」
「相変わらずって、なーんかバカにされてる気分」
「そんなんじゃないってば」
頬をそっとなぞるような控えめな声と少し眉毛が垂れる特徴的な笑顔に、あの頃の雰囲気があっという間に戻る。
高校を卒業してから初めての同窓会に呼ばれて、まず確認したのは高梨の出欠だった。
どうしても逢いたかった。逢って、だめでもいい。最悪縁が切れてしまってもいい。捨てられなかった想いを伝えたかった。
「どうしたの? おれの顔、なにかついてる?」
「いや、ごめんごめん。本当に久しぶりだなーって感慨にふけってただけ」
気づいたら、ぼうっと高梨を見つめていたようだ。とっさの嘘はうまくいったらしい。
「お前ー、ますますキレーな顔しやがってずるいぞ! どうせ大学でもモテモテなんだろ、ん?」
自分の左隣にいた、今も付き合いが続いている友人の冗談が飛んでくる。思いがけず訊きたかった質問をしてくれて、内心で思いきり親指を立てる。
「えっ、そんなことないよ。ほら、おれって大人しすぎるから目立たないし」
彼は謙遜しているが、知っている。おとなしくても分け隔てなく優しいし、そばにいると落ち着くから、実は相当女子からの人気は高かった。今も隙あらば自分のポジションを奪い、少しでも点数を稼ぎたいと狙っている複数の目をびしばし感じている。
だからこそ彼を壁際に座らせ、たったひとつの隣を奪わせてもらったのだが。空気なんて読んでやらない。
「二人はどうなの? 二人こそできててもおかしくないじゃない」
「ま、俺は……な。もしかしたらできるかもしれん」
その話に食いついたのは周りの面々だった。あっという間に餌食にされた友人に今度はハンカチを振ってやる。
「高崎は? ……いるの?」
なぜか怯えたような表情になる高梨に慌てて首を振る。
「いるわけないだろ? 毎日忙しくて、そんな余裕もないっていうか」
忙しいのだけは、嘘じゃない。
高梨を忘れた日はなかった。クラスが一緒になって、後ろの席に座っていた彼をひと目見た瞬間に「好き」の感情を抱いてから、決して暴かれてはならない秘密の片想いを続けてきた。
でもそれも、今日で終わる。
「でも、好きな人はいるんじゃないの?」
こちらに目線はくれず、高梨は呟くように問いかけてくる。
一瞬、内心を覗かれたのかと思った。そういえば、恋愛の話をするのは初めてかもしれない。
なぜか、嘘をついてはいけない気がした。かといって突っ込まれてもうまく誤魔化せる自信はない。
「おれはね……いるよ」
耳から、周りの喧騒が消える。視線の先にいるのは表情の読めない、いや押し殺しているように見える高梨のまっすぐな双眸だけ。
中性的で大人しそうに見えて、自我を曲げない意志の強さが一番に表れるこの瞳が好きだ。
彼は今、なにを胸に抱いているのだろう。なにを、伝えたいのだろう。
「高崎が撮ってくれたおれの写真、まだ持ってる?」
酒も手伝ってか、ふわふわとした頭で反応が少し遅れた。ポケットに入れていたスマートフォンからアルバムを起動して、お気に入りにしていた写真を拡大する。高梨だけの目に触れさせたくて、不自然にならないよう手首に角度をつける。
「……懐かしいね」
覗き込んだ高梨は微笑む。ただ嬉しいだけじゃない、どこか既視感を覚える、若かりし頃の失敗を振り返るような雰囲気と似ていた。
離れ離れになる前に、写真という形だけでも高梨を手元に残しておきたかった。下手な言い訳でも彼は快く許可をくれて、学校の花壇にあったミモザの花の前で微笑みをくれた。
端末を握る手に一瞬、力がこもる。既視感はそれだ。その時の笑みと、そっくりなんだ。
「おれ、ずっと後悔してたんだ。ちゃんと、言えばよかったって。怖いからって、回りくどいことしなきゃよかったって」
心音が強くなり、間隔も狭まる。今の自分と似ているのも偶然、なのか?
「あの、」
続きは、幹事の終了を知らせる主催者の声にかき消された。仕方なく帰り支度を始めるが、きっと高梨はわかってくれている。確証はないけれど、そんな気がした。
同窓会が高校から比較的近い場所で開催されたおかげで、よく道草をした公園に行くことができた。
さほど広くないから遊具も少なく、子供の遊ぶ姿はあまり見かけなかったが、それがかえって寄り道しやすかった。
「……高崎、手、いつまで掴んでるの」
「ごっ、ごめん」
ようやく頭が少し冷えて、強引に繋いでしまった手を解放した。恥ずかしさで逃げ出したい気持ちを懸命に抑え込む。
二次会の誘いを断っただけでなく、勢いのままに高梨を連れ出してしまった。きっと彼を狙っていた女子からは非難轟々の嵐で、明日あたり誰かから文句混じりのレポートでも届くだろう。
「でも、ありがと。おれ、二人で話したかったらちょうどよかった」
照れの混じった笑みが素直に可愛いと思えて、だいぶ理性が緩んでいることを悟る。こういうとき、中性的な容貌はある意味目に毒だ。
「さっきの、続きだよね」
一度ためらうように視線を泳がせて、改めて高梨はこちらを見上げる。
「その前に、さ。ちゃんと教えてほしいんだ。高崎、好きな人……いるの?」
彼の誠実さに、今度は逃げず正面から向き合わなければならない。
「いるよ。高校のときから、ずっといる」
ひとつ頷くと、再度撮った写真の表示をお願いしてきた。
「ミモザの花言葉って、知ってる?」
写真を差す指はよく見ると震えていた。戸惑いつつ首を振ると、調べるよう促される。
微妙な緊張感が二人の間に流れている。早く結果を表示してくれと、祈るような心地で画面が切り替わるのを待った。
「出た! えっと、花言葉は……」
反射的に言葉を読み上げて……ある内容で、止まる。
――秘密の、愛。
改めて視線を向けた先の高梨は、薄闇でもわかるほどに瞳を潤ませていた。思わず頬に手を伸ばすと、微熱でもあるのかと錯覚しそうな熱さが返ってくる。
「黄色いから、秘密の恋って言葉も、あるんだよ」
夢の中にいるような心地だった。端末をポケットに突っ込んで、もう片方の手も頬に触れる。
高梨の両手が自分の頬に触れる。少しひんやりとした感触が、夢見心地を覚ましてくれる。もうごまかさなくていいのだと、素直になっていいのだと伝えてくる。
「……先に、言ってくれてたんだな」
高梨の前では格好つけたいのに、高校のときからどうにもうまくいかない。
「俺、ちゃんと言うつもりだったんだ。ずっと好きで、忘れられなくて、でも勇気が出なくて……絶対今日、言おうって決めてきたんだ」
泣きそうになる。その顔だけは見られたくなくて強引に腕の中へおさめるも、背中に回された感触が、容赦なしに涙腺を刺激してきた。
「おれも同じだよ。言ったでしょ? 回りくどいことしなきゃよかったって」
背中を向けていたのは、互いに一緒だった。
でも、この写真が二人を繋ぎとめて、ひとつにしてくれたんだ。
#ワンライ
星を散りばめて

「一次創作BL版深夜の真剣120分一本勝負」 さんのお題に挑戦しました。
使用お題は『光』です。
年上×年下(どちらも大人)な組み合わせです。頑張って甘くしたつもりですw
-------
俺の恋人は海が大好きだ。
ただ、観光地と化しているほど人の多い海ではなく、プライベートビーチのような物静かな海が好きらしい。俺も人混みは得意ではないから、今回の宿、もといコテージはあっさりと決まった。
「いやー、ほんと綺麗な海だなー!」
さっきから彼は似たような感想を繰り返している。検索していたらたまたま見つけたコテージだったが、車通りも人影もほとんどない、おまけにメインの海はエメラルドの宝石をそのまま溶かしたような、まさに彼が喜ぶ類のものだったから、まさに完璧な選択だったわけだ。
「ねえ、俺ばっかりはしゃいでるけど、そこに座ったまんまでつまんなくないの?」
彼は砂浜に座ってただ海を眺めたり、趣味である写真を撮ったりとなかなかに忙しない。俺はといえば、最初こそ彼に付き合っていたものの、楽しそうな背中をひたすら眺めてはコテージに引っ込んで、溜まっていた本をのんびり消化していた。
「別につまらなくなんかないよ。……でも、そうだな」
まるで同棲しているように、気張らず、恋人らしいことをしないと、と気負いもせず、ただのんびり休暇を過ごす。旅行前に決めたルールだった。
久しぶりに重なった休みというのもあって、特に彼の生き生きとした姿を素直に堪能したいという気持ちもあった。
「ん、やっぱり一緒になにかする?」
目の前に立った俺を水面で輝く太陽のような瞳で見上げる彼に、まずは触れるだけのキスを落とす。
「そろそろ、俺にも構ってほしいかな」
唇の表面を軽く喰んで、薄く開いた隙間に舌を差し込む。陽の下に晒され続けたせいか、いつもより熱い口内を丹念になぞっていく。
耳をくすぐるのは、穏やかな波音に不釣り合いな、舌、唾液を絡ませ合う淫らにあふれた音、互いの乱れた呼吸だけ。
人気のないという事実が、普段以上に大胆な気持ちを生み出す。それは彼も同様のようで、白いTシャツの裾から手のひらを滑り込ませても、甘さに震える声をこぼすだけで拒否はしてこない。
「……いいんだ? まだ日中で、こんなオープンな場所なのに」
意地悪をされていると自覚しているらしく、わずかに頬を膨らませて欲情に濡れた瞳を釣り上げる。
「あんた、ほんとこういうときは性格悪いよね。オヤジだ」
「心外だな。五歳しか変わらないのに」
「五歳は結構ちが、っん!」
小さく笑いながら、すでに尖っている箇所を爪先でなぞる。あっという間に目元を緩ませた彼が可愛くて片方も強めに弄ってやると、もはや堪らえようともしない悲鳴が鼓膜を震わせた。
「コテージまで、戻る?」
耳元で囁くように問いかける。吐息がくすぐったいのか、首をすくませながらゆるゆると振る。
「我慢できないんだ」
「いいから! ……もう、意地悪しないで」
肩口に歯を立てられた瞬間、年上の余裕はいとも簡単に消え去った。
+ + + +
「あーあ、結局こういうパターンか」
「いいじゃないか。俺、実は結構我慢してたんだし」
「えっ、それなら早く言ってよ!」
ベッドから身を起こした彼は、こちらの変わらない笑顔を見て冗談だと悟ったらしく、溜め息をついてもそもそと元の位置に戻っていった。
「まったくの嘘ってわけでもないよ。ああしてのんびり過ごして、楽しそうな君を見ていたかったのも本当だから」
「それなら、いいけど……」
あれからコテージに戻っても熱は冷めず、シャワーを簡単に浴びてからずっと、ベッドの上で過ごしてしまった。外はとっくに薄闇で塗り替えられ、小さな輝きと半分に欠けた夜の太陽が、外灯の代わりにコテージを照らしている。
「明日は岬のある方に行ってみよう。ちょっと距離があるけど、高い場所から見る海もなかなかいいからね」
すぐに笑顔を取り戻した彼は素直に頷く。
明後日はなにをしよう? 幸せなことに明々後日も、その次の日もある。まだ、彼をたくさん独占できる。
けれど……ずっと、ではない。
「どうしたんだ?」
本当に、感情の変化に敏い恋人だ。それとも、それだけ俺がわかりやすいのか。嘘をつくのは苦手ではないのに、思ったほど余裕がないのかもしれない。
黙って肩を抱き寄せて、恐る恐る口を開く。
本来なら、旅行の最終日に打ち明ける予定だった。
「ずっと、考えていたことがあるんだ」
彼は何も言わない。かえって、俺のタイミングで続きを紡げばいいと言われているようで、少しだけ気が楽になる。
「俺と、一緒に住まないか?」
俺にとっての同棲は、「これから先もずっと一緒にいたい」という、いわば結婚と同等の意味を秘めていた。
彼も、それを知っている。
ずっと迷っていた。隣で笑ってくれている彼は、未来でもそれを見せ続けてくれるのかと。俺はとうに覚悟を決めていたけれど、彼は違うかもしれないと少しでも考えると、なかなか口に出せないでいた。
ようやく、なけなしの勇気を振り絞れたのだ。
あとは彼を信じるしかない。俺に向けてくれる笑顔の輝きに、すべてを委ねるしかできない。
「まったくさ、遅いんだよ」
虚空に響いたのは、呆れと愉悦の混じった声。
次いで俺を見下ろす瞳は、逆光でもわかるほどに星を散りばめたような輝きで満ちていた。
#ワンライ
お前だけに甘えた結果の現在(いま)なのか
「一次創作BL版深夜の真剣120分一本勝負」 さんのお題に挑戦しました。
使用お題は『アイスクリーム』『背比べ』です。
一応リーマンものです。暗くなってしまいました……。
--------
定期的に冷凍庫を開けるクセがついてしまった。
あいつは、俺から見たら異常なほどの果汁入りアイスクリームを愛する男で、規定の数がストックされていないと不機嫌になるのだ。
「やべ、残り三つじゃん」
ひどいときは一日に十個も消費する。だから互いに確認を怠らず、五つ以下になっていたら補充しようというルールを設けていた。
「なに買うかな……オレンジ味と、グレープ味……」
スマートフォンのメモアプリを立ち上げて、購入リストを作っていく。四つまで埋めたところで、指の動きを止めた。
「……俺の好きな味ばっか」
気づけば俺も果汁アイスを好むようになっていた。柑橘類のあの爽やかな酸っぱさは、一度ハマると季節関係なく定期的に食べたくなる。
ただ、あいつは果汁なら大体なんでも好きなクチだから、偏っていると不機嫌の原因となってしまう。
「一番食うんだし好みもうるさいんだから、いい加減自分だけで買うようにすればいいのに」
メモを破棄して、ソファに身をだらしなく預ける。スマートフォンのカレンダーをぼんやり眺めながら、同棲を始めた五年前を思い出す。
あの冷凍庫は、わざわざ単体で購入したものだった。まだ互いに大学生だったから、サイズと金額のバランスをこれでもかというくらい相談しあい考え抜いた末の、いわば思い出の品だった。ある意味受験や就職活動のときより真剣だったかもしれない。
『こんなん、ちゃんと付き合ってくれんのお前ぐらいだわ』
スポーツ好きにふさわしい短く整えられた髪型のせいか、妙に爽やかな笑顔であいつがそう言っていたのを思い出す。
「そんなの、俺だって言いたかったさ。俺みたいなやつに付き合ってくれんの、お前だけだって」
物心ついたときには同性しか好きになれない体質だった。大学に入って初めてあいつと出会って、友人として長く過ごすうちにそれ以上の感情を向けてしまっていた。
自覚したら気持ちを押し殺しておけない困ったこの性格は、あいつに対しても例外なく発揮された。
『……え、お前が、オレ、を?』
『悪い。……気持ち悪いだろ、ほんとごめん。困らせるつもりはなかったんだけど』
『お、おい。待てよ』
『これで何回も失敗してんのにマジ学習能力ねえな俺。……今までありがとう。じゃあ』
『だから待てって!』
そのとき腕を掴まれた力は、今でも昨日のことのように思い出せる。あんなふうに引き止められたことは一度もなかった。
さらに、「今すぐ返事できないから少し時間がほしい」と返され、社交辞令かと思っていたら本当に返事をくれて、それが断りでなかったことにもっと驚いた。
『ちゃんと考えたんだよ。お前と離れたくないって思ってるのは友人だからなのか、そうじゃなかったら恋人とするようなことをしたいほどなのかって。
それで……したいって、思った。多分気づいてなかっただけで、オレもお前が好きだったんだ』
根は真面目な、あいつらしい返事だった。それが思わず泣いてしまうくらいに嬉しくて嬉しくて、夢なんじゃないかと疑ったくらいだった。
抱きしめてぎこちないキスをくれたのに、次の日に同じ講義で再会するまでは夢と現実の区別が本当につかなかった。
――だから、無意識に甘えてしまっていたのかもしれない。
この関係はずっと変わらない。
なにがあっても、隣を見ればあいつの顔がいつもある。
俺とあいつは同じ想いを抱き合っているんだ。
「……アイス、買いに行くか」
テーブルの上に置きっぱなしになっていた長財布をポケットにねじ込んで、ゆらりと立ち上がる。あいつが特にうまいと繰り返していた商品を中心に揃えておこう。
あいつが突然いなくなって、二度目の夏がやって来ようとしていた。
#ワンライ
夢と誰か言ってくれ

「一次創作BL版深夜の真剣60分一本勝負」 さんのお題に挑戦しました。
使用お題は『音』『真紅』です。
主人公の独白メイン。暗いです。
--------
目の前が赤く染まる。呆然と、その赤を瞳に映していた。
生と死の狭間へと誘う音がだんだんと近づき、目の前で急停止する。
大丈夫ですか! 意識はありますか!
持ち上げるぞ!
まるで、自分の身体がこの場に存在していないかのようだった。
もしかすると夢かもしれない。だからこんなに現実感がないんだ。そうに違いない。
「すみません、お知り合いの方ですか?」
目の前ではっきりと声をかけられ、薄れていた意識が無理やり戻る。頷いた、というよりも項垂れた。間違いなく現実だと、宣告されたようなものだから。
「お前に、俺のなにがわかるってんだよ……!」
些細なきっかけで始まった喧嘩だった。このところ残業続きで疲れがたまっていて、それでも彼とのデートは数日前から楽しみにしていた。
行きつけのバーでの出会いがきっかけで付き合うようになった二歳年下の彼は、年下とは思えないほどしっかりしていて、自分をよく見てくれている、ただの恋人では括れない大事なひとだった。
その日のデートは彼からの提案だった。自分のためと確信できるのは、行く場所が好きなところだったからだ。
心から楽しんでいた。恋人の絶えない笑顔も胸に染み渡る思いだった。
それを、夕飯のときに入れたアルコールのせいで余計な口を滑らせ、口論したまま帰り道を進むはめになってしまった。
一言謝れば済む話だ――そう頭のどこかではわかっていたのに、意地が先行して過剰な内容ばかりが飛び出す。
「いいからもうほっといてくれ! お前も俺に付き合うのはうんざりだろ!?」
「っお前は! そういうところが無駄に頑固だからいらつくんだよ!」
優しい彼もいい加減我慢の限界に来たのか、背後から荒げた声をぶつけてきた。
ハンドルを切り損ねたのか、先頭にいたからよくはわからない。
空気を切り裂くような音が聞こえて、振り返ると白線を乗り越えた車のそばに、恋人が倒れていた。
自分の周りだけが照らされた待合スペースで、光と闇が入り混じった床をただ見つめる。
酒を飲まなければ。夕方で解散していれば。そもそも出かけなければ。
後悔ばかりが今さら浮かんで、胸を、頭を圧迫しにかかる。もうひとりの自分が激しく責め立てている。
喧嘩なんて、今までも何度かあった。そのたびにどちらかが折れて、元通りのふたりになっていた。
それなのに今はどうして、ここに謝りたい相手がいない? どうして、生死をさまよい、祈る事態までいってしまった?
失う未来なんて考えられない。たとえ喧嘩しても、誰よりも彼が大事なんだ。彼のいない日々に耐えられる自信なんてこれっぽっちもないんだ。
組んだ手のひら同士を固く、痛みを感じても握りしめる。この強さは、彼への祈りの強さ。
目を閉じればいろんな表情の彼が目の前に現れては消える。男にしては大きめの瞳で、まっすぐこちらを見つめ返してくれる視線の強さが好きだ。
言葉にせずとも伝わってくる想いに、込められる想いをすべて返せば、何よりも幸せそうな表情を浮かべる瞬間が好きだ。
どうか、その時間を再び味わわせてくれ。
#ワンライ
どうしようもない馬鹿のスイッチを押すとどうなるか

「一次創作BL版深夜の真剣120分一本勝負」 さんのお題に挑戦しました。
使用お題は『偶然か必然か』『大好物』です。
大学生もの。攻めが頑張って口説き落とそうとしてくるのを、いつも通りかわしたはずだった。
----------
「ねえ、僕が君の好物を当てられたのってすごくない? 本当に偶然なんだよ。これってもう愛の力っていうか、惹かれ合うものがあるっていう証じゃない?」
「はいはいそうですね」
「なんで投げやりなんだよ! あ、そうか。自分が負けたって認めたくないってことか! うんうん、君はプライド高いもんね。そんなところも僕は大好きだけど」
どうも盛大に勘違いをしているようなので、小説に落としていた視線を、ようやく目の前でぎゃんぎゃんとうるさい男に向けてやる。これから残念な種明かしをされるとも知らず、この男は俺が反応を示したことに素直な喜びを向けている。
「残念だけど、お前がこの小説を買ってきたことで証明されたのは、俺ではなくお前の敗北だ」
日本語が理解できない。そんな表情を返してきたので栞をはさんで小説を閉じた。やはりきちんと説明する必要があるらしい。
「俺は、この小説が好きだということをあるひとりの友人に『だけ』話した」
まだ彼は呆然としている。頭の中で己が取った行動を反芻していると言ったほうが正しいかもしれない。
「俺が、周りをちょろちょろしているお前に備えて、自分の情報を一切他に漏らしていないのは知っているな? だから『最初で最後のお願い』と、勝負を持ちかけられたときに思いついたのがこの方法だったのさ」
二週間の間に、今現在の俺の大好物を当てる。それを「己の力だけで」解き明かせたら、「付き合いたい」という彼の願いを叶えてやる。
相手にとってはただ分が悪いだけの条件をつけても承諾したのは、まぎれもないこの男だった。
彼がどれだけの頭脳を持ち合わせているか、高校二年の頃に知り合ってから大学生となった現在まで付きまとわれている以上、いやでも把握している。自力で割り出せるはずがないとはじめからわかっていた。
全くの予定通りすぎて、浮かんだのは喜びより呆れだった。
「自ら負け戦をするとは、お前も相当のバカだな」
ため息をついて、再び小説に視線を落とす。こちらとしては、タダでこの本を手に入れられて棚からぼたもち状態と同等だった。ハードカバーだから、学生の身には懐が少々痛む金額なのだ。
すっかりおとなしくなった男に小さく名前を呼ばれるが、生返事だけを返す。早く物語の世界に浸りたい。
瞬間、頭が持ち上がるような、不思議な浮遊感が走った。
「っお、ま……っ、ん!」
唇を塞ぐ感触を必死に引き剥がそうと、両腕にありったけの力を込めるがびくともしない。そういえば彼は、高校時代も今も運動部に所属している。体育ぐらいでしか運動していない俺との筋力の差は、認めたくないが歴然だった。
口内でうごめくこれは、舌だ。恋人になることすら許していないのにこんなキスをあっさり許してしまうなんて、失態以外のなにものでもない。
――告白だけは掃いて捨てるほどしてきても、強引な手段に出ることは一度たりとて、なかったのに。
「ふ、ぁ……は……」
耳を塞ぎたくなるような声だけが漏れてしまう。心なしか、背中にぞわりとした感覚も生まれている気がする。
それでも、角度を変えながら欲望をぶつけるようなキスを、何度も彼は続けた。
「……僕、諦めないから」
ようやく唇を解放するなり、彼は囁くように告げた。同時に切れた細い糸に、熱が顔に収束するのを感じる。
身体が動かない。すべて生気を吸い取られてしまったように、情けなく真顔の彼を見つめるしかできない。
「絶対、君を手に入れてみせる。最初で最後のお願いは、撤回する」
瞳の奥に、赤い炎が見えた気がした。こんな気迫も、今まで一度も見たことがない。
頬をひと撫でしてから、彼は静かに立ち去った。もともと人気がほとんどない大学校舎の奥にあるベンチに、本当の静寂が訪れる。
「……ありえない、こんなの」
はじめてあの男にペースを乱され、心臓が無駄に早鐘を、打っているなんて。
胸の上の服を、力任せに掴むしかできなかった。
#ワンライ
俺の頭の調子はもっとおかしい

ちょっと二次創作みたいなノリになってしまいましたw
風邪を引いた主人公のもとに見舞いにやってきた親友は、どこか色っぽいと感じてしまう雰囲気を普段から持っていた。
それは彼を好きと思っているから? いや、そんなはずはない。友達としてしか見ていないはずなんだ。
----------------
久しぶりに風邪を引いた。
前日は中学生以来の三十八度まで熱があがってしまったが、なんとか微熱より強い程度まで下がってくれた。うまくいけば明日には復活できるかもしれない。
一人きりは寂しくて嫌いというタイプではないのに、風邪特有のマジックか心細さを感じてしまう。本当に若干だが。
『ちゃんとおとなしく寝てろよ? お前、ただでさえ落ち着いてらんないタイプなんだから』
休みのメッセージを送った友人からの返信を思い出す。
大学の入学式で出会ってから一番仲がよくて気の合う、いわゆる「親友」という間柄だ。
昨日は見舞いの打診をされたが、風邪がうつると大変だからとお断りのメッセージを送っていた。それでも彼のことだから、抜き打ちでやってくる可能性が高い。
意外と面倒見のいいやつだから、黙って見過ごせないとかそういうことなのだろう。だとしても彼女じゃあるまいに、放っておいても問題ないのに。
「彼女がいたらお願いしちゃうかもだけどな〜」
看護婦のようにやわらかな笑顔を向けられながら、甲斐甲斐しく世話をしてもらいたい。
『どうだ? 身体、少しはさっぱりしたか?』
『ああ。拭いてもらっちゃってほんと悪い。めんどくさかったろ?』
『なに言ってんだよ。付き合ってるんだからこれくらい当たり前だって』
『そ、そっか。そう、だよな』
『全く、そんな風に照れられたら困るだろ……手、出せないのに』
「ってなんでアイツ思い浮かべてんだ俺はよー!」
かすれてパワーのない叫びでもせざるを得なかった。照れた親友の顔を思い出してひいい、と情けない悲鳴ももれる。
ダメだ、予想以上に頭をやられている。彼「女」がいいのにどうして彼「氏」なんだそこで!
……確かに、あの親友は同性の目から見ても変に色っぽい雰囲気を醸し出すことがあるが、全くもって関係ない。関係ないはずなんだ。
「……んあ? インターホン?」
もう一度寝直すしかないと布団をかぶって、意識が半分落ちかかったときだった。
仕方ない。重い身体を起こしてゆるゆると玄関に向かう。
「よ、今日こそ見舞いに来てやったぞー」
ついさっき妄想していたことを思い出して、固まってしまう。
なぜか、見慣れたはずの整った顔が妙にきらきらしている。今まで一度もそんな現象にあったことはない。まさか妄想のせい?
「おい、どうした? あ、まだ熱高いか……それなら悪い」
「あ、い、いや。今はそこまで高くないよ。大丈夫」
彼はほっとしたように笑う。……やっぱり、色っぽい。いや、むしろ可愛い?
「あ、上がってくか? お前がいいならかまわねーよ」
慌てた拍子に、遊びに来たときのようなノリで口走ってしまう。自ら追い込むような真似をしてどうするんだ!
「おー、もともとそのつもりだったし。んじゃ、ちょっと上がらせてもらうわ」
内心混乱する自分をよそに、彼はリビングにずんずんと進んでいく。後を追うと、手にぶら下げていた大きめのビニール袋からヨーグルトやゼリー、ペットボトルを取り出して冷蔵庫に入れてくれていた。
「ほら、おとなしく寝てろって」
こちらの視線を飲み物が欲しいという訴えと勘違いしたのか、食器棚にあるコップとしまったばかりのペットボトルを両手に、こちらに向かってくる。
まるでこの家のもうひとりの主であるような、実に無駄のない動きだった。
「他に欲しいものあるか?」
「あ、いや、大丈夫。つか、いろいろ買ってきてもらって悪いな。ありがとう」
「冷蔵庫の中スッカスカでびっくりしたぜ。昨日よく無事だったなお前」
「運よくプリンとかレトルトの粥とかあったから、それ食ったりしてた」
スポーツドリンクのほんのりとした甘さがありがたい。くだらない妄想事件はともかくとして、風邪の定番ものを差し入れてくれて助かったのは事実だ。
「あ、そこに貼ってるやつもぬるいんじゃねえの? 替えてやるよ」
実に自然な動作で額のシートを剥がされて、拒否するひまもなかった。
面倒見のよさが遺憾なく発揮されている。
……行き過ぎな気がするのは思い過ごしだろうか。いや、そんな感想自体が危険な気も……。
「そうだ、お前が休んでたぶんの講義のプリント持ってきたぞ。コピー代は差し入れぶんと一緒に、あとできっちり請求するからな~?」
どこか意地悪い笑みなのに、わずかに心臓が跳ねる。
あの切れ長の双眸と左にある泣きぼくろが、色気の元凶かもしれない。
さらに細められた状態で覗き込むように見つめられたら、道を踏み外しそうだ。
「お前さぁ……色気あるって、よく言われねえ?」
口にしてから、無意味に唇を思いきり真一文字に結ぶ。自分で自分をコントロールできていない。熱の恐ろしさを改めて実感する。
「んー、そうでもないけど? てかいきなりなんだよ」
自分も突っ込みたい。どう締めればいいのかわからず、とっさに「なんでもない」とありきたりで解決に向かない返しをしてしまう。
「……なるほど。お前、俺のこと色っぽいって思ってたんだ」
面白い遊びを発見した子供のような表情に、寒気とは違うものが背筋を走る。うまく説明できない。
「そういえば俺が世話してやってたときも嬉しそうだったし、もしかしてそういう意味で好きだったり?」
後ずさろうとして、背中を壁に預けていたことを思い出した。
「ま、俺としては狙った通りかな」
「……え、それって」
どういうこと。
訊き終わる前に、横になるよう促される。自分を映す瞳にますます輝きが灯って、ヘビに睨まれたカエルの気分そのものだった。
「のど、まだ乾いてるだろ?」
自分が口をつけたカップを自らのほうに持っていき、軽く傾ける。トレーの上に役目を終えたそれが置かれた瞬間、ようやく彼の意図に気づいた。
「ま、待っ……ん!」
口内に甘く冷たい感触が流れ込んでくる。火照った熱を冷ますように内壁もゆるくなぞられて、抵抗感が湧き上がらないどころか甘んじて受け入れてしまう。
まさか、夢見ていたシチュエーションがこんなかたちで実現するなんて。
「おいしかっただろ?」
満足げに微笑み、わざとらしく舌を這わせた親友の唇はつややかな光を放っていて、まるで蜜に誘われた蝶のように視線を奪われてしまう。
「それ、もっと欲しいって言ってんの?」
再び重ねられたのは、首を上下に振っていたのだろう。
すべてを飲み込んでもなお、唇は囚われたまま熱をさらに上げていく。不快感どころか、高揚感と気持ちよさを覚えるのは、彼がうまいせいか、風邪のせいか。
「……っあ」
離れていくのが名残惜しい。心の中の声は、ばっちり相手に伝わっていた。
「お前さ……人のこと煽るの、やめろって。さすがにこれ以上、手出せないし」
「いいよ。別に」
なんのためらいもなしに、肯定する。
「お前のせいで、下がってた熱がまた上がっちまった。見舞いに来たんなら、ちゃんと責任とれよ」
わがままなヤツ。
楽しそうに告げたその言葉が、合図だった。
身体を覆っていた毛布をまくられる。シャツの裾から滑り込んでくる、少しひんやりとした手のひらはごつごつとした感触をしているのに、甘美な痺れを生み出す。
「あ……っ、ん」
胸元をかすめた瞬間、思わず口元を塞いでしまった。なんだ、今の鼻にかかったような声は。
「ばか、塞ぐなって。そういう声、もっと聞かせろよ」
いやだと拒否しても彼はお構いなしに壁を壊して、頭上にまとめられてしまう。
「いいから、おとなしくしてろって……」
今度は舌でも触れられて、堪えきれずにみっともない喘ぎがこぼれ続ける。
男でも感じる場所だと知らなかったのは自分だけに違いない。でなければ、ためらいもなく胸に吸いつけるわけがない。
「気持ちいいんだろ? ここ、反応してる」
服の上からなぞられたら、抵抗する力はもうなかった。
「あ……はっあ、ぁ……、や……!」
緩急をつけて揉みしだかれ、ゆれる腰と声を止められず、ついには下着ごと下ろされ、直に触れられた――
目を開けると、見慣れた天井が飛び込んできた。
……天井?
耳の近くで鳴っていると錯覚しそうなほど心臓を脈打たせながら、首を軽く左右にひねる。いたはずの男がいない。というより初めから存在していない雰囲気だ。
「もしかして……」
夢?
声も感触もリアルに覚えているのに、まさかの夢オチ?
茫然自失とは今にふさわしい。ショックも計りしれない。そっと毛布をめくり、身体の中心を確かめてさらに後悔した。
どこからが夢だった? 変な妄想をしたところまでは覚えている。なら夢だけのせいにできないじゃないか。気の合う親友という認識だったはずなのに、ときどき色っぽく見えるなんて感想を抱いたばっかりに……!
のろのろと起き上がり、膝を抱える。しばらく穴ぐら生活をしたい気分でいっぱいだった。誰の目も届かない場所で、落ち着いて頭の中を整理するのに最低一ヶ月の時間がほしい。
「とりあえず、俺があいつを好きだってのはない。絶対ないから」
意味がなくても、言い訳をこぼしたかった。自分が好きなのは女の子、昔も今も女の子と恋仲になりたい。えろいことだってしたい。
『それ、もっと欲しいって言ってんの?』
『ばか、塞ぐなって。そういう声、もっと聞かせろよ』
『気持ちいいんだろ? ここ、反応してる』
瞬間、部屋を満たした音に、突き上がった衝動がかき消される。
家と外をつなぐ扉が、とてつもなく恐ろしく見えた。
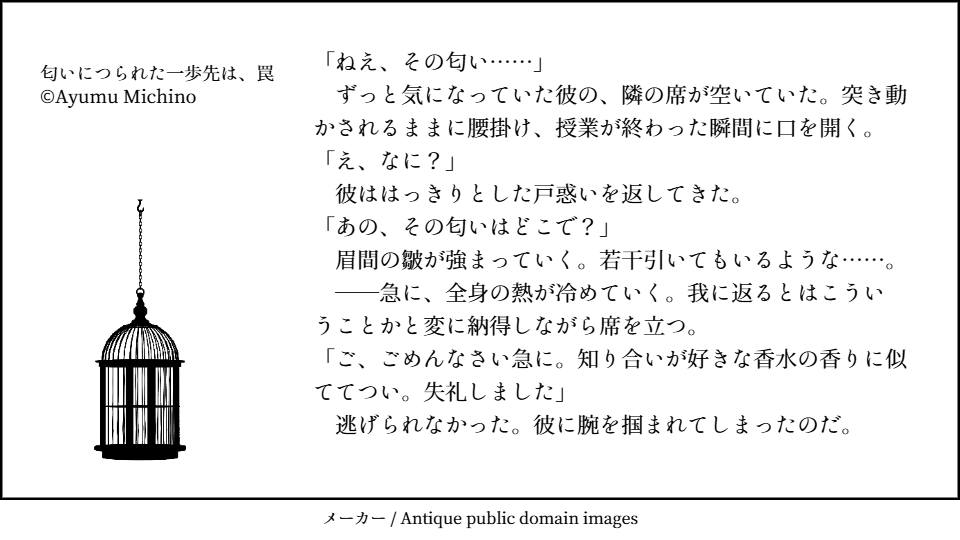
創作BL版深夜の60分一本勝負 のお題に挑戦しました。使用お題は「香り」です。
-------
「ねえ、その匂い……」
ずっと気になっていた彼の、隣の席が空いていた。突き動かされるままに腰掛け、授業が終わった瞬間に口を開く。
「え、なに?」
彼ははっきりとした戸惑いを返してきた。
「あの、その匂いはどこで?」
眉間の皺が強まっていく。若干引いてもいるような……。
――急に、全身の熱が冷めていく。我に返るとはこういうことかと変に納得しながら席を立つ。
「ご、ごめんなさい急に。知り合いが好きな香水の香りに似ててつい。失礼しました」
逃げられなかった。彼に腕を掴まれてしまったのだ。
「あ、あの。離して」
「待てって。思い出したんだよ」
不審や怪訝さにまみれていた表情から一変して、笑みを浮かべている。
「ち、ちょっと!?」
抵抗できない力で引っ張られるまま講堂をあとにして、人気のない空き教室に連れて行かれる。
「あんた、俺のダチと付き合ってた奴だろ」
こういうとき、うまい言い訳がすぐ出てくる人を本当に尊敬する。意味もなく顔をそらすしかできない。
「もう使わないからって余ったのをもらったんだけど、確かあんた、この香り好きだったんだっけ? あいつが言ってたよ」
好きだった。
いつも優しくて、自分の世界を広げてくれた彼にふさわしい香りだったから。
好きな彼が纏っていたからこそ、簡単に忘れられないほどに、好きだった。
彼の友達はようやく腕を解放してくれたが、出入口を塞ぐように扉に寄りかかった。どこか気持ち悪い笑みは変わらず、刻まれている。
「男と付き合うことになったって言われたときはびっくりしたなー。でも結局、うまくいかなかったみたいだけど」
「……やめて」
あの日の記憶がじんわりと頭を支配して、固く目を閉じる。
一時でも付き合えただけ幸せだった、期間限定でも神様が与えてくれた奇跡だった、そんなことを懸命に自らに刷り込む日々だった。やっと、やっと少し前を向けるようになってきたのに、こうやってまた、無駄にするのか。
「いいんだ、彼は男を好きになったのは初めてだって言ってたし、やっぱり女の人のほうが好きだってなってもおかしくないし。僕みたいに男しか好きになれないってやっぱり珍しいし」
いくら世の中が変化していっても人の嗜好は関係ない。だから彼を恨む気なんてさらさらないし、早く過去として受け入れないといけない。
「まあ、そうだな」
声が近くで聞こえて顔を上げると、彼の友達に見下ろされていた。あの人より背が高いから? 変な威圧感がある。
「でも、俺は正直興味あるんだよね」
「きょう、み?」
「そ。男を好きになるってどういう感じなのかなって」
心の隅にあった嫌な予感が成長していく。
「ねえ、俺に試させてくんない? 同性の恋人がどういうのか」
「な、にをばかなこと」
「いいじゃん。あんたも俺を利用すれば? 次の男が見つかるまでのつなぎでも構わないよ」
「つ、つなぎって! そういういい加減な理由なんて無理だよ!」
「無理かどうかはやってみないとわからないって」
キスは突然だった。振り払う暇もなく離れて、目の前の唇は憎たらしく満足そうに持ち上がる。
「少なくとも、俺は今全然気持ち悪くなかったぜ。あんたが可愛い顔してるからかもしれねえけど」
無意識に、頬をはたいていた。
「信じられない……きみ、絶対遊び人だろ」
「へえ、意外に気の強いとこもあんだ」
彼の友達は確かに驚いていたが、効果がまったくないのは明らかだった。
「遊び人だなんてとんでもない。俺って意外と一途よ? まだそういう相手が見つからないってだけ」
「物は言い様って言葉知ってる?」
「恋愛は一度きりってわけでもないだろ」
だめだ、口ではとても勝てそうにない。
どうしてあのとき、声なんてかけてしまったんだ。死ぬほど後悔しても遅いのに!
「……彼の香水、僕に渡してよ。君に持っててもらいたくない」
これ以上、彼との思い出を穢されたくない。
「いやだね」
「君が持ってたって意味ないだろ」
「意味はあるさ。俺が新しい恋人になるかもしれないだろ?」
「ない、絶対ない!」
視界が歪んできた。こんなに憎たらしく、悔しい思いをしたのは初めてだ。こんなやつと友達な彼にもなぜか腹立たしくなってくる。
「いいじゃんいいじゃん。あんた結構表情豊かなんだな。ずっと大人しい性格なんだと思ってたよ」
元々目立たない性格だと言いたかったけれど、もうどうでもいい。今はとにかくこいつをどうにかして、香水も手に入れないといけない。
「わかった。じゃああんたは俺から香水を奪うことを目標に、俺と付き合ってみなよ」
間抜けな問い返しをしてしまった。
「ていうか、そうでもしないとお試し付き合いしてもらえなさそうだし。どう?」
好きでもない人と、たとえお試しでも恋人同士になるなんて嫌だ、ほんとうに嫌だけれど……彼との大事な思い出を、守るためなら。
まるで悪魔に魂を売るような気持ちで、両手を固く、固く握りしめながらも、しっかり彼の友達を睨み、頷いた。
「よし。契約成立だな。……覚悟しとけよ?」
#ワンライ