Short Short Collections
主にTwitterのワンライ企画やお題で書いたショートショートをまとめています。
男女もの・BLもの・その他いろいろごちゃ混ぜです。
NotOneSummerLOVE
#BL小説 #R18——欲に負けた瞬間、ひと夏の過ちになると思った。でも、手のひらの上だったんだ。
高校生、同級生同士です。
続きを表示します
-------
少し色褪せた木目の天井を見つめていた。
見つめておく必要があった。
隣から意識を逸らしておく必要があった。
最初はただの同級生だった。
席替えをした時、前の席に彼がやってきたのをきっかけに、友達同士に変化した。
いつしか親友同士へとなり、……
驚くほど馬が合った。考え方は正反対、好きなものは被らない、けれど他の誰よりも、隣で呼吸をするのが楽だった。
『お前、今こういうこと考えてたろ』
それが彼の口癖となるのに時間はかからなかった。その予言はほとんど当たっていたからだ。
『お前はわかりやすいんだよ。まあ、俺が理解しすぎてるだけかもしれないけど』
ただのからかいとも取れる言葉が、嬉しかった。切れ長の目を細めて、口角を少し上げたさまが、格好いいとさえ思えた。
……逸らす必要があるくらい彼を好きになっていたのだ。
冷房は十分に効いている。
背中にじっとりと感じる熱は、明らかに隣のせいだった。
どうしてこうなったのか思い返してみる。夏休みの宿題を見てもらいたくて――本当は一緒にいたくて――彼の家に押しかけた。一時間もすると集中力は切れて、意外に長い睫毛とか、自分で整えているのかちょうどいい太さの眉をちらちら盗み見るようになったら、呆れたように気分転換のテレビゲームを提案された。それに敢えて熱中していたら思った以上に疲弊してしまい、互いに大の字に寝転んで、気づけば彼だけが寝ていた。そういえば寝付きのよすぎるタイプだと言っていた。
エアコンの風では打ち消せない呼吸音が左耳をくすぐる。――寝息だけを意識的に拾おうとしているのは明白だった。
身体の最奥で激しく打ち鳴らしているような鼓動が続いている。息を吐き出す瞬間も、無駄に熱さを含んだものだった。
視線はいつしか、テレビの左隣にある本棚へと移っていた。知っている漫画もあれば小難しそうな参考書と思われる文庫、分厚い図鑑など、多種多様な本が四段すべてにきっちりと収められている。
ここから視線を下ろしたら、無防備な彼へとたどり着いてしまう。今の状態で寝顔を捕らえてしまったら、どうなるかわからない。
「……、ん」
色を含んだように聞こえたのは特別な目で見ているせいだ。
だからこそ、ここでとめておかなければならない。
「つか、さ……」
名前を、呼ばれた。
今まで一度も、名前で呼ぶなんて、なかったのに。
まさか、夢を見ているのか?
夢の中に、「いる」のか?
「ゆき、と」
魔法にでもかかったみたいだ。鼓動のせいで苦しささえ感じているのに、今にでも飛び立ててしまえそうな気分になっている。
「ゆきと、ゆきと……」
何でも見通してしまう聡明な輝きに蓋をして、普段より柔らかな表情で寝息をこぼし続ける彼は、理性でつくられた壁を簡単に破壊していく。
エアコンは、もう役に立たない。
顔の両端に手をついた。初めて見下ろす、親友と油断している彼の無防備さにむしろ喉の奥を震わせた。
少しずつ肘を折っていき、腕半分を完全に床につける。
呼吸が、唇に触れる。皮膚同士はまだ離れているのに熱が伝わってくるような錯覚が襲う。彼の顔だけが、視界を埋め尽くして離れない。
夢の中でしか成し得なかった距離に目眩がしそうだった。
好きだ。友達として以上に、好きでたまらないんだ。お前しか考えられなくて、どうしようもないんだ。軽蔑しないでくれ。嫌わないでくれ。
初めてのキスは彼の飲んでいた麦茶の味が混じっていた。見た目には薄い唇なのに、心地よさを感じるほどに柔らかい。
口の中に吐息がかすかに入ってくる、それだけで何も考えられなくなる。いつまでも重ねていたいと、欲が頭を出しそうになる。
「っ、んぅ⁉」
あるはずのない衝撃が、後頭部に走った。反射的に身体を引こうとしても動けない。呼吸ごと奪おうとするような、確信的なキスまでされている。
「やっぱり、襲ってきた」
ほんの少しだけ距離を取って、目蓋の奥にあったダークブラウンがまっすぐに射抜く。
再び、唇を塞がれた。
背中をそわりとした感触が這って思わずくぐもった声を漏らすと、湿った塊が差し込まれる。
「ふぁ、は……っ、ん……!」
「ん……っは、ぁ……」
これは彼の舌なのか。苦しい。どう呼吸すればいいのかわからない。気持ちいい。
たくさんの情報が頭の中を圧迫して処理しきれない。ただ口内で余すところなくなぞっていく塊に、ぴくりぴくりと反応するばかりだ。
ちゅ、と唇を軽く吸われた音で、うつつな状態から戻ってくる。彼の細い指が下唇の端から端までをゆっくりなぞって、吐息に甘い音が重なる。
なんで。問いかけようと懸命に開いた口からは、引きつった悲鳴が漏れる。
「せっかくだから、こっちも触ってやるよ」
うそ、だ。
でも彼の手は確かに、ジーンズを押し上げているモノを捕らえている。形を確認するように、あるいは愛撫するように、ゆるく上下に動いている。
鼻で軽く笑う声が聞こえた。ベルトが外され、チャックまで下ろす動作を黙って受け入れてしまう。
両膝が崩れ落ちるのを助長するように、右耳に熱い吐息を注ぎ込みながら直に触れてくる。腰が大げさに跳ねるのも仕方ない。他人に、しかも彼に触れられる日が来るなんて、想像しろという方が無理だ。
自慰をするように、指全体で根元から先までを丁寧に何度もなぞる。たまに先端からにじみ出ている液体を拭うような動きを取り、さらになめらかな愛撫を重ねていく。
「わかるか? ここから、どんどんあふれてるの……」
「っ言う、なぁ……!」
「無理だね……お前が、エロいのが悪いんだ」
最初からエアコンがついていないような暑さにまみれている。汗がにじむ。触れ合ったところすべてが、じっとりとあつい。
「……ねえ。俺のも一緒に、触ってほしい」
触って?
もう一度ねだる声が、波紋のように頭に響く。
向かい合わせの体勢になると、明らかな欲に染まった表情と対面してぼうっと見つめてしまう。
視線で続きを促され、タックボタンを外し、下着越しに一度撫でる。十分な硬度が手のひらに返ってきて、思わず喉を鳴らしてしまう。
「っあ、は……ぁ」
甘く、待ち望んだとわかる溜め息が自らのものと混ざり合って、身体の奥がひどく反応している。
触れられている中心に、集まっていく。
「お前の……っまた、大きくなった、ぞ」
欲情にまみれながらも鋭い光を秘めた双眸と、唇が、ゆるやかな弧を描く。
とめられない。五感すべてが、彼を求めてやまない。
彼の一番の熱を、直接感じたい。下着を下ろして、そろりと手を添える。小さな震えを返してきた彼にいとおしさが増して、あふれる液を塗りつけるように全体を愛撫していく。少しずつ大きくなる濡れた音にさえ、煽られる。
クーラーの風は聞こえない。冷たさも感じない。でも、それでいい。もっとこの熱に浸っていたい。ぼやけた視線を、浮かれた吐息を、交わし合っていたい。
けれど、腰が軽く痙攣するほどに限界が近いのもまた、同様で。
「一緒に、いきたいんだろ?」
ふいに耳元へと落とされた囁きに、素直に首を上下させた。
互いに、撫でる動きを加速させる。鼓動がさらに速さを増す。無意識に伏せていた瞳を持ち上げて彼を捕らえると、唇を重ねた。
身体全体の熱が倍に膨れ上がって……すとんと落ちる。
手の中の感触を確かめるように、ゆっくりと握りしめた。
「全部わかってたよ。お前が寂しくなって、俺のところに押しかけてくることも」
さっきよりも温度の下げられた風が、身体全体を優しく撫ぜていく。
「お前が、ずっと俺のことを好きだったってことも」
繋がったままの手に、力が加わる。
「いつまでもうじうじしてるから、仕掛けてやったんだ。予想通り食いついてくれて、俺としては大満足だね」
隣を見やると、推理が的中した探偵を彷彿とさせる笑みが待ち構えていた。
彼に一番似合う、一番見惚れてしまう表情だった。畳む
油断禁物
#BL小説思いついたシーンをつらつら書いてみました。
イメージ的にはサラリーマン同僚同士。のらりくらり型男子とツンツン気味男子。受け攻めはあまり考えずに書きました。
続きを表示します
-------
まったく、まいったなぁ。
大体「なんでもないんですよー」「こっちは大丈夫です、それよりあなたですよ! なんか疲れてません?」的なことを言っておけばかわせるのになぁ。
「下手な誤魔化しなんてしないほうがいいよ」
「そっちのほうがしんどそうな顔してるくせに、よくそんなこと言えるね。呆れるよ」
ストレートすぎるくらいストレートに、実年齢より若く可愛い容姿の彼は言ってくる。
このすっぱり感はうちの弟を思い起こさせるが、むしろ鋭利さが増している。
綺麗なバラにはトゲがある的な? 綺麗より可愛いだけど。
変に詮索されるのは苦手なんだよね。自分は自分、他人は他人。たとえば俺が親身に話を聞いたところで、本当の意味で他人を理解できるわけじゃない。どうしたって主観が混じってしまうから、失礼だと思うんだ。
まあ、話すだけでも楽になるっていうのもあるけど、自分にはあんまり当てはまらないかな……。今までも自分で処理できてたし。
今回はちょっと、珍しく長引いてるってだけ。
「あんたは多分強い人間なんだろうけど、いつまでもそれを保ってられるわけじゃないでしょ」
「変な意地張ってないで、いい加減さっさと折れたら? 限界迎える前にさ」
それより、なんで君はこんなに構ってくるわけ? こっちの状態見抜けるわけ?
確かに普段からやり取りは多いほうだけど、大体ツンツンした態度だから、嫌われてるとばかり思ってた。俺はせいぜい「まあ面白いやつだな」ぐらいの意識だった。
彼のことがよくわからなくなってきたよ。
「そんなに必死になっちゃって、よっぽど心配なの? もしかして俺のこと好き?」
ドラマとかでよくある冗談を言えば、怒って解放してくれると思ったんだよね。
ほんと、もういい加減にしてほしかったし。
「……そうだとしたら、どうなの?」
まっすぐに俺を見つめて、ツンツンした物言いも影をひそめて。
予想外の反応に、もっとわからなくなった。まさかこっちが動揺するなんて思わなくて、うまい言葉が出てこない。
彼がさりげなく距離を詰めてきた。目線がほぼ同じ位置だ、なんて場違いな感想を抱いてしまう。
「ぼくがあんたを好きだって言ったら、あんたは素直になってくれるわけ?」
初めて間近で見た彼の瞳は、腹が立つほど綺麗だった。
真面目な言い方をしてるってことは、まさか、本当に? いやでも、全然そんな素振りなかった。わからない。
「それは、どうだろうね」
精一杯の返答をすると、まったく可愛くない不敵な笑みを彼は浮かべた。畳む
ひっつき虫が可愛く見えるまで
#BL小説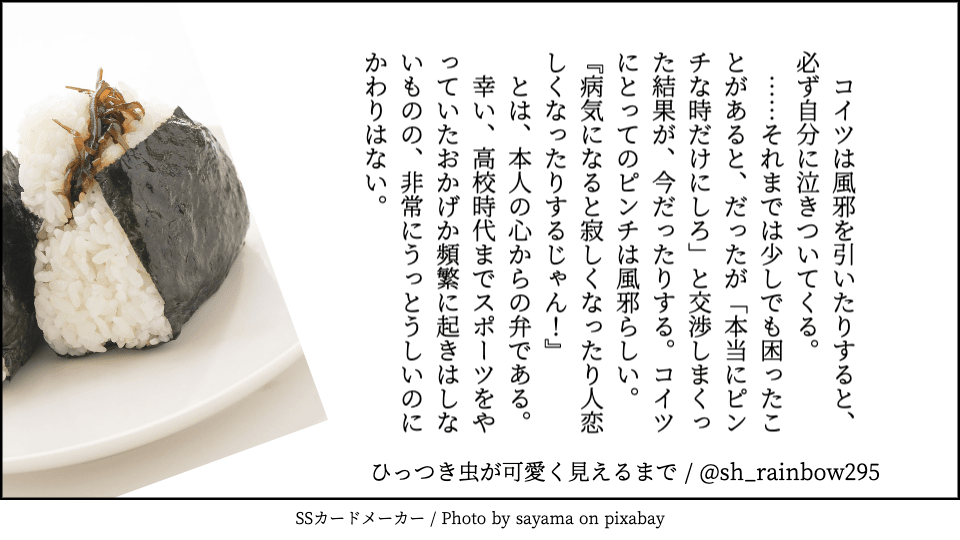
ふらっと思いついたまま書いてみたものです。
主人公:無自覚な友達以上恋人未満
お相手:片思い
な雰囲気です。
続きを表示します
-------
コイツは風邪を引いたりすると、必ず自分に泣きついてくる。
……それまでは少しでも困ったことがあると、だったが「本当にピンチな時だけにしろ」と交渉しまくった結果が、今だったりする。コイツにとってのピンチは風邪らしい。
『病気になると寂しくなったり人恋しくなったりするじゃん!』
とは、本人の心からの弁である。
幸い、高校時代までスポーツをやっていたおかげか頻繁に起きはしないものの、非常にうっとうしいのにかわりはない。
「安藤~どこ行くんだよ~オレを一人にしないで~」
「だー! 買い出しだってんだろが!」
「そんなの宅配とか通販でいいじゃんか~」
「今すぐ持ってきてもらえるわけないし配達の方に申し訳なさすぎるわ! てか徒歩5分もかからないコンビニなんだから我慢しろっての!」
これである。毎回、これである。
とにかくべったりひっついてくるのだ。いくら友人とはいえ同性に隙間なくくっついて気持ち悪くないのだろうか?
「ったく、お前は毎回毎回しょーもないな……」
やはり寝入った隙に行くしかない。一応病人だから気を遣う心はあるものの、精神力が異常にがりがり削られて、気を抜いたら共倒れしてしまうんじゃないかと思うこともある。
「へへ、安藤が優しいとこも毎回変わらないよ」
「へいへい、嬉しいお言葉をどうも」
ベッドに大人しく横になった石川はふにゃりと口元を緩めた。身長が180以上ある、精悍な男の笑顔にはつくづく見えない。
「つーか、いい加減彼女とか作れよ。よっぽど甲斐甲斐しく世話してもらえんぜ?」
余計なお世話だろうが、言わずにはいられなかった。自分だって、いつまでも「お世話係」をやらされたらたまったもんじゃない。
「……え?」
さっきまでの笑顔はどこへやら、見事に固まってしまった石川にこちらも面食らう。
「な、なんだよ。俺ヘンなこと言ったかよ。そりゃ余計なお世話だと思ったけどよ」
その気になれば、恋人という関係を手に入れられる容姿も性格も備わっている。他の友人もきっと同じ評価をするだろう。
「……オレを捨てるんだ」
全く予想外の言葉に勢いよく殴られた。恋人に縋り付くダメ男そのものじゃないか。
「オレが頼れるのは安藤しかいないのに……」
「いやいや、他にもいるだろ。お前が俺にばっか言ってくるだけで」
「オレは安藤がいいの!」
本当に、物理的に縋り付いてきた。振りほどきたくとも病人相手に本気は出せないのに、ものすごい力が腕にかかっていて痛い。
「おま、ちょっと力ゆる」
「安藤じゃなきゃイヤなんだ。いつだって、安藤にそばにいて欲しいんだよ」
似たようなことは高校生の頃から言われてきた。まるでお熱い告白のようにも聞こえると冗談まみれで返しては石川がただ笑って、気づけばやり取りの頻度は減った。
どういうつもりで言葉にしているのか、深くは考えていなかった。ただ、石川がどこか寂しそうな雰囲気を漂わせていたような気はする。
「そ、そばにって、なんか、意味合い違うように聞こえるんだけど」
今日はいつもと違う。風邪を引いているせい? だとしてもこんなに戸惑うだろうか。らしくない返答をしてしまうだろうか。
「ちがくないよ。オレにとっては一緒だから」
見上げてくる石川の瞳は完全に高熱で揺れていた。触れたら崩れてしまうんじゃないかとつい思ってしまうほど、頬も熟れすぎている。
「オレには安藤だけだもん。知らないでしょ、オレがどんだけ安藤を」
「ま、待て待て。お前風邪引いた勢いで変なこと言うんじゃねえって」
この流れはお互いにとって不幸しか生まない気がする。もし危惧している通りの流れになったら正直受け止め切れない。
「変なことじゃないよ。オレ、前から言ってるじゃん」
触れられた腕から伝わる熱さで、自分まで眩暈でも起こしそうだ。こんな展開になるなんて誰が想像しただろう。
「安藤……本当に、だめ? オレ、一ミリも望みなし?」
これでもかというくらいに眉尻を下げて、図体とは正反対の空気を一気に纏いだした。
正直、ずるい。こんなの、駄目だと一刀両断しづらいじゃないか。いや、ここで中途半端な態度を晒してしまうのがいけないんだと思う、思うが。
「……なんだかんだで、大事な奴だとは思ってるよ。じゃなかったら、クソ面倒なお世話なんてしねえし」
石川が求める意味とは違うだろうが、嘘ではない。一番つるんでいる友人だし、一緒にいると気が楽というか、自然体でいられる存在だったりする。
「……安藤がそんなこと言ってくれるの、はじめてだね」
本当に驚いたようで、小さい双眸がかなり見開かれている。
「ありがとう、納得したよ。今はね」
「今は、ってなんだよ」
「うーん……そうだなぁ」
頬をそろりとひと撫でした石川は、唇の端をわずかに持ち上げた。
「覚悟しといてね、ってことかな」
小悪魔のような笑みとは、今のような表情を言うのだろうか。
初めて、心臓が無駄に高鳴ってしまった。
「へいへい。心からお待ちしておりますからいい加減寝ろ」
悟られないよう、石川の頭を枕に押しつけて布団をかぶせる。
きっと自分も見えない熱に浮かされているに違いない。そう思い込まないと、動揺を抑えられそうにはなかった。畳む
感情の共有
#男女もの
続きを表示します
-------
まだ離れたくないな、と思ってしまった。
相手からすればただのわがままだ。しかも二人きりで出掛けたのはこれが初めて。それなのに求めすぎじゃないだろうか。
「どうかしたの?」
口数が減っていたらしい。慌てて作り笑いを返して、本当に今日は楽しかったと改めて感想を伝えた。
お世辞抜きに、ただ楽しかった。この人と一緒にいるととても心地いいし、多分「ピースがかちっと嵌まる」感覚はこのことを言うんだろうとさえ思えたくらいだ。
視界の先に、駅の出入口が見えてきた。あそこに辿り着いたら今日は解散しなくてはならない。
――果たして、この人も同じ想いでいてくれているんだろうか?
そうだ、今日があまりにも楽しすぎてその可能性を忘れていた。下半身から力が抜けていくような感覚に襲われて、一気に未来が怖くなった。
足を止めてしまった自分を、想い人は怪訝そうに振り返った。
絶対に、この出会いを無に帰したくなかった。この人とこの先も付き合っていきたい。
「……っあ、の」
声は驚くほどに震えていた。目の前の表情が明らかな心配顔に変わる。違う、具合が悪いんじゃない。反射的に首を振ってから、勇気を出して左腕の裾を掴んだ。
「もう少しだけ、付き合ってくれませんか」
わずかに開かれた目を必死に見つめ続ける。拒否されたら、という恐怖で押しつぶされそうな心を意地で食い止める。たとえどんな結果でも、この選択をしなかった後悔だけはしたくなかった。
自分にとっては五分くらい経ったような感覚が身体を走った時、右手に少し湿ったようなぬくもりが触れた。
「ありがとう。……実は俺も、同じことを考えていたんです」
——ああ。少なくとも今は、同じ気持ちを共有しているんだ。
望む未来への足がかりになれた。それだけで今はたまらなく幸せだ。
触れたままの手に相手の指が絡まる。優しく込められた力に引かれるかたちで、解散予定だった場所とは反対の方向へと歩き始めた。畳む
カテゴリ「その他SS」[8件]
Powered by てがろぐ Ver 4.2.0.
template by do.
ふたつの直線、交わる日はいずこ
#男女もの——諦めない。気持ちを受け入れてもらえるまで。
*平泉春奈×エブリスタ 短編小説コンテスト 応募作品です。
エブリスタで読む場合はこちらから 。
------
「すっかり遅くなっちゃったわね」
依頼を受けた時は、まさか都内を飛び出すことになろうとは思いもしなかった。思わぬ遠出になってしまった。
依頼主の関係者に話を聞く必要が出たまでは仕方ないものの、事情で正体を明かせない、理由も明かせないのはさすがに参った。
「でも、おかげで完璧な報告ができるんじゃないですか?」
私の事務所でただひとりの所員である彼は弱々しくも明るく笑った。
「そうね。これなら謝礼もたんまりもらえることでしょう」
「さすが、たくましいリーダーですよ」
「でしょ?」
上司と部下の垣根を越えたやり取りも、すっかり板についた。とても心地のいい、まさに理想的な状態だとつくづく実感して、幸せにさえ感じる。
腕時計を確認すると、もうすぐ日没を迎えそうな時間だった。この道をまっすぐ進めばバス停に辿り着く。便はまだ残っているはずだった。
背伸びついでに横を見ると、湖面に橋がかかっているように、オレンジ色の光が山の方へと伸びていた。今の疲労感に相応しい、優しく穏やかな景色ができあがっている。仕事でなければカメラ片手にゆっくり散歩を楽しんでいただろう。
「秋は紅葉とかすごそうよね、ここ」
少し見上げればまだ瑞々しい葉をつけている木々が出迎えてくれる。先の季節を想像したら、ますますプライベートで訪れたくなった。
「実際、春と秋はそれなりに混むところらしいですよ。デートスポットとして密かな人気があるって、ネットの記事に書いてあったかな」
「へえ。じゃあ、さっきカップルの振りをしたのは間違いじゃなかったってことね」
思い出してつい笑いそうになる。彼が妙に慌てふためいていたからだ。依頼人からたまに告白されることもあるらしいのに、意外と初なのかそもそも恥ずかしがり屋なのか。
「デートはこういうところでしたい派?」
「……僕は、あんまりこだわりはないですよ。好きな人とだったらどこでも楽しいと思うし」
「そうなの? ああ、でもあなたらしいね。好きな子が聞いたらすごく喜ぶんじゃない?」
手を繋いでにこにこ散歩を楽しむ姿が頭に浮かぶ。きっと微笑ましい光景に違いない。
「所長は、どうなんですか?」
声のトーンが変わった気がして、思わず足を止めた。
少しずつ弱まる光に照らされた彼の表情が、変に真剣に見える。たいした話題でもないのに。
「私は、そうね。どっちかっていうとこういう静かなところとか、自然が多いところがいいかな。のんびりしたいから」
「のんびり、ですか。所長なら酒とつまみ、絶対持って行きそうな気がしますけど」
「あ、言うじゃない。確かにお酒は大好きだけど、飲み屋とかで思いっきり楽しみたいタイプだからね私」
「ええ、本当ですか?」
「本当よ! 何回も一緒に飲みに行ったことあるでしょ?」
……普通だ。
さっきの違和感が嘘だったように、元通りの空気が流れている。
単なる勘違いだったのか?
「じゃあ、それを証明するためにも今度出かけませんか?」
一歩、彼が距離を詰めた。光が背中に隠れて、表情が見えにくくなる。
「何、デートでもしてくれるの?」
再び変な緊張感を覚えて、わざとおどけてみせた。
何が正解なのか、もはやわからない。こんな彼は知らない。
「……所長がそれでいいなら、僕、本気で誘いますよ」
――自分の身体が、どこかに連れて行かれたかと思った。
視界が白く染まる。
右目が少し眩しい。
私以外の熱が、私に触れている。
「……ちょ、ちょっと?」
ドラマや映画を観ていて、「どうしてすぐ行動できないの?」と登場人物に対してぼやくことが結構ある。
実際、できるわけがなかった。
体験し慣れてないほど、予測不能であればあるほど、頭が回らず、全身が縫い付けられてしまう。
そして、意味もなく自問してしまう。
どうして、私は彼に抱きしめられているの?
「さっき、所長が恋人の振りしてくれたとき、年甲斐もなく嬉しいって思ってました」
伝わってくる心臓が速い。緊張しているのは明白だった。
これが冗談なら、かなりの芸達者と言える。
「好きです。ずっと好きでした。僕が依頼人だったときから、ずっと」
「そんな、前から……」
思わずつぶやいていた。
働かせて欲しいとあんなに頼み込んできたのは、それが理由? 何回断っても諦めなかったのは、私を想ってくれていたから……?
さらに引き寄せられる。身じろぎしても力は緩まない。
「気づいていたんじゃないですか? 僕の気持ち」
半分正解で、半分外れだ。
特別な好意をもってくれているのは、何となくわかっていた。だが、そこまでだった。深く探ろうとはしていなかった。
「所長の隣で過ごすようになって、どんどん好きになっていきました。仕事に誰よりも誇りを持っているところも、まっすぐ過ぎて時々不器用になるところも、可愛いものが好きなところも、何もかも」
彼にはいろんな私を晒してきたと思う。
それでも、決して否定することなく隣に立ち続けてくれていた。いつしか心地よさに変わっていったのは、嘘じゃない。
「僕は、あなたの特別になりたい。あなたの近くに、いたいです」
嬉しい。
素直な気持ちだった。こんなに想われて、いやなわけがない。もったいないとさえ思う。
無意識に拳を握りしめていた。変に震えて、あまり力が入らない。
「……ありがとう」
何とか、最初に言いたい言葉を返せた。
「私も好きよ。あなたがとても大事」
抱きしめてもらえて、敢えてよかったかもしれない。顔を見ながらなんて、とてもできそうにないから。
息をのむ音が聞こえたところで、緩く首を振った。
「私にとって……あなたは、最高の相棒よ。それ以上でも、それ以下でもない」
時間が止まったようだった。
空気が固まっている。微風さえ感じない。彼は動かない。
「他の誰も、代わりなんて務められないわ。私の隣に立てるのは、間違いなくあなただけ」
彼が求めている答えではないとわかっている。ある意味、最上級の残酷な言葉を投げている。
「……仕事上での、相棒ですか」
絞り出すような声がかすかに震えていた。
「光栄です。もったいないと思います。でも……仕事上、なんですね」
納得できないと、言外に告げている。
「他に好きな人がいるんですか?」
「いないわ」
「僕みたいな男は眼中にもない?」
「そういうわけじゃない。あなたは本当に素敵な人だと思う」
「だったら!」
縋り付かれているような心地だった。
「だったら……いいじゃ、ないですか……」
もしかしたら、泣いているのかもしれない。私のせいで、いつも纏っている穏やかな空気を澱ませてしまった。
それでも答えは変えられない。
たとえ、たとえ彼がいなくなってしまったと、しても。
――本当に? 違う。本当はいやだ。彼に「相棒」であることを受け入れて欲しい。そして隣に立ち続けて欲しい。
何て一方的なわがままだろうか。こんなわがまま、彼が受け入れるとは到底思えない。なのに、私は説得できる言葉を必死に探している。
「……私、本当に仕事だけね」
彼に訊き返されるまで、声に出していたことに気づかなかった。
夕日に照らされた彼の瞳は、陽炎のようにひどく揺らめいている。耐えきれず、少し目を伏せた。
「仕事の報告はすらすら言えるのに、駄目ね。あなたのことが、恋愛感情とか、そういうの関係なしに大事なんだってうまく言えそうにない」
「……うまく言えたとしても、意味なんてないです。僕は、あなたと恋人同士になりたい。あなたは、僕と相棒になりたい。着地点が違う」
だから説得しても無駄だと、はっきり宣言されたも同然だった。
力ない笑いがこぼれた。お互い、どこまで頑固なんだろう。どちらかが諦めなければまっすぐな道が映るばかりだ。
「はぁ……」
距離を取った彼が、肺の中を空っぽにする勢いでため息をついた。
「やっぱり、勢いで告白なんてしたら駄目ですね」
半分以上は山の裏側に沈んだ夕日を、正面から受け止めている。ぎりぎりまで細められた目が、やけに輝いているように見えた。
「本当は、わかってたんです。所長は僕のこと大事に思ってくれているけど、僕とは違う気持ちなんだって」
「……私、そんなにわかりやすい?」
「いつも仕事のことばかりなんですもん。仕事が好きすぎて、他が入り込む余地がないっていうか」
何年も前に振られたときも同じことを言われた。その頃はまだ事務所を立ち上げたばかりで必死だったせいもあるが、仕事好きは当時も変わらなかった。
「それなのに……恋人の振りしただけで我慢できなくなるなんて、ほんと、格好悪い」
身体の内側からじわりと熱くなってきた。裏を返せば、それだけ想いを募らせていたという証なわけで……。
さっきの熱烈な告白たちを思い出して、自然を装って目線ごと俯く。
「何ですか、その顔。もしかして、今さら恥ずかしがってくれてるんですか?」
「い、今さらって、だって、いきなりだったし」
「でも、そういう反応してくれたんで、ちょっと自信つきました」
そのまま歩き出した背中を、少し迷って追いかける。迷いを吹っ切った態度に見えるのは気のせいなのか。
だとしたら、何を考えているのか。
「あなたの気の済むまで、相棒でいてあげます。その間に、絶対惚れさせてみせます。僕の諦めの悪さはよくご存じでしょう?」
顔だけ振り返った彼は、あのときと一緒の笑顔を浮かべていた。
社員として彼の採用を決めたときと、同じ。
「……何よ。一人で勝手に解決して、勝手に決めて」
わざと彼を追い抜いてやった。聞こえた笑い声は空耳に違いない。
「大事な相棒が辞めるんじゃないかって心配だったんじゃないですか?」
すぐ隣に並んだ彼の顔が目に浮かぶようで、正直悔しい。反論はしないが多分正しい。
「いいわ。あなたの挑戦、受けてあげる。でもそう簡単にいくかしら」
「長期戦はとっくに覚悟してます。でも、今まで通りだと思ったら大間違いですよ」
回り込んできた彼の顔が、やけに近い。いつの間にか顎も掴まれて、動けなくなっていた。
「ちょ、っと。まだ付き合ってないのに、反則じゃない?」
彼を至近距離で見つめるのは初めてだった。改めてなかなか整っていると実感する。それを活かして何度か偵察に向かわせたこともあった。最初は初々しかったけれどだんだん板についてきて頼もしく感じると同時に少し寂しさも―― 「また緊張してる。隠そうとしても無駄ですよ」
呆気なく見破られた。
いや、それよりもキスをされた。口ではなく頬だが、キスにかわりはない。
「じゃ、いい加減行きましょうか。帰れなくなっちゃいますしね」
反射的に繰り出した拳は虚しく空振りに終わった。そのまま小走りで逃げていく背中をすぐ追いかける。
「頬もだめじゃない!」
「あれ、頬へのキスは親愛の証だって知らないんですか? 親が子どもにやったりするじゃないですか」
「私たちの関係は今そういうのじゃないでしょ!」
もしかしたら、早まったかもしれない。
相棒を失わない代償に手元にやってきた、変化の確定した日々を想像しただけで落ち着かない。
これも、彼の作戦?
だとしたら、バス停に着くまでにいつもの私を少しでも取り戻さなくちゃ。
戦いはもう、始まっているのだから。畳む