Short Short Collections
主にTwitterのワンライ企画やお題で書いたショートショートをまとめています。
男女もの・BLもの・その他いろいろごちゃ混ぜです。
ひっつき虫が可愛く見えるまで
#BL小説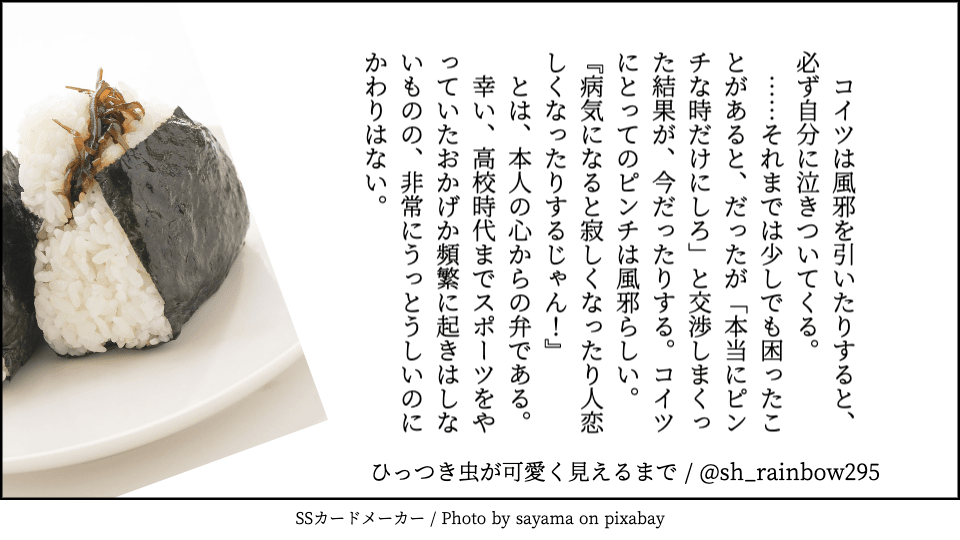
ふらっと思いついたまま書いてみたものです。
主人公:無自覚な友達以上恋人未満
お相手:片思い
な雰囲気です。
続きを表示します
-------
コイツは風邪を引いたりすると、必ず自分に泣きついてくる。
……それまでは少しでも困ったことがあると、だったが「本当にピンチな時だけにしろ」と交渉しまくった結果が、今だったりする。コイツにとってのピンチは風邪らしい。
『病気になると寂しくなったり人恋しくなったりするじゃん!』
とは、本人の心からの弁である。
幸い、高校時代までスポーツをやっていたおかげか頻繁に起きはしないものの、非常にうっとうしいのにかわりはない。
「安藤~どこ行くんだよ~オレを一人にしないで~」
「だー! 買い出しだってんだろが!」
「そんなの宅配とか通販でいいじゃんか~」
「今すぐ持ってきてもらえるわけないし配達の方に申し訳なさすぎるわ! てか徒歩5分もかからないコンビニなんだから我慢しろっての!」
これである。毎回、これである。
とにかくべったりひっついてくるのだ。いくら友人とはいえ同性に隙間なくくっついて気持ち悪くないのだろうか?
「ったく、お前は毎回毎回しょーもないな……」
やはり寝入った隙に行くしかない。一応病人だから気を遣う心はあるものの、精神力が異常にがりがり削られて、気を抜いたら共倒れしてしまうんじゃないかと思うこともある。
「へへ、安藤が優しいとこも毎回変わらないよ」
「へいへい、嬉しいお言葉をどうも」
ベッドに大人しく横になった石川はふにゃりと口元を緩めた。身長が180以上ある、精悍な男の笑顔にはつくづく見えない。
「つーか、いい加減彼女とか作れよ。よっぽど甲斐甲斐しく世話してもらえんぜ?」
余計なお世話だろうが、言わずにはいられなかった。自分だって、いつまでも「お世話係」をやらされたらたまったもんじゃない。
「……え?」
さっきまでの笑顔はどこへやら、見事に固まってしまった石川にこちらも面食らう。
「な、なんだよ。俺ヘンなこと言ったかよ。そりゃ余計なお世話だと思ったけどよ」
その気になれば、恋人という関係を手に入れられる容姿も性格も備わっている。他の友人もきっと同じ評価をするだろう。
「……オレを捨てるんだ」
全く予想外の言葉に勢いよく殴られた。恋人に縋り付くダメ男そのものじゃないか。
「オレが頼れるのは安藤しかいないのに……」
「いやいや、他にもいるだろ。お前が俺にばっか言ってくるだけで」
「オレは安藤がいいの!」
本当に、物理的に縋り付いてきた。振りほどきたくとも病人相手に本気は出せないのに、ものすごい力が腕にかかっていて痛い。
「おま、ちょっと力ゆる」
「安藤じゃなきゃイヤなんだ。いつだって、安藤にそばにいて欲しいんだよ」
似たようなことは高校生の頃から言われてきた。まるでお熱い告白のようにも聞こえると冗談まみれで返しては石川がただ笑って、気づけばやり取りの頻度は減った。
どういうつもりで言葉にしているのか、深くは考えていなかった。ただ、石川がどこか寂しそうな雰囲気を漂わせていたような気はする。
「そ、そばにって、なんか、意味合い違うように聞こえるんだけど」
今日はいつもと違う。風邪を引いているせい? だとしてもこんなに戸惑うだろうか。らしくない返答をしてしまうだろうか。
「ちがくないよ。オレにとっては一緒だから」
見上げてくる石川の瞳は完全に高熱で揺れていた。触れたら崩れてしまうんじゃないかとつい思ってしまうほど、頬も熟れすぎている。
「オレには安藤だけだもん。知らないでしょ、オレがどんだけ安藤を」
「ま、待て待て。お前風邪引いた勢いで変なこと言うんじゃねえって」
この流れはお互いにとって不幸しか生まない気がする。もし危惧している通りの流れになったら正直受け止め切れない。
「変なことじゃないよ。オレ、前から言ってるじゃん」
触れられた腕から伝わる熱さで、自分まで眩暈でも起こしそうだ。こんな展開になるなんて誰が想像しただろう。
「安藤……本当に、だめ? オレ、一ミリも望みなし?」
これでもかというくらいに眉尻を下げて、図体とは正反対の空気を一気に纏いだした。
正直、ずるい。こんなの、駄目だと一刀両断しづらいじゃないか。いや、ここで中途半端な態度を晒してしまうのがいけないんだと思う、思うが。
「……なんだかんだで、大事な奴だとは思ってるよ。じゃなかったら、クソ面倒なお世話なんてしねえし」
石川が求める意味とは違うだろうが、嘘ではない。一番つるんでいる友人だし、一緒にいると気が楽というか、自然体でいられる存在だったりする。
「……安藤がそんなこと言ってくれるの、はじめてだね」
本当に驚いたようで、小さい双眸がかなり見開かれている。
「ありがとう、納得したよ。今はね」
「今は、ってなんだよ」
「うーん……そうだなぁ」
頬をそろりとひと撫でした石川は、唇の端をわずかに持ち上げた。
「覚悟しといてね、ってことかな」
小悪魔のような笑みとは、今のような表情を言うのだろうか。
初めて、心臓が無駄に高鳴ってしまった。
「へいへい。心からお待ちしておりますからいい加減寝ろ」
悟られないよう、石川の頭を枕に押しつけて布団をかぶせる。
きっと自分も見えない熱に浮かされているに違いない。そう思い込まないと、動揺を抑えられそうにはなかった。畳む
愛したくて愛したくて
#BL小説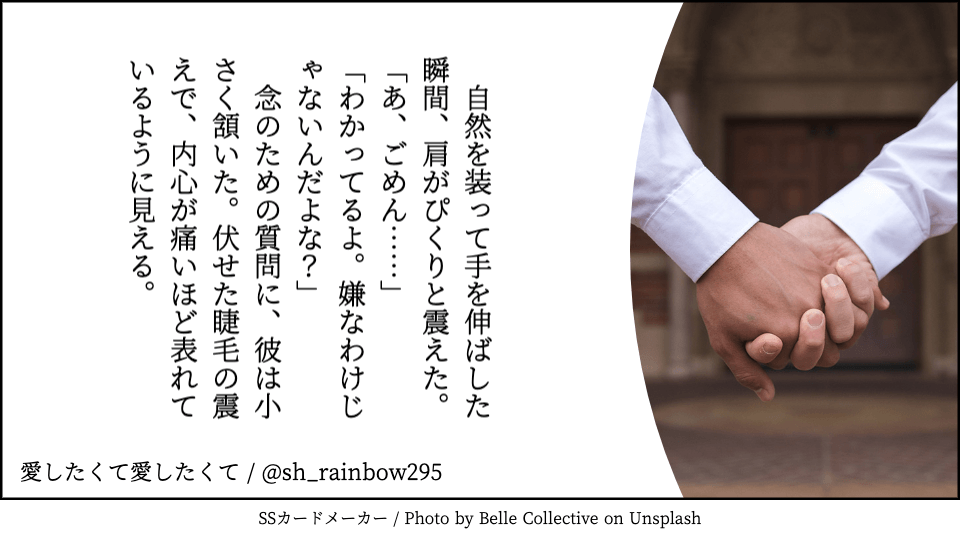
お題bot* のお題に挑戦しました。
お題は「愛されることには、まだ不慣れで、」を使いました。
続きを表示します
-------
自然を装って手を伸ばした瞬間、肩がぴくりと震えた。
「あ、ごめん……」
「わかってるよ。嫌なわけじゃないんだよな?」
念のための質問に、彼は小さく頷いた。伏せた睫毛の震えで、内心が痛いほど表れているように見える。
勇気を振り絞った告白に、受け入れてもらえた瞬間の自分以上に彼は驚いていたと思う。
『告白ってしてもらったことなくて……いつもこっちからしてたから』
脈があるとわかっていても、自分から告白してOKをもらわないと気持ちを信じられないこと。
だから多分、告白されていたとしたら、その瞬間に気持ちは冷めてしまっていたかもしれないこと。
普通じゃないとわかっていても逃れられずにいたことを、告白したその日にカミングアウトされた。
『え、じゃあなんで俺は……』
『わかんない。わかんないけど、大丈夫だったんだ。むしろ、なんかぶわーってなったっていうか、もっと好きになったっていうか……』
普段の付き合いで驚くほど正直者だと知っているから、ひどく戸惑っている姿を疑う気にもなれなかった。
『じゃあ、正式に付き合って、みる?』
普通なら諸手を挙げて喜ぶ場面でお互いおそるおそるなのも変な状況だが、改めて気持ちを確かめてみると、控えめに笑いながら頷いてくれた。
「逆に見てみたいかもな、お前の『愛し過ぎちゃう』姿」
微妙に伝わってくる緊張感をほぐすように肩を軽く撫でながら言うと、びっくりしたようにこちらを見つめてきた。
「トレーニング中なのはわかってるけど、愛されるのも好きだからさ。たまには受けたい」
『恋人に愛される喜び、っていうのを確かめてみたいんだ。あと、勉強もしてみたいし……だからしばらくは、受け身でいさせてくれる?』
冗談を言っているようにはもちろん見えなかったし、それだけ自分との関係を本気で考えてくれているのだと嬉しくなった。
今も不満らしい不満は特にないものの、欲が頭をもたげ始めたのもまた、事実で。
「……説明したこと、あったよね?」
いつでも「100%」を出し切って接していた結果、ある人は重すぎると苦し紛れに呟かれ、ある人は束縛されているみたいで嫌だと泣かれ……反省して言動を改めてみたつもりでも、ゴールは「離別」一本だったという。
興味本位もあるが、そこまでの愛情を浴びてみたいという純粋な願いもあった。
たとえどんな姿であっても、彼への想いは絶対に揺るがない。
「わがまま言ってるのは自覚してる。強制もしない。……でも、味わってみたいなぁ」
敢えて砕けた言い方をしてみた。
「完全再現じゃなくていいから! こんな感じだったかも、ぐらいで全然」
「余計に難しいよ……でも、僕のわがままに付き合ってもらってるもんね」
気合いでも入れるためか一度頷くと、肩に伸ばしていた手をそっと外し、緩く握り込んできた。
思わず息をのむ。
覗き込むように見つめてきた瞳の輝きが、いつもと違う。不快にならないぎりぎりのところで捕らわれているような、どっちつかずの気分になる。
「いつも、本当にありがとう。君には負担ばっかりかけてるよね」
まとわりつくような甘い声だった。普段は緊張の方が目立つのに。
「僕が君を好きな気持ち、ちゃんと伝わってるかな。いつ愛想尽かされるかわかんないって、毎日不安なんだよ?」
握ったままの手の甲を、自らの頬に擦りつける。昔漫画でよく見た、段ボールに入れられた子犬のような上目遣い付きだ。
すでになかなかの破壊力を発揮している。これで全力なのか、まだまだなのか。
「そんなことあるわけないだろ? 本気で好きだから告白だってしたんだし」
それでも、あくまで日常生活の延長のつもりでいきたい。自ら望んだのは確かだが、ただ享受するばかりでは対等じゃない。
「……ほんと、君の言葉って不思議。すごく信じられるんだ。すごく、安心する」
自然に距離を詰められ、抱き込まれた。わずかに速い心音に口元が思わず緩む。
「だからかな、僕にできることなら何でもしたい。君の願いを全部叶えてあげたい」
背中にあった両手が顎を掬い上げる。まっすぐに与えられる視線から摂取できる糖分の限界値は、とうに超えている。めまいでも起こしてしまいそうだ。
「ねえ、僕にしてほしいこと、ない?」
「わざわざ言わなくたって、充分してもらってるよ」
「僕は足りない」
とん、と肩を押されて、気づけば彼を見上げる体勢になっていた。いつも使っているソファは意外に固いんだなと、どうでもいい感想を内心呟いてしまう。無理やり意識を逸らしていないと今すぐ抱き潰してしまいそうで、安易にその選択肢をとるのは嫌だった。
「僕がどれだけ、君に夢中なのか……知らないでしょ?」
「わかってるけどな」
触れるだけのキスを終えた瞬間、彼の瞳が頼りなげに揺れた。どうやら心の奥に巣くった不安は、相当しつこく根付いているらしい。
「俺も夢中じゃなかったら『お願い』聞こうなんて思わないし、『わかってる』なんて言えないだろ?」
「でも……」
キスを返して、頭を包むように胸元へ引き寄せた。くせの弱い髪は相変わらず、指に簡単に絡まる。
「告白した時以上に好きになってる。できるんなら四六時中こうやって一緒にくっついてたいし、いっぱい愛したいって思ってるんだからな」
シャツを掴む手にぎゅっと力が込められた。触れ合っている箇所すべてが妙に熱く感じるのはきっと、気のせいじゃない。
彼に感化されて、自分も相当恥ずかしい台詞を口にしている自覚はある。あくまで彼のためだ、悶えるのは一人きりになった時でいい。
「……ずるい」
くぐもった声は震えていた。
「僕より、君の方がトレーニングになってるんじゃない」
「はは、そうかな」
「本気で、君なしじゃ生きていけなくなっちゃうかも」
「そりゃ光栄なことで」
もっと愛されるよろこびを味わって、二度と離れられないところまでいけばいい。
少なくとも、自分はとっくにそうなっているのだから。畳む
【300字SS】世界でたったひとりだけ
#BL小説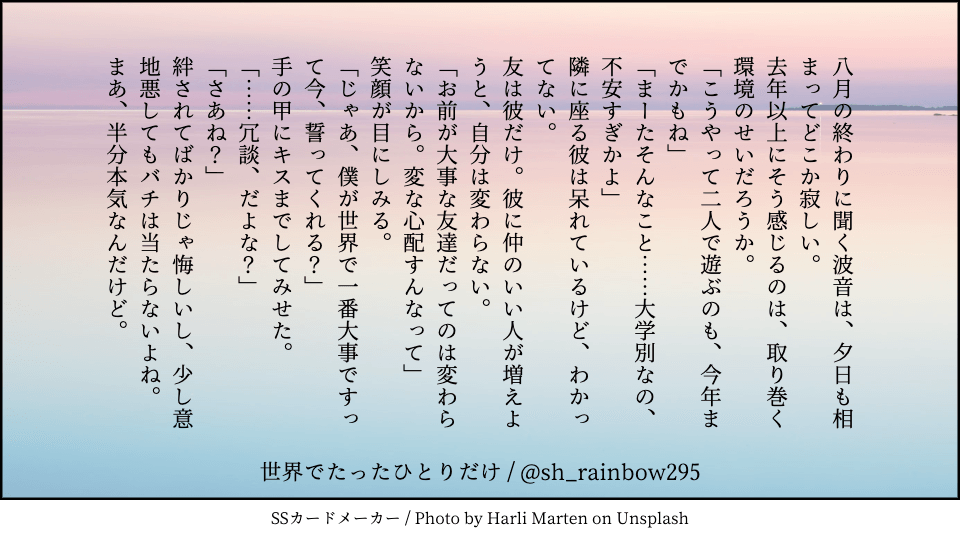
300字SS のお題に挑戦しました。お題は「波」です。
めっちゃ遅刻しました💦
ほんのりBL要素ありです。
続きを表示します
-------
八月の終わりに聞く波音は、夕日も相まってどこか寂しい。
去年以上にそう感じるのは、取り巻く環境のせいだろうか。
「こうやって二人で遊ぶのも、今年までかもね」
「まーたそんなこと……大学別なの、不安すぎかよ」
隣に座る彼は呆れているけど、わかってない。
友は彼だけ。彼に仲のいい人が増えようと、自分は変わらない。
「お前が大事な友達だってのは変わらないから。変な心配すんなって」
笑顔が目にしみる。
「じゃあ、僕が世界で一番大事ですって今、誓ってくれる?」
手の甲にキスまでしてみせた。
「……冗談、だよな?」
「さあね?」
絆されてばかりじゃ悔しいし、少し意地悪してもバチは当たらないよね。
まあ、半分本気なんだけど。畳む
最後の嘘と願って
#BL小説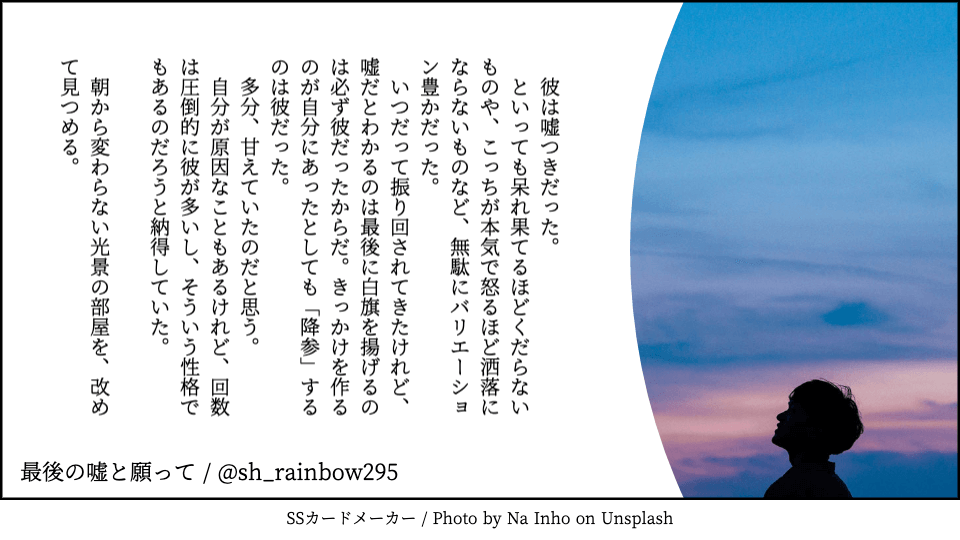
深夜の真剣物書き120分一本勝負 のお題に挑戦しました。
お題は「③西日が差す窓」を使いました。お題要素は軽く触った程度です😅
どうしてもユーミンの曲『最後の嘘』が頭から離れなくなってしまいました……該当の歌詞は「朝日が差し込む〜」なんですけどね。。
続きを表示します
-------
彼は嘘つきだった。
といっても呆れ果てるほどくだらないものや、こっちが本気で怒るほど洒落にならないものなど、無駄にバリエーション豊かだった。
いつだって振り回されてきたけれど、嘘だとわかるのは最後に白旗を揚げるのは必ず彼だったからだ。きっかけを作るのが自分にあったとしても「降参」するのは彼だった。
多分、甘えていたのだと思う。
自分が原因なこともあるけれど、回数は圧倒的に彼が多いし、そういう性格でもあるのだろうと納得していた。
朝から変わらない光景の部屋を、改めて見つめる。
昨日の夜はいつもと同じようでいて、主に自分自身の勝手が少し違っていた。
だから「きっかけ」を作ったのは間違いなく、自分。
「どうしたの、なんからしくないじゃん?」
軽口を叩き合う延長上のような口調だったのは、多分気遣ってくれていたのだと思う。それに真面目な空気にしたところで、素直に吐き出すわけもなかった。
「……うるさいな。ほっといてよ」
離れている間どういうことがあったのか察せなんて傲慢でしかないのに、そう願ってしまった。
仕事で嫌なことがあっただけ。いつもなら鼻で笑って流せるレベルが、今日はなぜか胸につかえてしまっているだけ。疲れが溜まっているせいかもしれない。
ここまでわかっていながら、彼には伝えなかった。悪い癖だ。
「あ、もしかして冷蔵庫にあったショートケーキ食べたのバレた? ごめん、どうしても食べたくって」
ショートケーキは確かに買ってあった。まだ確認していないが、たとえ嘘だとしても「甘いもの好きな自分のために、明日にでももっと美味しいケーキを買ってくる」という意味だったのだと思う。
そこまで推察できたのは、数時間後の未来でだった。
「嘘でも本当でも、ケーキくらい別にいいよ。……いいから、そういうくだらないの」
放っておいてほしかった。一晩すれば元通りになって、こんなやり取りにも苛ついたりしなくなる。
彼は何も知らないのに、あまりにも感情的になりすぎていた。
「……ごめん。何かあったんだね」
「そう思うなら、ほっといて」
それからどんなやり取りをしていたのか、細かいところは思い出せない。
ひたすらに、せっかく伸ばしてくれていた手を振り払い続けていた。ひどい態度だと頭のどこかで鳴っていた警報も無視して、気づけば部屋を包む空気はかつてないほどの重苦しさに溢れていた。
「……あのさ。俺と付き合ったこと、やっぱり後悔してるんじゃない?」
一言一句、声の調子も、表情も忘れられない。
笑っていた。雰囲気に似つかわしくないはっきりとした声だった。やせ我慢のようなものだったと今ならわかる。
反論できなかったのは、彼の問いかけが頭の中でぐるぐると回り出し、まるで必死に材料をかき集めているようだったから。
「……ごめん、嘘。だけど悪い、言い過ぎた」
ちょっと頭冷やしてくるよ。
それが、三日前に聞いた彼の最後の台詞だった。
「こんなに落ち込んでるのに、後悔なんてしてるわけないでしょ……」
今さらな返答だった。わずかでも口ごもった時点で、あの時の彼にとっては肯定されたも同然だ。
異性と付き合うのをやめて、初めてできた同性の恋人だった。好きという気持ちにあれから揺るぎはないものの、半年ほど経って同性なりの難しさや悩みが出てきていたのも事実だった。
隠していたつもりでもあんな言葉が飛び出すのだ、きっと見透かされていた。だから「頭を冷やす」と嘘をついて、出て行ってしまったのでは……。
「ほんと馬鹿だな、僕」
後になって後悔する癖は直る兆しが全くない。今日はまともに食事すら取れなかった。お出かけ日和の天気なのに身体は全く動かず、部屋の中は薄暗い。
そういえば、ベランダのカーテンを閉めたままだった。
『ここ、日当たりがすごいいいんだってさ。日当たり大事!』
その一声で借りることを決めた部屋だったのを思い出しながら、ベージュ色のカーテンを開ける。
「まぶし……」
真正面から浴びているような感覚に陥る。やたら目に沁みる気がして、ぎりぎりまで目蓋を下ろす。
窓を突き抜ける光の大元は朝も夕方も一緒なのに、どうして後者はやたらもの悲しい気分にさせられるのだろう。……違う。きっとひとりきりだからだ。二人でいる時の空気はもっと、穏やかだった。
――このまま終わりだなんて思いたくない。頭を冷やすが嘘だなんて、思いたくない。
目元を窓に押しつけた。光の強さとは裏腹にひんやりとした温度が、少しずつ熱を奪っていく。
「……まだ、決まったわけじゃない、よな」
近所を探しに行ってもいなかったのは、たまたますれ違っただけだと信じたい。
そもそも、仕事から帰ってきても部屋の様子に変化はなかった。何より、彼の荷物は全くの手つかず状態にある。スマホすら、未だテーブルに置かれたままなのだ。
今日は気力が底まで落ちてしまったけれど、いつまでも立ち止まっているわけにはいかない。
今度は自分が「降参」する番。
そして、こんな嘘はもう最後にしてとお願いしなければ。畳む
タグ「BL小説」[36件](3ページ目)
Powered by てがろぐ Ver 4.2.0.
template by do.
隣の幼なじみがマジです
#BL小説創作BL版深夜の60分一本勝負 のお題に挑戦しました。
使用お題は「吐息」「ゼロ距離」です。
-------
「いいよ。考えてやるよ」
もちろん冗談のつもりだった。
今まで自分自身そんな気配を感じたことは一ミリもなかったし、これからも起きるわけがないと信じていた。
彼は幼なじみで一番の友達だった。
普段は自分のあとをついて回る甘えん坊かと思えば、言うときははっきり言うし、彼が前に出るべきと己で判断したときの動きは全く迷いがない。
まさに「守り守られる」という言葉が似合う関係だった。
それが、なんだ。急に「ミツが好きだ」と真面目な顔で告白なんかしてきて。
「そういう意味で好きって、俺は違うぞ」
「わかってる。ただ、言ってみただけだから」
明らかに狙って言ったと、もちろんわかっていた。彼、ユウキは大事なことを「ついうっかりこぼす」性格ではない。
「まあ、これで友達やめるつもりはないけど」
「相変わらずわがままだな。俺が気持ち悪いから絶対いやだ! ってごねたらどうするんだよ?」
てっきり泣きついてくるかと思ったが、ユウキは熟考している。嫌な予感がするのは気のせいだろうか。
「二度とそんなこと言えないように無理やり説得しちゃうかも」
予感は当たっていた。本当に降参するまで諦めなさそうだから冗談に聞こえない。
「でも、どうするの? おれ、今のところ諦めるつもりは全然ないんだけど」
その訊き方は正直ずるいし困る。たとえば絶対友達以外ムリ! ときっぱり言っても意味がないということになる。
「どうにもならないだろ。お前と恋の始まりなんて見える気配すらないね」
しかし、よくも悪くも諦めの悪いのがユウキだった。
「恋の始まり……ときめき?」
顎を触りながら大真面目につぶやく。
「ほら、相手にときめきを感じたとき『これって恋?』みたいに自問するやつあるじゃん。それだ」
「待て待て、一人で勝手に話進めんなって」
さらに嫌な予感が強まった気がしてならない。
ユウキは一歩距離を詰めると満面の笑顔で見上げてきた。
「ねえ、ミツをときめかせられたらさ、おれと恋人同士になること真面目に考えてくれる?」
アホか、と切り捨てようとしてとどまる。
たぶん彼は諦めないであれやこれやと手を尽くして条件をのませようとするだろう。もっと面倒になるのは勘弁してほしい。
「いいよ。考えてやるよ」
絶対にユウキを親友以上の色眼鏡で見ることはない。
自分の感情を信じていたから、敢えて乗ってやった。諦めて今のポジションのままでいることを選ぶ未来しか見えていなかった。
「ほんと? ありがとう!」
語尾に音符マークでもついていそうな言い方ではあったが、まあ、しょせんは男だしな……。思わず苦笑がこぼれる。
「約束したのはそっちだからね。覚悟してよ?」
一瞬で、ユウキの双眸が視界を埋めつくす。緩やかな月を描いている。
「そんなに無防備で大丈夫? おれ、調子に乗っちゃうかもよ?」
唇に、吐息がかかる。すべての神経が奪われてしまったように身体が動かない、突き飛ばしたり茶化したりできない。
「まあ、ここで無理やりしても意味ないし、宣戦布告ってことで」
こんな刺激的な宣戦布告があるか。
――初めて、ユウキの恐ろしさが身にしみた瞬間だった。畳む